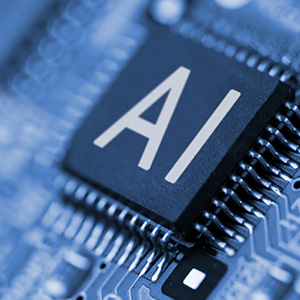2022.09.22 放送分
【オンラインイベント】ビジネスで活用するには?
第99回アートリーアカデミア
THEME
【オンラインイベント】ビジネスで活用するには?
今回のテーマは「オンラインイベント」。コロナ禍を経て爆増したオンライン参加のイベントは、ライブコマースの流行やメタバースの発展によりさらに市場を拡大していくと見られています。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- 今夜も始まりました、アートリーアカデミア。本日のテーマは、「オンラインイベントをビジネスで活用するには?」
- 井戸
- さっそくフリップを見ていきましょう。「オンラインイベントの種類」という参考資料になります。
- 蒲生
- 「オンラインイベント」とは、「パソコンやスマートフォンなどの通信機器を介してオンラインから参加できるイベント」を言います。こちらのフリップによると、オンラインイベントは「規模の大小」や「社内向けか社外向けか」、「参加費が有料であるか無料であるか」などを軸に大別できるそうです。なお、「全体的な市場規模」は「まだ不確定」ですが、昨年の「オンラインライブの市場規模」は「約500億円」、「『ZOOM』などを利用したウェブ会議」においては「約370億円」と「十分成長力のある市場」であることは読み取れます。そのため、この先「メタバース」などの仮想空間技術が発展していくことで、「アバターとして参加するオンラインイベント」というものも、「増えていくのではないか」と思います。……次のフリップに「オンラインイベントの成功例」をまとめています。
- 井戸
- 「オンラインイベントの成功事例」というフリップですね。最初が『東京ゲームショウ2021』ですね。このイベントは、「2019年まではリアル開催(会場は幕張メッセ)されていたものが、2020年からはオンラインで開催されるようになったそうです。ちなみに、2021年のものでは、「中国語の同時通訳付き」や「多言語字幕」などを用意したことで、総視聴数が20年を2割も上回る「3947万再生を記録した」とのことです。また、『資生堂』は、「コロナ禍による購買者意識の変化」に対応すべく、2021年には「200件のライブコマース配信」を行い、「顧客に対する高いエンゲージメントを維持している」そうです。
- 佐藤
- 39……。
- 井戸
- (39)47万再生。
- 佐藤
- 確かに、『東京ゲームショウ』は有名だものね。とは言え、「『資生堂』が200件もライブコマースやっていた」ことには、「ビックリする」よね。要は「単純計算でほぼ2日に1回のペースでやっていた」わけだものね?
- 蒲生
- 「連発して」いますよね。
- 佐藤
- 『資生堂』には「いろいろなブランドがある(※『資生堂』には全部で30のブランドがある)」から、「それぞれがライブコマースをやっている」みたいな図式なんだろうね。だけど、「ライブコマースを量産できる」ことは、世界的な化粧品メーカーである「『資生堂』だからこそできること」のように思うよね。
- 蒲生
- 実は『資生堂』は、「2017年から中国向けのライブコマースを先行していた」そうです。ところが、何の因果か「コロナ禍になった」ことから、「国内向けのライブコマースも始めた」というのが、事の真相のようです。
- 井戸
- だけど、「2017年」というのは「早い」ですよね。
- 佐藤
- ライブコマース自体が「グローバルな話」の上に、中国では「既に流行っている」と言うか「すごい市場規模」だからね。言わば「『資生堂』はそこへ参入していた」わけだから。だから、「災い転じて」ではないけれど、「実績があることで国内シェアも取りやすかった」んだろうね。
- 原
- 「絶対にマストな話」でしょうからね。
- 佐藤
- もちろん、「『資生堂』の売り上げも増えている」わけだよね?
- 蒲生
- おっしゃる通りで、コロナ前から「ECサイトで買っていた人もい」ますけれど、最近では、「身だしなみの一環」として「男性が化粧をすること」も「ある種の常識になりつつある」わけです。そのため、「実際の売り場で買うことに及び腰だった男性」が、「ライブコマースであれば質問しやすい」という具合で利用するケースも多いようで。だから、「男性顧客の新規獲得に成功した」という意味では、「『資生堂』の売り上げは増えている」と言えるかと思います。
- 佐藤
- そうなると、ライブコマースは「コンプレックスビジネスと意外と相性が良い」のかもしれないよね。
- 原
- 「人前に出しづらい話」をね。
- 井戸
- つまり「秘密にしたいものは買いやすくなる」よね。
- 佐藤
- そういうものは「意外とある」よね……。
- 渡邉
- 例えば「アダルトグッズ」辺りですか?
- 佐藤
- 確かに「それもある」だろうけど。とは言え、「間口は広い」だろうね。 (原)先生はいかが思われますか?
- 原
- 「ここのオンラインイベントすごいんだぜ」みたいな話は、「まだそこまで聞かない」ですよね。だから、「会社ごとの目立った打ち出し方がない」と言うか、「同じようなやり方をしている」ように思えるんです。だから、「企業ごとの運用方法が確立」されれば、この先の市場は「さらに広がっていく」ように思うんです。
- 佐藤
- ところで、俺は「結構ゲームをする」から知っているんだけど、『モンスト』などは前々から「オンラインイベントが強い」印象なんだよね。要は「幕張メッセなどに設営したリアルの会場」からの「ライブ配信を見ながら、プレイヤーは自分のスマホなどからオンラインでビンゴクエストに参加できる」みたいな感じで。確か「年末にお金が当たるキャンペーン」みたいなイベントもあったよね?(※おそらく「モンスト年末年始キャンペーン」の一環で行われた「モンスト年末BIGボーナスくじ」のことかと思われる)
- 久田
- (『モンスト』の場合は)「年末」などのいわゆる「ホリデーシーズン」は、「1時間に1回」くらいの頻度で「何かしらのイベントを開催している」こともありますよね。
- 佐藤
- 「年末の現金キャンペーン」みたいなイベントでは、「1位の人には1000万円ぐらい配っていた」よね?
- 原
- もはや「年末ジャンボ」みたいなものですね。
- 佐藤
- だから、「インタラクティブ要素のできるゲーム」なら、「オンラインイベントには強い」だろうね。
- 原
- 確かに、「親和性は高い」だろうね。
- 佐藤
- 「リアルの会場から芸能人が出演する番組を配信しながら、視聴者はビンゴカードのクエストを進めていく」なんて、「まさにオンラインイベントならでは」だよね。渡邉さんはどうですか? 「オンラインイベント」には参加したことがありますか?
- 渡邉
- ないですね。だけど、「ファッション業界のオンラインイベントの事例」で言えば、『MIU MIU』が面白いですね。『MIU MIU』とは、PRADA創業者の1人である「マリオ・プラダの孫娘」の「ミウッチャ・プラダの小さい頃の愛称」を名前に使った「PRADAのセカンドライン」です。分かりやすく解説するなら、「タツヒコ・ハラ」さんを『PRADA』とした場合、「タッちゃん」が『MIU MIU』に当たるわけですが。……話を戻すと、『MIU MIU』が「オンラインでどのようなファッションショーを開催したか」ですよね? 『MIU MIU』のオンラインファッションショーは、「雪山の天辺」のような「物理的・地理的に誰もが行けないところでやる」んですよ。……ちなみに、今回の(『VEDUTA COLLECTION』を)「延暦寺で行うこと」とも似ていて。なぜなら、「延暦寺も比叡山という山の上にある」わけで。だから、「誰もが気軽に来られない場所である」から、「オンラインイベントとしてやること」が「メリットになる」わけで。あとは、『MIU MIU』の事例で言うと、「リモート会議風のファッションショー」なんてものもあって。要は『ZOOM』などのビデオ通話アプリは「画面が参加者の数だけ分割され」ますよね? あれが「ファッションショーの背景になっている」と言いますか、「見ている人を背景にランウェイが行われる」ので、「視聴者もファッションショーの映像に映る」んですよ。それから、「CGと組み合わせ方」の上手さで言えば、「『フェラガモ』も面白かった」ですけど……。
- 佐藤
- 確かいつぞやのこの番組で話したような記憶があるんだけど、「コロナ禍がまだ完全に先行き不透明だった頃」に、「アメリカのプロレスを中継で観た」のだけれど。その時は、いわゆる「無観客試合」みたいな状況で、「会場でレスラーが闘っている」のだけど、「実際のお客さんはいな」くて。代わりに「全ての観客席にモニターが置かれていて、「『ZOOM』のような感じ」でチケットを購入した観客が観戦していたんだよね。(※おそらく2021年6月24日放送の第34回『オンラインライブ』の際に話していた「海外のプロレスがすごかった!」という話のことだと思われる。)
- 井戸
- 要は「モニター越しに視聴者が一人一人 映っている」わけですね?
- 佐藤
- 「実際の会場に観客はいない」のに、「歓声はすごい」し、「他の観客の表情も分かる」から。だから一瞬、「これって、リアルだよね?」と錯覚しそうになると言うか……。
- 原
- 少し前に「どこも個性のある打ち出し方を見つけられていない」みたいなことを言いましたが……。……ごめんなさい。実際には「オンラインイベントは様々な開催のされ方をしている」ことがよく分かりました……。
- 佐藤
- 確かに、それぞれが「独自の解釈でオンラインイベントを開催している」みたいな印象はあるだろうけど、未だに「コロナ禍」ではあるわけだから、「オンラインイベントの需要は、この先もどんどん広がっていく」ような気はするけどね。
- 原
- 要は「距離を感じさせない」というところが重要になるわけですね。確か、前回「現地行かなきゃいけない」みたいな話をしたように思いますけれど……(※正しくは前々回(2022年9月8日放送の第97回『グローバル社会』))。その時に「現地に行かなきゃ分からないこともある」なんて言いましたけれど、現実には「現地行かなくてもできることが増えた」わけですから、「物理的な距離に縛られることなくイベントに参加できること」は、「プラスに働く」わけですからね。
TOPICS
テーマ討論
- 佐藤
- それに「リアルに対する付加価値がより高くなる」だろうね。そもそも(オンラインイベントに)「様々な活用方法があること」は、「もはや当たり前になりつつある」よね。……そろそろ、本題に戻りましょうか。「オンラインイベントをビジネスで活用するには?」ということで。七菜子はどうですか? アートリーのビジネスで「オンラインイベントをどう活用していくか?」と問われた場合……。
- 久田
- それこそこの間、「延暦寺に行った」んですけれど。想像以上に過酷で、「行けない方もいるだろうな」とは……。
- 井戸
- 「過酷」とはどういう意味?
- 久田
- 文字通り、「過酷」なんですよ! 移動する道のりの「酸素が薄い」と言うか、「高低差がすごく」て……。(※比叡山の標高は848mある。)
- 井戸
- ある意味「高地トレーニング」なのか。
- 久田
- だから、「汗だくになって、ずっとハァハァ言いながら移動していた」わけですが。だから、「行きたくても行けない方は絶対にいる」だろうなと思って。延暦寺は「世界遺産にも認定されている」ので、「一生に一度は行っておきたい」と思われる方はいると思うんですよ。だけど、(延暦寺は)「そもそもが観光地ではないので、スロープもほとんどない」んですよ。だから、実際に行った時は、「足腰が不安になってきた」みたいな理由で「行けなくなっている」人たちに対して「オンラインの社会的価値」と言いますか、「オンラインを通して現地の様子を伝えられること」の価値を「すごく感じ」ました。それから、先ほど原先生が、「物理的な距離を無視できる」なんておっしゃっていましたが。そこが「オンラインイベントの1つの強み」であって。「箱の制限を受けない」ことが……。例えばオンラインイベントの中には、「(現地と)一緒にクッキングできる」みたいな形式のイベントもあって……。とは言え、「キッチンスタジオのあるイベント会場」は「限られる」ので、「参加人数制限」なども設けられたりするわけですが。しかし、「自宅のキッチンから自分の使い慣れた道具を使いながらそのイベント見て、一緒に料理に参加できる」のであれば。「人数制限の解消」もそうですが、「イベント会場で火を使える」みたいに「好き放題参加できる」と言いますか(笑)。例えば「スキンケアのブランド」の場合、実際のイベントでは、「参加者は既にメイクをしている」ので、「自分の顔で直接スキンケアを試せない」んですよ。だけど、「オンラインイベントで自宅から参加できる」のであれば、「試供品を手元に送ってもらえればそのまま試せる」ので。だから、「箱の制限がない」と考えれば、「やれることは一気に広がるだろうな」と思います。
- 佐藤
- ということは、「オンラインイベントのほうがリアルよりも可能性があるかもしれない」ということか……。「ビジネスで活用するには?」ですが、徹郎さんはいかがでしょうか?
- 蒲生
- オンラインイベントそのものが「リアルで活動するよりも敷居が低い」と言えるでしょうね。要は「場所代などがかからない」と言いますか……。だから、私の個人的な意見を言わせてもらうと、各企業は(オンラインイベントを)「低コストの実証実験」として「様々なところでしていくべき」だと思います。
- 佐藤
- その場合は「既存のプラットフォームを使って」ね。……仮に「自前で用意して」しまうと、「サーバー代」や「アプリケーション開発費」などが「諸々かかってしまう」からね。
- 蒲生
- だから、「展示会などでのライブ配信」のような形で「場数を踏んでいけば良い」ようには……。
- 佐藤
- 「展示会はナイスアイディア」だよね。何より「上物を建てなくて済む」わけだから。
- 久田
- (展示場は)「既に建てられている」わけですからね。
- 佐藤
- 既に「場所が整備されている」だけで……。だから、「実際の費用感も安くなる」わけだよね。「既存プラットフォームを利用する」のであれば、「基本的な費用は安く抑えられる」わな。改めて、(原)先生はいかがでしょうか?。「オンラインイベントをビジネスで活用するには?」ですが。
- 原
- いずれは「中小企業もオンラインイベントを当たり前に開催する」ようになるだろうとは思っていて。……おそらく前提は「オンラインイベントで集客するには?」だろうとは思うので。なぜなら、オンラインイベントの効果や威力を知らない企業からすれば、「集客するための広告費用=固定費」みたいな感じだろうから。だけど、「オンラインイベントにおける集客力」みたいなところが分かれば、「中小企業でもできる話」ではあるだろうから。要するにこの先「オンラインイベントが当たり前になっていく世の中」になるのであれば、物販だろうが何だろうが「中小企業の思うようなB to Cの裾野もさらに広げやす」くなるようには思って。それこそ、オンラインイベントは「年間で何万件どころか何十万件、もしかしたら何百万件と開催されている」わけですよね? そうなると、「オンラインイベントがどこでやっているのか分からない」みたいな事態も起こりうるわけですよね? だから、そうしたところを「検索できる」ようになれば、「こんなものもやっているんだ」みたいに……。
- 佐藤
- つまりは「ポータルサイトのようなサービスを」ということ?
- 原
- ふと、「そうしたものが出てくれば便利だろうな」と思いまして……。
- 蒲生
- タイミング良く「中小企業におけるB to Bの話」が出たついでに補足をしますと。例えば、前々回のテーマで取り上げた「グローバル化における販促」でもオンラインイベントは「利用でき」ますし。あとは「今日はモロッコ向けのオンラインイベント」や「明日はアメリカのどこどこ州向けの」みたいな形で連発も可能ですよね。
- 佐藤
- 確かに「ローカライズはさせやすい」だろうね。あとは「セグメントも切りやすくなる」だろうね。要は「リアルイベント」の場合では「1件開催するにも諸費用がかかるから大変」になってしまうし、仮に「間口を狭めても数を打てない」から、「割と間口を広めに取る」しかないのだけれど……。とは言え、「オンラインイベント」であれば! 確かに、「手軽にやること」は「前提にはなる」だろうけれど、そこを逆手に取れれば、「狙いのターゲット層」……。例えば、「『年代』や『国』などに応じたイベントを量産できるようにはなる」だろうから。要するに「オンラインイベントはハードルを低く始められる」ことが強みな分、中小企業も「徐々に参入してくる」だろうとは思うけどね。……事実、「リアルのイベントや展示会などでもそう」だとは思うんだよね。要は、「実際のイベントをきっかけに、積極的にビジネスに活用していく」という形になるような気がして。言い換えると、「オンラインから入って、実際のイベントを増やしていく」と言いますか……。
- 原
- 要は「これまでのリアルイベントに対しては興味のなかった人」に対して、「オンラインイベントを介させる」ことで、「こんなのもあるんだ!」と思わせることで、「実物を見たい」みたいな動機で、「実際の展示会に誘引できる」みたいな感じで、「相乗効果を期待できる」と言いますか……。
- 佐藤
- 「リアルに誘致するため」というアイディアは「確かに良い」よね。
- 原
- そうですよね?
- 佐藤
- とは言え、考え方によっては「ホームページみたいな役割」にはなるだろうね。言うなれば、「いつでも見に来れる」と言うか……。
- 原
- すいません、話の流れを遮ります……。言いたかったこととしては、(現状では)そもそもオンラインイベント自体を「自力で探さなければならない」ことが「ネックになっている」ような気がするわけですよ。だから例えば『インスタ(グラム)』のように、「検索ウインドウから引っかけられる」ようになれば、「知らない人にも届けられるようになる」わけですから、「従来以上の集客を見込める」ような気がするんですよ。
- 佐藤
- 詰まるところ、現行の検索エンジンで、「検索したいワードを入力」すると「それに関連する動画やニュースが上がってくる」みたいな感じで、いずれは「現在配信中のオンラインイベント」みたいな感じで……。
- 井戸
- 「(ハッシュ)タグ」みたいな感じのね。
- 佐藤
- 「表示される」ようになれば、(オンラインイベントは)「なお一層活性化される」だろうね。仮にそうなるとすれば、「オンラインイベントに対するマーケティング」も「しやすくなりそう」だよね?
- 原
- 言い換えれば、「新しいマーケティング層が開拓される」ような気もしますよね。要は「オンラインイベントによる新規顧客の流入」は、ある種の「新規開拓」のわけですから。だから、「オンラインイベントが普及する」ことで、各社の手法も「どんどん増えていく」でしょうから……。
- 佐藤
- 渡邉さんはどうですか。「オンラインイベントを活用していきたい」とはお考えですか?
- 渡邉
- 「活用していきたい」です。(2022年)10月10日(の『VEDUTA COLLECTION』)を皮切りに、「世界中に向けてどんどんやっていきたい」です。なぜなら、「知ってもらわなければ、いくら作っても届かない」ので。ちなみに、オンラインイベントは「物理的な距離を超えられる可能性しかない」ので、「積極的に取り入れていきたい」です。
- 佐藤
- 1つ尋ねるとするなら、「どうやって活用させていくか?」だろうね。要は「オンラインイベントを開催していく」上では、「単に配信すれば良い」わけではなく、「イベントに参加している感」も必要になるわけだから。ということは「確実にインタラクティブはセットになってくる」だろうから。例えば、「自分がアクションを起こすことで、リアルの会場に何らかの変化がある」であったり……。あるいは、「自分がアクションすることで、そのプラットフォーム上の集団に対して何らかの行動を起こせる」であったり……。だから、「相互通信のできるオンラインイベントプラットフォーム」を開発できれば。「IT業界の未来は明るい」ように思うけれど。とは言え「ビジネスで活用するには?」だから、「逆パターンから考えなければならない」わけだから……。
- 原
- そもそも、オンラインイベントを開催する上で重要になるのは、「使ってもらう側」だものね。それに、言ってしまえば我々はむしろ「業者側」……。
- 佐藤
- オンラインイベントで取り扱う商品が「新製品」であれば、「マーケティングにも使いやすい」かもしれないよね。要は「ちょっとした広告を打つ」だけでも集まってくれる「ロイヤルカスタマーやファン」に集まってもらうことで、「あとの布教を任せる」と言うか。狙いとしては、「イベントがやっている」ことに「少しでも関心のある人」であれば、「(オンラインイベントが)やっているのなら、試しに行ってみようか?」みたいなノリで「誘引しやすい」と言うか。かえって「予定を組んでしまう」と「本当に根っからのファンしか来ない」みたいになりかねないから。「オンラインイベントと広告を活用」させることで、「シームレスに動線を引ける」よね。「今やってます!」みたいな内容で広告を「常に配信した」としても「流入が見込める」みたいな……。だから、各企業は「オンラインイベントを積極的に活用していくべき」のような気はするよね。言うなれば、「情報収集」や「情報価値の擦り合わせ」であったり……。
- 久田
- 確かに。(オンラインイベントの場合は)「反応がすぐに返って」きますものね。
- 佐藤
- 例えば、「アンケートを取る」みたいな感じでね。実際、うち(アートリー)のシステムでも、「オンラインライブ中にアンケート飛ばせる『サーベイ』」みたいな機能を開発したよね?
- 井戸
- やりましたね。
- 佐藤
- 今年(2022年)の「ビッグサイト」の展示会でね。
- 原
- つまりは、「選択肢が広がった」分だけ、先ほど私が言ったように、「新規のターゲット層を開拓していく話」になるわけだから……。
- 佐藤
- 「良いワードが出た」ね!
- 原
- そこ(新規層に対する開拓)が「かなりピンポイントにできる」ことは、「ありがたい」ですよね。要は「モノを売りたい」や「サービスを提供したい」という思いをワンストップで届けられるから……。しかも「どこの層が狙い目か」をズラしたりしながら試せることも「メリットの1つ」でもあって……。おまけに、「あまりコストをかけずにできる」ことがすごく「魅力的」だと思うし……。
- 佐藤
- 「イベントは認知を集めやすい」からね。だからそこは結構「ミソ」のようには思えるよね。ただ、同時に「段取りをしっかりと組んでおかなければならない」んだよ。なぜなら、「オンラインイベントは基本的に『生配信』」だから。もちろん、「撮ったものをあとから編集することも可能」だけれど、それ(録画済のデータを編集したもの)は、「アーカイブとしての作品」という「コンテンツになる」から。確かに、「価値として利点」は、「今を共有していること」にあるのだけど、「きちんと動線を踏めるような施策」は仕込んでおかなければ……。要するに、「事前の計画などを強化していく」必要があるのだろうけれど……。
- 原
- アートリーさんの場合は、元々が「オンラインイベントに強かった」ところが、「さらに強まる」わけですよね? 要は「どこもかしこもがオンラインイベントをやるようになってくる」と、「ニーズに応えられる制作会社が求められる」ようになるから。だから、「動線の作り方」と言いますか、「間違いなくプロデュースしますよ」みたいなところも「ますます求められていく」わけですよね。
- 佐藤
- その話は、「オンラインイベントをビジネスとしてするには?」みたいな前提でしょうけど……。確かに、うち(アートリー)にとってはその辺りは「得意領域」にはなるだろうけど。そもそも、「それを狙ってやっている」ところもあるわけだけど……。だから、(オンラインイベントに対して)「可能性はある」とは思っているけどね。なぜなら、「基本的に市場が世界中に無限とまでは言わないけれど、それなりの規模ではある」からね。
- 原
- だから、蒲生さんがおっしゃったように、「国を跨げる」わけですよね? そこが「すごく強い」と思って……。
- 佐藤
- そこも(ワールドワイドに向けて)「同時通訳者を呼ぶ」などの段取りを一通り組んでおいてこそ、「開拓が可能になってくる」わけで……。「開拓」という表現は「結構気に入った」な……。……そろそろソリューションタイムに入りましょうか。
TOPICS
ソリューション
- 井戸
- お願いします。
- 佐藤
- 本日のソリューションはこちらです。「ユーザーの開拓に活用しよう!」。……ここまでの話を聞いてくださった方からすれば、「当たり前」かもしれないけれど、日頃こうしたものに「アクセスできない方」からすれば。例えば、「インターネット」であれば、「今までのイメージ」であれば、「ホームページ」や「動画」みたいな次元だったわけだけれど……。「オンラインイベントが主流」になれば、「新しい層を取り込める」わけだから。「イベントとして参加する」ことも非常に良いだろうし、自社のプラットフォームの1つとして「常設させて何らかの企画を立ててどんどんやっていく」というのも「1つの手」だよね。もちろん、「スタートは『YouTube』」みたいな感じでも「悪くはない」だろうね。 要するに、「イベントを上手く活用して、ビジネスを躍進できれば良い」と言いますか……。さらに「海外向け」という目標を掲げてやっていけば、「夢が出てくる」から……。……結局、「当たり前の話」で終わったね……。
- 原
- すばらしいです。
- 佐藤
- ありがとうございます。
- 井戸
- よろしくお願いします。
- 佐藤
- (徹郎さんは)いかがでした?
- 蒲生
- オンラインイベントは「好き」なんですよ。
- 井戸
- 結構見られていますか?
- 佐藤
- 今までどういうものを見てきたの?
- 蒲生
- 実は私は「私物の『Oculus Go』……、いわゆる『VRゴーグル』を持っている」のですが……。 ちなみに、『YouTubeライブ』で検索をかけると、「『VRカメラから現在配信中』みたいな結果が出てくる」んです。だから、そうした配信動画を渡り歩いた場合、1時間あれば、「サグラダファミリア(スペイン)」と「カッパドキア(※トルコの世界遺産。巨岩に開けられた無数の横穴で有名)」、それから「アンコールワット(カンボジア)」に行けますね。
- 佐藤
- それは「現地にいる人が配信している」の?
- 蒲生
- そうです。
- 佐藤
- アンコールワットから?
- 蒲生
- えぇ。要は「素人」が(と、蒲生、「自撮り棒を使って撮影中」のポーズをする)
- 佐藤
- 要するに「観光客が(配信している)」(ということ)?
- 蒲生
- そういうことです。だから、「VRではない」にしろ、今後は「誰もがスマホから手軽に見られるようになる」ことで、「オンラインイベントを開催する」みたいな配信者も世界中に増えているので、(オンラインイベント自体が)「より身近になっていく」でしょうし、「オンラインイベントのある生活」が一般的になれば、企業はそこに倣っていくものでしょうから……。
- 佐藤
- 「ソリューション」の話にも繋がるけれど、いざ「オンラインイベントをやろう」という時に、「どうやってユーザーを集めるか」が焦点になるように思うんだよね。だけど、「実際は違う」んだよ。本当のところは「企画だけ」で十分なの。今回の(『VEDUTA COLLECTION』出演をかけたモデル)オーディションもそうだけど、「良い企画を立てれば、ユーザーのほうから自然と寄ってくる」わけよ。もちろん、「それ(『VEDUTA』のモデルオーディション)に参加してもらうための方法が「投票」という仕組みであって……。要は、「どうやって集客をした上でオンラインイベントを開催するか」ではなくて、まずは「オンラインイベントを開催する」ことが大事なんだよ。言わば、「オンラインイベントを開催する」ことで、「自然とユーザーが集まる」から。そこを「リスト化させていく」ことで、「次なるオンラインイベントやマネタイズに繋がっていく」のだろうと思います。
- 原
- 要するに「入口が全然違ってくる」わけだよね?
- 佐藤
- そうだね。少なからず広告なども関わってくるとは思うけれど。そうしたことは「ビジネス的には企業秘密」だったりしますので……。
- 原
- つまり、「ここから先はここでは言えない」わけね。
- 佐藤
- ここから先は、いわゆる「続きはウェブで」ということで。
- 井戸
- お問い合わせ先は!(と井戸、「概要欄下方にURLがあるよ!」という動きをする)
- 佐藤
- 「お問い合わせ」ということでお願いします。
- 井戸
- お待ちしております。来週以降の放送はこちらの通りとなっています。次回も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また来週もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
コミュニティサイトがマーケティング戦略の中心に!強力なコミュニティを形成してビジネスを成長させるには
2024.06.15 放送分
ダイナミックプライシングで収益最大化?リアルタイムに変動する価格戦略で企業の競争力を高めるには
2024.06.07 放送分
MFAサイトが生成AIで量産される!悪質なコンテンツファームに負けないマーケティングを成功するには
2024.05.10 放送分
ビジネスをゲームチェンジ!ゲーミフィケーションで顧客体験を変革するには
2023.11.09 放送分