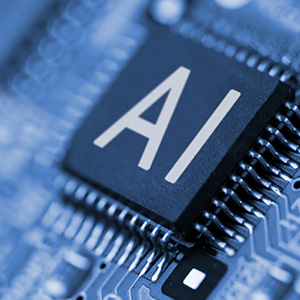2022.09.15 放送分
【ブランディング】誰もが成果を生み出すには?
第98回アートリーアカデミア
THEME
【ブランディング】誰もが成果を生み出すには?
今日のテーマは「ブランディング」。サービスやコンテンツが乱立する現代。複数のサービスなどを展開する上では、今や欠かせない概念となりつつある。今回も「誰もが成果を生み出すには?」をメインテーマに据えて話は進んでいく。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- 今夜も始まりました、アートリーアカデミア。本日のテーマは、「ブランディングで誰もが成果を生み出すには?」
- 井戸
- さっそくフリップを見ていきましょう。「ブランディングとマーケティングの違い」を表した資料です。
- 蒲生
- 広義の意味では「販売促進の活動」……。要は「マーケティング活動の一環としてのブランディング」というものもありますが。「視点の違い」としては、このフリップでは、「マーケティングは、「自主的に発信をしていく」ことで……。イラストでは、男性が「僕は頭が良いです」なんて言っていますが……。つまり、「マーケティングは能動的」なんです。一方、「ブランディング」は、何かしらの理由をきっかけに、女性が男性に対して「あなたは頭が良いと思います」というようなイメージを持っていく……。要するに「受動的なイメージ」……。だから、「受動的なマーケティング手法を『ブランディング』と呼ぶ」という定義付けになっています。
- 佐藤
- 詰まるところ、「マーケティング」は「自分から発信すること」で、「ブランディング」は、「マーケティングの結果なりを根拠に、『相手からこう思われる』こと」だということかな? だけど、これらは「同時に成り立つ」から、「本来は対比的に描くものではない」だろうね。
- 蒲生
- 続いては、「企業のブランディングの活用事例」のフリップです。
- 井戸
- 「ビジネスの活用事例」というフリップですね。『無印良品』は、「奇抜さを狙わない」というコンセプトで商品を開発しているそうです。また、『バーミキュラ』は、「商品の『高価格・高付加価値』を提供すること」をブランディングのモットーに据えています。さらに、『レッドブル』は、「翼を授ける」という「飲んだ人に焦点を当てた打ち出し方」をしています。
- 蒲生
- 「私が(佐藤)社長と何年か前に東京のセミナーに行った時」の話になりますが。記憶に残っている話の1つに、「『無印良品』は、『様々な料理を食べてきたけれど、一周回ってお茶漬けが一番おいしいよね』みたいなことを社内のコンセプトにしている」というようなものがあって。だから、「消費者にとって『シンプルイズベスト』に映る商品が置いてある」わけだよねみたいな話を聞いたように記憶していて……。それから、『バーミキュラ』は、「競合他社の同等・類似商品よりも高価格」なのですが、その製品のスペックは、「生活に劇的な変化を与えるほど高品質」なんですね。だから消費者は、「これを買えばさらに料理が楽しくなるのでは?」や「家庭に楽しい要素を取り入れられるのでは?」などのイメージを植え付けていく戦略なんです。ちなみに、『レッドブル』は、言わずもがなの「エナジードリンク」ですが、その成分には一切触れず、「飲んだ人に向けた体験」を……。もはや説明するまでもない「翼を授ける」という有名なキャッチコピーがありますけれども……。要は「飲めばパワーアップできるのでは?」という「イメージをブランディングをしている」と思われる事例になります。(※おそらく『レッドブル』の場合は、「製品の含有成分に言及」してしまうと、販売国によっては、いわゆる「薬事法(医薬品の品質や安全性について定めた法律)系統に抵触してしまう」可能性があるため、「ボカした表現をしている」と思われる。)
- 佐藤
- 要は「コンセプト押し」の話だよね?
- 原
- 世間で「ブランディング」が意識されるようになってから「かなり経つ」けれども、私からすれば「イメージ戦略の1種」ように思えます。要は「消費者に向けて、『この製品やサービスを使うとどうなるか?』というイメージを植え付けよう」と言いますか。言い直すと、「ブランディングの有様」ではなく、「製品やサービスの使い方に焦点が絞られている」と言いますか……。
- 佐藤
- だけど、「そういうこと」だよね。そもそも「ブランディング」の対象には「ビジネス」だけでなく、「個人もあり得る」から。例えば、「丈亮ってどういう人?」や「萌ってどういう人?」みたいに。だから、一言で言えば「分かりやすくしていくこと」なんだよ。なぜなら、「分かりにくいものは他人から受け入れられにくい」から。そうは言っても「分かりやすいから選ばれるとも限らない」けれど。とは言え、「分かりやすくすること」で、「選ばれやすくはなる」から。だから「ブランディングの本質」は、「商品」や「会社」、「ビジネス」などを「分かりやすくするための手段」なんだよ。
- 原
- 要するに「触れたり使ったりしてもらいやすいようにするための入り口」なわけですね?
- 佐藤
- だから、「あらゆるビジネスプロダクトにおいて使っていくべきもの」のようには思うのだけど……。
- 原
- 要は、ここまでの話は「商品に対するブランディングの仕方の話」だったけど、「会社のイメージ」も「ブランディングできる」わけですよね? 実際、「アウターブランディング」や「インナーブランディング」なんて言うものね……。
- 佐藤
- 必ずしも「お客さんに向けたもの」だけでなく、「中側(社員)に対しても必要」だからね。
- 原
- そういうことなのでしょうね。
- 佐藤
- 渡邉さんも「ブランド(『VEDUTA』)を展開されて」いますけれど、どうお考えですか? 一例として『無印(良品)』、『バーミキュラ』、『レッドブル』と3社が挙げられていますが、これらに対しては「どのような見方をされ」ますか?
- 渡邉
- アパレルのブランディングには、「必要な成功の秘訣」が2つありまして。それは「コンセプト」と「ターゲティング」なんですよ。もちろん、「どのメーカーさんでも同じ」だとは思いますが。ちなみに、「コンセプトやターゲティングを明確化させるための分析手法」には、「3C分析」と「SWOT分析」の2つあって。「3C(分析)」は、「カスタマー(顧客:Customer)」、「カンパニー(自社:Company)」、「コンペティター(Competitor)」は「競合」か。だから以前に(『アートリーアカデミア』の出演者の)皆さんとは「お話した」かもしれませんが。要するに「世の中に何があって、自分は何ができるのか」を分析して……。ちなみに、「SWOT(分析)」の場合は、「自身の強み(Strength)と弱み(Weakness)」、「機会」は「Opportunity」か。それから、「Threat」だから「脅威」ですよね? だから、結局は「3C分析の上位版」みたいな感じですが。そもそも海外に行った時に、「和服のストリートファッションみたいものがない」ことは「既に分かっていた」ので、「競合がいない」ことは「分かっていた」し。僕は「佐渡島の生まれ」なので、「伝統的な価値観の根強いところで育って」いますが、「最先端のトレンドも好き」なので。だから、「(古いものと新しいものを)組み合わせて作ろう」という感じで「コンセプトを築き上げた」わけです。ちなみに、「ターゲット」には「経営者が多い」印象ですかね。実際、(出演者の)皆さんも『VEDUTA』は手に取られていると思いますが、「人と違うものが欲しい」であったり、「クオリティに対しても目が肥えていらっしゃる方が多い」と言いますか。それから、もう1つ付け加えるなら、「心を豊かにできるような作品を作りたい」と思って制作をしています。
- 佐藤
- ちなみに、「コンセプト」という面ではいかがですか? この3社(『無印良品』、『バーミキュラ』、『レッドブル』)においては、「奇抜さを狙わない」や「高価格・高付加価値」など……。
- 渡邉
- 僕も最初は「コンセプトは奇抜なほうが良い」と思っていたので。例えば「柄物」の場合は、丈亮さんも持っていらっしゃる「クリムトの柄(※グスタフ・クリムトの『接吻』をあしらった『Klimt』という浴衣のこと)」のような「『大胆な柄』で行こう!」と思っていました。なぜなら、「小さな花柄をあしらった浴衣」は、言ってしまえば「ありふれて」いますが、「大きな柄がドーンと付いているもの」は「あまりなく」て。だから、「むしろそういうことをやっていこう」と思って。だけど、それ(大振りの柄がドカンと付いたデザイン)だけでは、「ハデ過ぎて普段は着れないよね……」となってしまうので、「カウンター要素」として『Essentials』や『Fear of God』(※2 どちらもアメリカのファッションデザイナー、ジェリー・ロレンゾが手がけるアパレルブランド)のような、「スウェット生地で、ワンポイント的にロゴが入って」いて、「普段着としても着やすいように、カラーバリエーションも黒とグレーのみで」というような商品(※3 おそらく『Life goes off』というセットアップのことと思われる)も展開するようにして。だから、「和服がベース」というところは「揺るがざる骨子」となっていますが、「多角的にやっていく」ことは心がけています。
- 佐藤
- 要するに「それが既にブランド」というわけですね?
- 渡邉
- そういうことです。要は「和服デザインの洋服」や「和柄のアロハシャツ」というようなものは「意外とある」ものですが、『VEDUTA』のような「逆転の発想」をしているものは「あまり見かけない」ので。だから、「他と被らない」という意味合いでも「強い」わけです。
TOPICS
テーマ討論
- 佐藤
- そろそろ、本題(課題)に戻りましょう。 (本日の課題は、)「ブランディングで誰もが成果を生み出すには?」ですが。七菜子はブランディングについてどう考えていますか?
- 久田
- 丈亮さんや渡邉さんのように、「何らかの思いがあって、ブランディングを始められている方」というのは、おそらく「無意識的に実現できている」わけですよ。要は、「こういったものを表現したい」や「こうしたニーズを叶えられるものがないから、これを実現させて、こういう世界にしたい」というような「ビジョンがある」ことで……。
- 佐藤
- 要は「こういう存在として見られたい」という思いがあるからね。
- 久田
- だから、「そうした方々」においては、「既にブランディングが成り立っている」わけですが。しかし、「B to B」や「量販」のように、「何か思いがあるからそれを作る」のではなく、「市場があるからものを作っている」という人たちは「ブランディングを迫られて困り果てる」というような傾向があるらしくて。だから、「取り立てて特徴はない」とする人たちに、「ブランディングさせていくことは非常に難しい」と言いますか……。要は「立ち位置をどこに置いて、 何をブランディングしていくべきかが分からない」という話を「案外耳にする」ので。だから、そうした方に、「どうやってブランディングの観点を探していくか?」をずっと考えていて……。
- 佐藤
- 一言で言えば、「ブランドを消費する」に尽きるだろうね。……「消費する」というと語弊を招くかもしれないから言い直すのであれば、「ブランドを体験すること」になるかな?
- 井戸
- 「ブランドを体験する」とは?
- 佐藤
- 確か「いつかの回で言った」ような気がするけれど、「ブランドを体験しなければ、自分のブランドは作れない」から……。
- 久田
- 「他のブランドに触れる」ことで……。
- 佐藤
- そうでもしなければ、「魅力的なブランドは作れない」からね。分かりやすく「魅力」なんて表現したけれど、「まずあるべきは分かりやすさ」だから。そこを踏まえた上で、「他社ではなくて自社を選んでもらうための工夫を何かしら施していける」わけだよ。だからそれが「ストーリーやビジョンになる」のだろうとは思うけど。だけど、それ(自社でなければならない理由)が「見えていない」ということは、コンセプトなり何なりの「社会との結びつきが弱い」のかもしれない。だから、「伝統技術を詰め込んだ箸」があるとして。だけど、箸なんて「世の中にはいくらでもある」わけだよね? だから、「それ(伝統技術を詰め込んだ箸)を選んでもらうための何かしらの理由付けをしていくこと」が、「付加価値」と言うか「ブランディング」なんだよね。要は「形のない価値」が「ブランド」と呼ばれるわけだから。
- 佐藤
- 例えば、「この(伝統技術が詰め込んだ)箸を使うと、環境保護に貢献できるので、やがては地球の環境を豊かにします」みたいなメッセージを伝えられれば……。だけど、「それも誰もがやっている」から、「効果が弱い」と言うか「出遅れている感が否めない」と言うべきか。だから、「伝えたいメッセージをより具体化させていくことで……。例えば、「ユーカリでできているので、次第にコアラを救えます」みたいに……。
- 井戸
- 「具体化させていく」わけですね?
- 佐藤
- そういうこと。要は「コアラをどうこう」と言った時点で「ブランディングが成立する」わけよ。とは言え、「コアラの保護に興味のない人には「コアラに興味ない人には刺さらない」わけだけど、一方で「コアラ好き」や「コアラを含めたあらゆる動物好き」などに対しては、「この箸を買うだけでコアラを1頭でも救えるのであれば……」みたいな感じで「買ってもらえる動機になる」わけだよ。だから、そこが「ある種のブランディング」と言えるわけで……。とは言え、「現実的にはむちゃくちゃなことを言っている」のだけど……。
- 渡邉
- 丈亮さんのおっしゃる通りですよね。「アパレル」における「どの服を選ぶかを決める判断基準」には、「機能性」と「デザイン」の2つがあると言われていまして。だから、「最大の 差別化」が必要とされているわけです。要は、戦後以降の日本には、「機能性やデザイン性で優れた服は「既にたくさんある」わけですよ。なので、そこに加える付加価値として「何が必要なのか?」と問われれば、「感情に訴えかける表現」というわけですよ。それがいわゆる「哲学」や「バックグラウンドストーリー」になっていくわけですよね。つまり、「これらがいかに確立されているか」によって、「誰かの共感を得られるようになる」わけです。……ちなみに、「ユーカリから箸を作って」しまうと、むしろ「食料不足によってコアラを絶滅に追いやって」しまいますが……。
- 佐藤
- だから、「むちゃくちゃなことを言っとる」と自虐したわけで……。(※おそらく「1膳の箸を買って、オーストラリアの砂漠化進行地域にユーカリの苗木を植え、コアラの生息地を守りましょう!」というような内容であれば、差し支えはなかったと思われる。ちなみに、「コアラのエサ」というイメージの強い「ユーカリの木」には600種類以上があるものの、コアラが好んで食する種類は30種類ほどしかない。そのため、「コアラが食べない種類のユーカリ」であれば、「箸の素材としても問題はない」と言える。)
- 渡邉
- だけど「おおよその言いたかったこと」は理解しました。
- 井戸
- 要するに「要素としてプラスアルファのストーリーを加える」ということですね?
- 渡邉
- 要は「どこで誰がどうやって作ってきたか」みたいなところを「伝える」わけですよ。野菜などでもよくありますけど、例えば「ハヤシさんが作ったトマトです」みたいに……。
- 久田
- そうは言っても、「『今自分が作っているものに特にこだわりはない』し、『会社も祖父が興したものがそのまま続いているから自分が継いだまで』です」みたいな人たちもいるわけですよね? だから、そうした人たちに、「その商品は何のために社会に出すのか」や「どうやって社会に関わっていくのか」を教えていけば良いのですか?
- 佐藤
- 少し前にナベちゃんが「SWOT(分析)を活用している」なんて言っていたけれど……。だから「SWOT(分析)」で言うところの「(自社の)強み」を……。例えば、「孫子の兵法」にも「己を知って敵を知れば百戦危うからず(※正確には、『彼を知り己を知れば百戦殆うからず』)」とあるように、「何はなくとも最初に自分を知ること」が大切なわけで。要は「社会にどのような価値を提供できているのか」を知ろうと言いますか……。だけど、そのためには「様々な要素を分析しなければならない」わけで。だから、「どのようなブランディングをすれば良いか分からない」なんて言う連中は、「自身の目指すところも分かっていないオタンコナス」としか言えないんだよ。要するに大切なのは「その背後にどんなストーリーがあるのか」を伝えることで……。例えば、4〜5年ぐらい前に、『カメリア』さんというパン屋さんの案件を手がけたことがあるのだけど……。その時は、「お宅にはどんな歴史があるんですか?」や「『カメリア』とはどういう意味ですか?」みたいなことをヒアリングして。それで、「『カメリア』とは『ツバキ(椿)』のことなんですよ」のような回答をしてもらって、そこから「イメージ」や「ストーリー」などの世界観を作ったり、逆に「世界観からストーリーを作った」りすることもあるけれど。だけど、何にせよ「ブランドがない市場」であれば、「頭1つ抜けられる」だろうね。そうは言っても、「ブランドだらけの市場」の場合は、「多様化させねばならなくなる」から、「さらにターゲットを絞り込まなければならなくなる」けれど……。
- 佐藤
- 「誰もが」という観点から見た場合、(原)先生はいかがお考えになりますか?
- 原
- 実際、「すごく難しいな」と思っているところはあって。それこそ、「いろいろな企業に顧問税理士などの立ち位置から携わっていると、「モノやサービスを売りたい・提供したい」という思いはあるのだけど、少し前におっしゃられていたような「コンセプト」や「歴史」と言った「自社の価値をそもそも知らない人たち」が「実はすごく大勢い」まして……。
- 佐藤
- 確かに、「そういう可能性もある」かもね。
- 原
- 実は「2〜3カ月ぐらい前に お客さんのところでそういう出来事があった」んですよ。要は、経営陣が「うちの会社はこういう打ち出し方をしているんですよ!」と言っていたのですが、実際の現場にいる従業員たちは「全く知らなかった」んですよ。要するに、「会社側としては 打ち出しているつもり」だったのに、「見かけ倒しで終わっていた」わけです。「中に対してアピールできていない」ということは、況やをやで、「外に出せていない」わけです。だから、その会社としては、「アピールの手法をさらに工夫していく必要があった」わけです。それか「やり方自体をそもそも手入れしておく必要があった」ように思うんです。つまり、「インナーブランディングが揺るぎなく構築されていること」が「誰もが成果を生み出すために必要なところである」と思うのですが……。
- 佐藤
- だけど、「極端な例え話」をすれば、「人口が100人しかいない村でパン屋を経営していた」としていた場合、(需要と供給のバランスは)「成り立っている」わけだから。だから、「その状況で『ブランディング施策を講じた』」としても、「100人以上の来店はあり得ない」わけで。だとすると、代わりにできそうなことは、「パンの消費頻度を上げる」ぐらいしかないだろうし……。つまり、「そもそもマス(市場)を相手にしなければ、成果は出ない」のかもしれないね。せめて「地域ぐらい」の規模ではなければ。だから、「そもそものブランディング戦略にもよる」のかもしれないね。
- 佐藤
- 何かヒントはありますか?
- 蒲生
- 要するに、「ファンを構築していくこと」ですよね?「誰かのファンだった経験は誰しにもある」と思うので、「それを思い出してみる」であったり……。例えば、「好きな映画」などでも構わないので、「そのストーリーや世界観を自社に投影できないか?」と考えてみるであったり……。だから、「誰かのファンである経験を因数分解していくことが鍵」のように思いました。
- 原
- 詰まるところ、「趣向の差を出す」のかな?
- 蒲生
- 「ファンコミュニティ参加した」場合、大勢のファンが、「あれが良いよね」、「これが良いよね」というような会話がされているわけですよね? 要はその(ファンコミュニティならではの)空気感を「自社の要素として持ってくる」わけで……。
- 井戸
- 要は「自分が(会社の)一番のファンになる」ということですか?
- 蒲生
- そうではなくて、「自分がファンになっているもののコミュニティで会話をしている」と、「自分はこのポイントに対するファン」だけど、「BさんやCくんはまた違う視点や理由からファンである」こともあるわけですよね? だから、そうしたところをヒアリングしていって、「ブランドの人格」? ……「ブランドアイデンティティをどうやって構築していくか」だろうと思います。
- 佐藤
- そうね。「『成果を生み出す』には」だからね。だけど、「誰もが」というところが「ハードルを上げている」よね。
- 原
- 「入り口からお尻のところまでを踏まえて」が「成果」だものね。とは言え、「それぞれの切り口はある」からね……。
- 蒲生
- 例えば、「SNSのフォロワーが継続的に増えて」いれば、「良い商品なのでは?」と思わせられますよね?
- 井戸
- 確かに、「ブランディング」としては……。
- 蒲生
- 要するに、「噛み砕いて言え」ば、「要素の1つ」として「フォロワーを増やすこと」は「あり」だとは思うんです。なぜなら、「SNSのアカウントを持っていれ」ば、「誰でも 挑戦できる」からです。そのため、渡邉も「ストーリーなどを考えながらアップしている」からこそ、「現状フォロワーが増えている」わけですよね?
- 渡邉
- 名古屋市出身の方が作ったアイウェアのブランドに『INARI』という名前のところが ありまして。そこは最初は「すごく大きなサングラスを作っていた」ので、「INARIと言えば、『でかいサングラス』だよね」だったのですが、今や「『でかいサングラス』と言えばINARIだよね」となっていて。そもそも「ブランド」自体が「印」という意味なので。だから、「ビジネスでの活用事例」というフリップで『無印(良品)』が挙げられていましたが、あれ(『無印良品』)は「印がない」という意味なので。言い換えると「誰もが普遍的に使えるものが印になっている」わけですから……。実際、『Essentials』や『Fear of God』は「スウェット」や「パーカー」、「Tシャツ」などの「誰もが着れるものしか作らない」という「普遍的なブランド」ですが……。要するに、「ブランディングが必要ない」と言うか「印を持たないブランドもある」し、「印を付ける」のであれば、「誰が作りました」というところが重要になって。要は「ブランド」というものは「ある種の印鑑」なので。だから、「印鑑の持ち主の人となり」や「誰を巻き込んで 作っているのか」が明確化されていれば「選びやすい」と言いますか……。
- 佐藤
- 要するに、「市場を一旦置いておく」にしても、 「まずは不要なものを削ぎ落としていく」ということだよね?
- 渡邉
- そうです。「(散らかっている要素は)整理しなければダメ」です。
- 佐藤
- 今回の冒頭で、「マーケティングとブランディングの違い」というフリップがあったから、「かえって分かりにくくなった」感が否めないけれど、「ブランディング」は、「マーケ ティングを踏まえた上で成り立つもの」だから。つまりは「ブランドを構築していく1要素」という捉え方になるのかな? だから、「ごちゃ混ぜになっている要素がある」場合は、「不要なものを全て削ぎ落としていく」必要があるんだよ。要は「要素がたくさんあると、そこを踏まえて構築していくことに大変な労力を割くことになる」と言うか、新たな「上流工程」や「上位概念を作らなければならなくなる」んだよ。要は仮に、「ホームページを作ります。名刺も作れます。システムも作れます。動画も撮れます」とした場合、「すごく分かりにくい」よね?
- 井戸
- 「一体、ここは何屋さん?」となりますよね。
- 久田
- ぼやけちゃう!
- 佐藤
- そう。もはや「何屋か分からない」よね。だから、注力していきたい事業が「動画制作」の場合は、「動画制作だけでブランディングしていく」ことを求められるんだよ。例え、目立たずとも続けていけば、「動画制作に関することなら、あの会社に相談すれば頼りになるよね」みたいな感じで「選ばれやすくなる」わけだよ。だから「不要なものを削ぎ落とす」か「さらなる上位概念を作るか」の2択になるわけだよ。だけど、どちらの選択をするかで「ターゲットが少なからず変わってしまう」から。例えば、「今、あれもやってます。これもやってます」みたいになっていると「散らかって仕方がない」わけだから。だから、うち(株式会社アートリー)では「ソリューション」という言い方をしたり、「IT」という言い方をしてみたりいろいろあるのだけど。とは言え、中には「名刺制作」などの「ITなのか?」と思うものもあるから。だから、そうしたものは、「いっそのこと省いたほうが分かりやすいよね」ということもあって……。要は、「ブランディングと合致しないことはやるな」ではなくて、「ブランディングのためのプロモーションの中には入れるべからず」なんだよ。確か、先ほど渡邉さんが「印」なんて言い表わしたけれど、まさに「そういうこと」なんだよ。だから、「成果を生み出したい」のであれば、「断捨離」ではないけれど、「一思いに削ぎ落としていくこと」が、「答えになる」ような気がする……。
- 原
- 要は「シンプルな本質に持っていく」ために「ひき算をしていく」ということですか?
- 佐藤
- ご明答!
- 渡邉
- ちなみに僕は「1人での外食の際は駅前の店には絶対に行かない」んです。確かに、「複数人で集まるから、アクセスの良さで選ばないとね!」となった場合は「行く」けれど、「1人の時」は「確実に駅前から離れたところ」へ行くんです。そもそも「駅前」という「人流にこびた戦略を取っている」時点で、「大したことはない」ことが分かっているので。だから1人の時は、「多少駅前から外れたところにあっても人が集まる食堂」みたいなところに行くんです。それに、「案外そうしたお店のオムライスやラーメンのほうがおいしい」というようなこともあるので。それから個人的には、「メニューが『中華そば』のみ」のようなお店は最高ですね。確かに、「味噌や豚骨など様々なメニューを楽しめるお店も誰かと行くのであれば楽しい」ですが。とは言え、「うちはこのメニューに魂を注ぎ込もうと決めたので」みたいなスタイルを貫くお店には「その道のスペシャリストです!」という「強い意志」と言いますか「ブランドらしい感じがする」ので好印象ですね。
- 佐藤
- 確かに、「ブランド戦略的」としては「それが正しい」ものね。
- 原
- 「明確化される」ので、ね。
- 佐藤
- そういうこと。だから、仮に「それ以上のことをしよう」と思ったとすると、例えば「IT」というジャンルに絞ったとしても、「ブランドポートフォリオ戦略」ではないけれど、「それぞれに対してブランディングしていく必要が出てくる」わけだよ。だから必然的に「名前を付けていく」みたいなことになったりして……。だからアートリーでも昔は『狼煙』や『7S』と銘打って……。
- 井戸
- 確かに、「サービスごとに名前を付け」て……。
- 佐藤
- 分かりやすいように「動物の写真を使って」ね。ちなみにあれ(アートリーが個々に名付けていたサービス群)は「全部まとめて『BREMEN』」みたいなこともしていたけれど。……確かにあれは、「あの当時のブランディングだった」わけだけど。とは言え、「少なからず時代が変わった」から、「もういらないな」と思って「捨てた」わけだけど。だけど、それを1つずつやっていくことは「手間でしかない」わけだよ。そもそも「ブランディングをしている」時点で、「競合と比較されることが前提」のわけだよね? その場合、「『サービスを提供する母体』である会社そのものは、『どんなブランディングをしているのか?」という話になるわけで。だから要は「アートリーはソリューションを提供しています」みたいになるわけで……。
- 佐藤
- だから、今回延暦寺で行う『VEDUTA COLLECTION』もそうだよね。あれは「モデルたちの景色を集める」という「『ある種のブランディング的な考え方のファッションショー』としてやる」わけだけど……。だけど、それ(『VEDUTA COLLECTION』)を内包する存在である『伝燈LIVE』は、「(文化や伝統の)明かりを伝えていく」という「さらに上位の概念としてブランディングしている」わけで。だから要は「階層的」に……。
- 原
- 要するに、「単純に明確化させていけば良いわけではない」のか。
- 佐藤
- 確かに、「分かりやすくしていくこと」は「最優先」だけど、「捨てるばかりでは成り立たなくなる」んだよね。要は「『カレーライスだけ』や『オムライスだけ』を提供していく戦略であれば構わない」のだけれど。そうは言っても「飲食チェーンとして様々な系列店を経営していく」とした場合、そこには少なくとも「『グループ会社としてのコンセプト』みたいなものが必要になっていく」わけで。
- 原
- 要は「企業に対するブランディング」と「事業に対するブランディング」をそれぞれ 組み合わせることで、「それぞれを明確にさせながら、企業のコンセプトも明確にさせていく」わけだよね?
- 佐藤
- 大切なのは、「同時に発信しないこと」なんだよ。なぜなら、「同時に発信すると、かえってわけが分からなくなるから」なんだよ。もちろん、「オムライスしか認知させなくて良い」のであれば「構わない」けれど……。とは言え、「念入りなファンやユーザー」は、(お店を)「選ぶ」時点で、「このお店の経営母体はどんな取り組みをしてるのか?」みたいなことまで「調べる」から。だから、(自社を)「知ってもらうためのきっかけや道筋を作っておく」ことで。(彼らが)「辿り着いた」時に、「このお店の運営会社はアニマルウェルフェアに取り組んでいるんだ」みたいなことを認知して、「つまり、オムライス屋さんの中でも『商品の品質にこだわっている』わけだから、試しにちょっと行ってみようか」みたいになるんだよ。
- 原
- 要は「興味を掻き立てる」わけだよね? だから、「カスタマージャーニー」と言うか……。
- 佐藤
- 要は そこまで行き着いて初めて、「体験を設計していく」わけだよ。
- 原
- ということは、今回の『伝燈LIVE』は「まさに」というわけか。
- 佐藤
- ここは「公の場」だから、「戦略的の中身などはあまり言いたくない」けれど……。とは言え、「結構組み立ててはいる」よ?
- 原
- 本当に「今年一番注力しているイベント」ですものね。
- 佐藤
- 宣伝していただいてすいません。……そして、「CM(告知)に繋がって」いきます!
- 井戸
- 筋道の立て方が上手いですね。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- よろしいでしょうか?
- 井戸
- お願いします。
- 佐藤
- 本日のソリューションはこちらです 「伝えたいことを整理しよう」。結局、「ここまで話していたことに尽きる」よね。要は「全てがごちゃ混ぜになっている」と、「結局何を出したかったのかが分からなくなってしまう」から。だから、「整理をする」ことで、「これはこっちにグルーピングできるね」や「こちらは単発にしかならないね」みたいに「区別できる」ようになるんだよ。その上で、「それぞれをブランディング」していくことが「筋」なんだよ。要は、「不要なものは整理の段階で弾けば良い」わけだし、そうすることで、結果的に「収益性にも繋がって」きて、それが「成果になってくる」わけだから。つまり、「ブランディング」とは、「選ばれやすい状況を作っていくこと」のように思います。ありがとうございました。
- 佐藤
- ところで、『VEDUTA』は、「本当に分かりやすいブランディングがされている」よね。
- 渡邉
- とは言え、最初の頃は、「自分の中でもやりたいことが散在していて、はっきりしていなかった」んですよ。それで、「自分のやりたいことを明確化させなくては!」と思い立って、手始めに「自分の家」と言うか「部屋を掃除した」んです。その際に、「いらない服は後輩にあげる」みたいな整理の仕方もやってみて……。例えば、「すごくお世話になった人は別」として、「1年以上連絡を取ってない人の連絡先は『LINE』から全て消す」であったり、「いつも100枚持ち歩いていた名刺を2枚だけにしてみる」であったり……。だけど、不要なものの断捨離をしたことで、「スティーブ・ジョブズ」ではありませんけど、「決断が早くなった」んです。例えば、「朝から出かける」にしても、「散らかってる部屋で支度をする」場合と「不要なものが何もない部屋で支度をする」場合では、「完了するまでの速度が違う」んです! そもそも、「お客さんは『自分のことを分かっていない」のだから、まずは「身の回りの掃除」と言うか「整理整頓」をしていくべきだと思います。(ちなみに、スティーブ・ジョブスは、「余計な選択に思考回路を持って行かれないため」という理由で、「『イッセーミヤケ』の黒のタートルネック」、「『リーバイス』のジーンズ」、「『ニューバランス』のスニーカー」を複数用意し着回していた)
- 佐藤
- 複雑になってくると「IQの心底高い人物」とまでは言わないけれど、「真に難しいことを考えられる人からしか理解されなくなる」ものね……。
- 原
- そうだよね。
- 佐藤
- とは言え、「あえてそこを狙う」のであれば、それも「1つの方法にはなり得るかもしれない」けれど、おそらく「あえて狙ってそう(複雑に)はなっていない」よね?
- 原
- おそらく、「結果的にそう(複雑に)なってしまった」のでしょうね。
- 渡邉
- ちなみに僕は「お客さんが特に喜んだ作品だけを抽出して」いますね。例えば、「ファスナー付きの着物」や「書をあしらったもの」などの「反応が良かったものは残していく」と言いますか……。だから、「お面のマスク(『Face 2 Faith』のこと) 」も「バージョン違いでまた出そうかな?」なんて思っていて……。特に最初は、「売れるか売れないかも分からず世に送り出している」ので、「フィードバックは回収して」います。
- 佐藤
- これからも「『VEDUTA』に期待」ですね。
- 井戸
- ありがとうございました。来週以降の放送はこちらの通りとなっています。次回も木曜日の夜10時にお会いしましょう。来週もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
コミュニティサイトがマーケティング戦略の中心に!強力なコミュニティを形成してビジネスを成長させるには
2024.06.15 放送分
ダイナミックプライシングで収益最大化?リアルタイムに変動する価格戦略で企業の競争力を高めるには
2024.06.07 放送分
MFAサイトが生成AIで量産される!悪質なコンテンツファームに負けないマーケティングを成功するには
2024.05.10 放送分
ビジネスをゲームチェンジ!ゲーミフィケーションで顧客体験を変革するには
2023.11.09 放送分