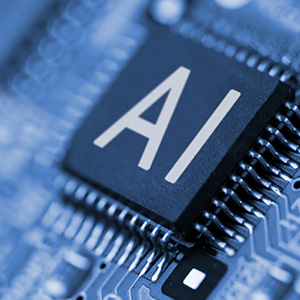2024.04.11 放送分
グリーンオーシャン戦略で開く新たな市場!社会課題をビジネスチャンスに変えるには
第180回アートリーアカデミア
THEME
グリーンオーシャン戦略で開く新たな市場!社会課題をビジネスチャンスに変えるには
社会課題をビジネス機会に転換し、新たな市場領域であるグリーンオーシャンの概念と戦略について議論します。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、今夜のアートリーアカデミアは。
- 井戸
- 「グリーンオーシャン戦略で開く新たな市場!社会課題をビジネスチャンスに変えるには」。グリーンオーシャン戦略とは、社会的な課題解決をビジネスのチャンスと捉え、その解決を通じて新たな市場を創出する戦略を指します。社会的責任、CSRや持続的可能な開発目標、SDGsの達成にも寄与するため、現代のビジネス環境において特に重要性が増しています。
- 佐藤
- またちょっとマニアックなキーワードっていうか、ビジネスワードを拾ってきちゃったんですけど、グリーンオーシャン。調べてみると結構いろんなオーシャンあるみたいで。みんながそれぞれ言ってて。グリーンオーシャンもいろんな定義がある中で、今回テーマにするのは公益性を、社会課題を解決しながらビジネスにしていくっていう。エコっていうかサスティナブル、SDGs、社会的責任っていうところを全うしながらやるって、最近の潮流の中の市場っていうところでグリーンオーシャンっていうものを今日話していきたいなというふうには考えています。その前にどういったオーシャンが世の中あるのかっていうのをおさらいでいきたいと思います。
- 井戸
- さまざまな市場環境です。五つありまして、ブルーオーシャンが競争が少ない新しい市場、レッドオーシャンが競争が激しい既存の市場、ブラックオーシャンが競合他社が存在しない独占的な市場、ホワイトオーシャンが競合他社に認識されていない未開拓の市場。本日行うグリーンオーシャン、これが公益性と事業性を両立して成り立つ競争的な市場とされています。
- 佐藤
- ブラックオーシャンは一番メインなワードであって、レッドオーシャンっていうのもよくいわれるよね、最近は。それぞれ意味としては、ブルーオーシャンは本当にまだ誰もあんまりやってない市場っていうか、のイメージなんだけど、レッドオーシャンっていうのは既存のライバルが多い市場っていうところで、ブラックオーシャンもこれもいろいろ定義があったんですけど、イメージ的に深海のイメージみたいな、暗い、光が届かないみたいな。だから光が届いてない、だからまだ見えてないとか、それと見えてるんだけど敷居が高い、深海だから届かない、だからなかなかやれない、そもそもやるにあたって利権だとかそういうものが必要なブラックオーシャン。だから独占的な市場っていう意味になりやすい。深海魚とかでも独占的な進化をしてたりだとかするしっていうようなイメージなんだよね。で、ホワイトオーシャンっていうのは多分ブラックとの反対語で生まれたような言葉なんだけど、見えてない市場。大体白い海なんてものはないから、だから認識されてない、未開拓の市場っていうようなイメージだよね。伝説的な、ユニコーン的なイメージかもしれないね。で、今回やるのはグリーンオーシャン。競争的な市場っていうところで、エコなイメージのグリーンっていうところから多分きてるはいると思うんですけど。これ、どうですか、先生。いろんな市場がある中でグリーンオーシャン、今回どういうところを注目したいですか。
- 原
- 一般的に上場会社もそうですけど、ESG経営を求められているところがどうしても、このグリーンオーシャンっていう言葉に私の中で引っかかってくる要素、兼ね合いがどうしても入ってくるので、そこら辺で上場会社とかをここら辺のグリーンオーシャンへの参入のさせ方っていうのをすごく考えるのかなっていうふうに思うところ。でも一方で、中小企業が入ってくるときの公益性っていうけど、一般的に言う公共とかそういった部分にどうやって入っていくのかっていうところが、市場の拾い方がなかなか理解しにくいところもあったりするんだけど、でもここら辺って動き回りやすい事業体だからこそ、むしろ入りやすい部分もあったりするっていうのは、市場性としての部分は、興味はあるところですよね。
- 佐藤
- ありがとうございます。次、フリップ、手順っていうものがあるので、グリーンオーシャンの開拓の仕方っていうところで勉強していきましょう。
- 井戸
- 戦略実行の手順です。大きく三つのフェーズに分かれていまして、それぞれのフェーズで2段階ずつあります。まず市場と社会課題の同定のフェーズでは、市場調査をしてグリーンオーシャンの認知をしていきます。次にステークホルダー分析とエンゲージメントのフェーズでは、ステークホルダーの認知をしてエンゲージメントを構築していきます。最後にビジネスモデル開発のフェーズで、社会課題の解決と利益創出を検討し、サスティナブル化していくといった流れになっています。
- 佐藤
- 難しそうに見えてポイントになるのが公益性、共創っていうことなんで、ステークホルダー、いわゆる企業と関係するものだよね。だからお客さんとかもそうだし、取引企業とかもそうだし、地域の人たちもそうだし、行政もそうだし。そういった方たちが、自分が参入したいグリーンオーシャン、参入したいビジネスにどうかかわってくるのかっていうのを考えなきゃいけない。で、その人たちと人間関係っていうか、こういうことをやろうと思ってんだけど、協力してくれるかしてくれないか、どこまでやってくれるか。だからそこの部分はキーになってくるから、エンゲージメント、関係性を構築していくっていう。で、3段階目って言ってるんだけど、そっから利益を創出できないと企業としてはやる意味がないので、最初に投資する期間は長くなるようなイメージにはなるんだけど、そっから回収できるスタンスだとか、回収できるようなスキームが考えれるかどうかだよね。強いて言えば、さらに言うと、サスティナブル化、持続可能な末永いビジネスになっていくかどうか。っていうところまで考えられるといいのかなっていう感じですね。これ、毛受さんどうですか。
- 毛受
- グリーンオーシャン自体はすごく言葉としては興味があって、これからの時代、ここの部分を自分自身でも取っていけたらいいかなっていうのは思うんですけれども、ただ具体的にどういう行動を起こしてこのビジネスを作っていくかって考えたときに、ちょっとわかりづらいなっていうのは正直思います。誰と何を何の問題を解決したらいいのかっていうところからなので、それは公益性っていうところも割と難しい、難しいっていうか定義が曖昧な気がしてしまって。ただ、ここを取っていく企業っていうのは企業イメージもすごく上がると思うので、時代をちゃんと見ているなっていうイメージはあります。
- 佐藤
- それこそ前回やった逆プロポなんかが、結構このグリーンオーシャンなんじゃないのかな。
- 毛受
- 自治体と一緒に作っていくっていうところではそうですね。
- 佐藤
- だから市場調査、グリーンオーシャン、認知って書いてあるんだけれど、いきなり新規で何かやるっていうよりは、今やっている事業をどう拡大するかとか、今持ってるサービスとかプロダクトを、どうやってこのグリーンオーシャンに参入させていくかっていうかたちがイメージ近いのかなっていう。多分そういうことだと思うんだよね。例えば、前も話したと思うけど、モンクレールなんかでも品質管理番号みたいなやつがついててとか、偽物と本物のやつを区別できるQRコードで追えるみたいなプラットフォームあったりするから、そういうサービス展開してるよ。それ自前でやってるところもあるし、そういうサービスを展開してるIT系の企業があったりだとかっていうのもそうなんだけど、それは例えば品質管理のものだとか、生産者のところまで追っかけてますとか、わからんけど、例えばそれも公益性っていうかサスティナブル。それをもうちょっと、例えばサービスを持ってたとしたら、どうやって社会の、もっと人に役に立ってもらえるようなかたちにできるかみたいな。服だけじゃなくて、もっといろんな人が利用してもらえるためにとか、わからんけどね。いずれにしても競争していくっていうことなんで、こないだ話した逆プロポなんかでもすごくマッチするし、自社完結でやるっていう感じじゃないよね。基本的に前提がアライアンスになる、事業アライアンス。三方よしの考え方ができるといいのかなっていう感じかな。
- 原
- それこそ先ほどおっしゃられたように、自分のところで持ってる事業体自体がどこまで公益性の部分に反映させられるかっていうところなので、提案する内容は限定列挙になると思うんですよ。あんまり広く公益性って考えちゃうと、何でもかんでも公益性なので、それじゃなくて、自分のところの事業に隣接する、じゃあ社会に一番みんなが喜ぶの何?っていうところで入っていくっていうところで、前回の逆プロポもそうなんだけど、多分提案型、本来は提案型なんだけど、欲しい部分のところで拾ってもらうっていう需要は高くなると思うんです、地方公共団体から。
- 佐藤
- 結構それこそ、スタートアップっていうか、創業、起業する方たちって何かしら社会課題を持って起業する方って多いと思うんだよね。フリーランスとして稼いでやるとかいう、ああいうデザイナーとかそういうのじゃなくて、一般的なっていうか、まあ一般的だよね。だんだんやっていくうちにいろんなものに追われてとか、いろんなことを考慮しなきゃいえなくなってくるから、だんだん社会の課題を解決するっていうのが多分薄まっていっちゃうんだと思うんだけど。だし、そこを今までやろうと思ったら、結構本当にいろんなステークホルダーとつながってとかいうのが必要だったじゃん。で、今、逆プロポがあったりだとか、ああいう、それこそユニークベニューを活用してとか、それこそインターネットでSNSがとか、リーチしやすくなってるから、すごく社会とすぐにアクセスできる状況になったから、すごく今までよりもいい、やりやすいと思うし、過去何十年っていうか、これまでとは。ましてや、こういうことを言いだしてきてるから、社会とか行政機関もウェルカムな姿勢になってきてるし。今まで手つかずだったぶん、解決できることっていっぱいあるし。しかもこれって、解決しきれないんだよね。経済、文化、人類の発展だから、社会って。文化の上に社会があるから、だからどんだけ発展してもさらに先の発展に向けて課題っていうのは尽きないから、だから企業がなくならないのも一緒だし。だからここのスキームが組めると、ビジネスっていうのはどんどん展開していけれるのかなっていうのはある。
- 原
- 私独自の解釈なんですけど、日本の文化の大切さみたいなものって、市場主義だったり、資本市場主義のところで結構減っていってるっていう認識なんですけど、このグリーンオーシャンってそういうのを再度見直す市場だと思っているんですね。日本のよさみたいなものをもっと打ち出していくことができれば、例えばそれって先々にあるのって、外国の方にもっと観光で来てもらったりとか、そういうものにもひもづく部分であったりとかするんですけど、今ってそういうのってそんなに、じゃあ公共性があるかって、市場があるかっていうとないなんですけど、ここでグリーンオーシャンの発想が出てくると、そこら辺はリンクしやすくなるんじゃないのかなって思うんです。
- 佐藤
- いい面だけの話をしてもあれだから、リスクっていうか課題っていうか、フリップを最後に用意したので見ていきましょう。
- 井戸
- グリーンオーシャンの課題です。グリーンオーシャン戦略の実装は企業にとって大きな機会を提供する一方で、多くの課題に直面します。代表的なものに四つ挙げられてまして、資金調達の難しさ、ステークホルダーとの協働の複雑さ、社会的価値の測定と評価の困難さ、市場と規制の不確実性といったものが挙げられています。創造的な思考、持続可能なビジネスモデル、強固なステークホルダー関係、そして長期的な視点が必要となります。
- 佐藤
- これ、七菜子さんどうでしょう?
- 久田
- もう社会課題として認知されてる、みんなが知ってる課題に対して取り組む。じゃあ、何でその課題って残されてるのかって、難しいから残ってるんであって。よし、手を出してみようっていうわけにはいかないんだろうなっていうのはすごい思う。
- 佐藤
- 本当に数え切れんぐらいあるし、細分化したらどの領域を取るかっていうだけでも違うし。
- 久田
- でもこれから先、イノベーションが必要になるとかっていわれているときに、じゃあ何に対して取り組めばいいのか。結局こういうことですよね。
- 佐藤
- そうだね。やれることないよねっていうことだったら、これだよねっていうのはなりやすいよね、確かに。
- 久田
- 出しやすい。見えてるし(笑)。
- 佐藤
- 手段っていうのもだんだん行政も用意してくれてきてるわけだし、逆プロポみたいなやつとか。
- 久田
- 昔よりは絶対取り組みやすくなってる。向こうの地方自治体とか公共側もオープンになってきてるし。
- 井戸
- 自社だけで解決できるのにはもう限界がきてるってことですよね。
- 佐藤
- でも、これって、さっきスタートアップの話もしたんだけど、ある程度資金持ってないとやれないよね。資金調達の難しさっていうのもあるじゃん。だし、今まで大企業とかがやってたような領域なんだけども、逆プロポがあってとか、こういう、だから中小企業を何とかしようっていう見方もできる。中小企業がずっと同じことをやってきて、オペレーションワークでやってきてたこの50年とかの人たちを、新しい時代に向けて、ある程度お金、資金力もあるし、ビジネスも何十年やってきているから、ある程度ステークホルダーとの関係性もあるし、そういうことに多分チャレンジして踏み込んでもらえたら国もよくなるし、社会もよくなるわけじゃん。だから全く新しい概念だから、新しい人たちがやるっていう感じじゃなくって、2代目3代目とか継いでる人たちでもそうだし、価値観も新しいから。だけど、地場に影響力があってとか、いろんな会社の人たちとかいろんな人が知っててみたいな。で、お金も多少あると。大なり小なり動かせれると。だから、こういうことをできることが多いと思うんだよね。資金調達も資金があるからある程度あとで回収でいいわけだし、ステークホルダーもある程度長い会社ってのはあるし。だから社会的価値の測定、評価の困難さっていうところ、ある程度会社がやってこれば、CSRとしてやれるっていう考え方、CSRの延長で考えることもできるわけでしょ。それよりももうちょっとさらにビジネス化させるっていう、CSRをビジネス化させるって感じなんだよね、昔の言い方ですると。
- 原
- 前はコンセプトだったり、本当に概念だけで話をしてたことが多かったやつが実業としてって話ですね。
- 佐藤
- 昔はボランティアでごみ拾いして終わりみたいな感じだったわけじゃん、堀川を清掃してとか、名古屋にあるんですけど、堀川っていう汚い川が(笑)、昔はきれいだったんだけど。だからそれをビジネス化させるみたいなイメージじゃんね。市場と規則、規制の不確実性、これはすべてが全部そうだからしょうがないんだけど。だから、今、停滞してる中小企業こそグリーンオーシャンにチャレンジしてほしいなっていう感覚はある。
- 久田
- いいきっかけになるし、自分たちの事業についてもう一度社会とどうかかわれるかっていうのを考えるきっかけになりますよね。
- 佐藤
- その中でスタートアップだとか小さい細分化した領域っていうのも、個人のもそうだし、小さい会社、零細っていうか小企業っていうか、スタートアップだとかかかわらせてやっていくと手数も増えていくし、これができる人たちはもっともっとプロジェクトを多分回していく必要があるから、プロジェクトエコノミー的に考えたときにさ。だから全部が全部っていうふうに考えんでよくて、全員が全員がっていうんじゃなくて。多分そうだと思うんだよね。実際やりだしたら本当にYORU MO-DEとかでも、あれはグリーンオーシャンと言っていいかわからんけど。あんなんでも結局、地域経済がなんて、じゃあ何かやるとなったら、工事もしなきゃいかんし、電気もあれしなきゃいけないしとか、広告も出さなきゃいけないしとか、タレントを呼ばなきゃいけないしとか、かかわる業界が多いわけだから、公共的なそういう場所でやるとなっただけで。だから、中小企業が動くきっかけになると面白いのかなっていうふうには感じるね。
- 久田
- YORU MO-DEで言うと、本当に単体でやる必要もないですね。逆に得意なもんを持ち寄って集合体でやるっていうのも一つの実現の方法ですよね。
- 佐藤
- そうそう。集合体でね。課題は課題としてつきものなんですけど、一回アジェンダ見ていきましょうか。
TOPICS
テーマ討論
- 井戸
- 「グリーンオーシャン戦略で開く新たな市場!社会課題をビジネスチャンスに変えるには」。
- 佐藤
- さっきも言ったけど、資金的な部分があるから。いきなりやりますっつって銀行が金を貸してくれるかっつったら多分難しいと思うんだよ、これってさ。だって回収のめどが見えんやつだから、自治体は多分自己キャッシュである程度利益から出してやらないといけない話だよね。だからまずそこはポイントなのかなっていう。
- 原
- あと不確実性っていうわけですけど、要は終わりが見えないので。なんで、どこかで、もしこのビジネス始めましただったら、いつまでである程度めどをつけるようにしようじゃないといけないし、それがある程度資金的に伸びそうだったら、融資ではなく、さっきもあった何社からJVみたいなかたちで取り組むっていうふうにしないと、リスクを分散することが多分1社だけではなかなか難しい部分も出てくるとは思うんだよね。
- 佐藤
- あとグリーンオーシャンって、その考えでいくと、あくまでグリーンオーシャンだからボランティアとかでできる範囲で実証実験して、ボランティアして実証実験をすればいいんじゃない?だから最初から投資しりゃあいいわけよ、投資っていう感覚っていうよりは社会貢献しりゃあいいんだから。セットで考えるからあれなんだけど、
- 毛受
- 入りが社会貢献で入って、そのあとビジネスに、
- 佐藤
- ビジネス化させる。だからビジョンを持って戦略設計できれば一番いいんだけど、だけど何にしてもそこを捉え方として、まずボランティアだよっていうふうにすればステークホルダーも集まりやすいし、ボランティアに参画したい人たちが。ビジネスでって、こういうビジョンで、こういうふうだからっつうんだったら、取りぶんどういうふうにしようとかそういう話になっちゃう、最初から。
- 久田
- 自分の利益の話になっちゃう、みんな。
- 佐藤
- 全部狸の皮算用しなきゃあかんくなってきちゃうから。だから、まずボランティアで始めてって、それでステークホルダーが見えてくるし、大体どれぐらいのユーザーがとか、どれぐらいの経済、それでベンチマークが取れるようになってくるじゃん。だからその数字を見たうえで、じゃあ例えばそこで取引している金融機関だとかでもいいし、こうやって事業計画立てて、こんだけやったらこういう見込みがあるよっていう。だから、ある意味、ビジネスを試し打ちするよりも、CSRでやるから、社会貢献でやるから、めちゃくちゃその時点でリターンあるんだよね。ビジネスは失敗したら、まんじゅう作りたいんでまんじゅう作るわとかいって、まんじゅう作ったら、これ、余った在庫どうしようみたいなさ、なっちゃうけど。だけど被災地にまんじゅうを届けるために、こういうふうにするために目的でやりますみたいな感じでいったら、ちょっとサービスして仕入れ値落としてあげるわとか、最初からその体でいけば、食べてみたら案外おいしいじゃん、この味みたいな感じだったら、じゃあ商品化しようかみたいなんになっていくとか。
- 井戸
- 確かに仲間は集めやすいですね。手伝うよでいけるってことですもんね。
- 佐藤
- そうそう。
- 毛受
- 順番ですね。グリーンオーシャンに入りたいから社会問題は何?って探すのではなく、そこに社会問題があって、まずやってみて、それがグリーンオーシャンになっていった結果みたいな、ビジネスになっていったっていうか、そういう考えですよね。そうすると、私は個人事業主なんですけれども参加しやすい。私、じゃあその部分できますっていうふうに参加して、結果ビジネスとして私の事業にもなっていくっていうかたちだったらすごく参加しやすいですよね、個人の人も。
- 佐藤
- だからセールシートを作るイメージなのね。CSRがセールシートになっていくみたいな。やったことが事例として残っていくみたいな。
- 井戸
- 確かにビジネスって思うと、さっき言ったみたいな売り上げとか利益になりますけど、ボランティアって思うと自分が一番興味持てる社会課題からいけそうですよね。
- 佐藤
- そうそう。そうなってくると、ビジネスも楽しくなってくるわけだ。自分が好きなことをビジネス化させようっていうふうに頑張れるになってくるから。
- 原
- 興味の持ち方のベクトルが違うよね、確かにね。
- 佐藤
- そうそう。だってどのみち事業化させてビジネス立ち上げようと思ったら、結局うまくいかんかったら1円にもならんわけだし、どの時点でキャッシュ化させるかっていう戦略性があるじゃん。だったら、最初の1段階目はCSRでやろうっていうふうにしたほうが、究極論、失敗してこけてもCSRでいいことをしたとかいって(笑)。
- 原
- 世の中のためにはなったんだからね。
- 佐藤
- 世の中のためになったし、得した人がおるわけ。それが一番よくない?
- 原
- そうだよね。
- 毛受
- グリーンオーシャンに今、市場にどういうビジネスがあるのかって私も勉強不足でわからないんですけれども、ここでそういうふうにボランティアから入っていった活動している人たちに対して、例えば資金を援助してくれるところも出てくるかもしれないですし、クラファンとかちょっとやったら思いに共感して、ビジネスって言ったら変ですけれど、資金は集まる可能性は高いかなっていうのはあるので、いかに意味のあることをちゃんとやるかっていうところが大事ですよね。
- 佐藤
- 意味があることをやるのが大事ですね。それはそうだと思うな。でも本当にそれこそ、おやじが最近亡くなって、それこそApple Watchとかつけてれば、確かに今、脈があれですよみたいなやつとか、飛んでくるとか、多分あると思うんだけど、でもちょっと設定が難しいとか、もっと簡単なバンと押したらビュンっていくようなボタンみたいなやつがあったら、もっと助かる人たちもいるんじゃないのかなとか、別に死ぬ死なんじゃなくて、困ったときにバンと押せるとか。バンと押したときだけカメラがどんって起動して、そうしたらプライバシーの保護の観点でもとか、わからんけど。そういう身近に起こった、これ不便だったなとか、こうだったなみたいな。で、訪問医療の人たちが来てたんだけど、その人たちも常にどっかあれだけど、でも緊急の優先順位みたいなやつって、本人たちも情報がなさすぎてつけれないわけじゃん。電話がかかってきて、じゃあそっから行きます、こうです、ああですじゃ遅いんだね、もう。バンっていったら、もうどんってアプリが、ぽんって通知が入って、何々さん宅が今こうなってますみたいな、ぱんって見たら、やばいじゃんみたいな。それが例えば病院とかでもぴゅって行ったりとか、すぐ駆けつけてみたいな、そういう動き方ができるプラットフォームを作れたらいいよねみたいな。それをじゃあボランティアでやってみようかみたいな、近くの家からとか。まあ、わからん。それは逆プロポの発想か。まあまあ、これもグリーンオーシャン。
- 原
- グリーンオーシャンだし、逆プロポではなく、そこは商品提案としての在り方じゃなくって、サービス提案の一環になるっていうふうに考えれば全然問題ないと思う。
- 佐藤
- ボランティアじゃなかったね、これは(笑)。でも、それもボランティアでやっちゃうみたいな。
- 原
- そうそう。だってそこの考え方としてはそうでしょ。
- 佐藤
- いいよね。便利だね。
- 毛受
- 社会課題っていうと大きく考えちゃうけれども、結局は自分の身近な問題が社会課題なので、そこから、うん?って思うことをビジネスってなっちゃうと難しいけれど、ちょっとやってみるって始めやすいかもしれない。
- 久田
- 確かにビジネスになると収益セットで考えないといけないから、いろいろ考えすぎてちょっと難しいかもってなる(笑)。
- 毛受
- 難しいっていうか、めんどくさいとかになっちゃうけれども、ちょっとやってみたいとか、こういうことをやりたいんですっていうのを誰かに話すだけでも協業っていうのはできると思う。
- 佐藤
- それも協業ですよね。確かに。
- 原
- これ、社会課題をって、ビジネスチャンスにという話なんですけど、社会課題っていう捉え方って多分人それぞれ違うんです。何で困ったことがあるかっていう経験値の部分の話だと思っていて、身近な部分をどれだけ事業としてよりも、世の中の役に立てたいかっていう基軸でまず考えたときに、自分が何ができるだろう?っていう考え方で中小企業が考えてもらえると、市場としての活性化は進めやすいんでしょうね、今のお話は。一方でその中で、可能性としての部分のビジネスチャンスは、出てくるかもしれないし、出てこないかもしれないなので、あくまでも、投資っていうよりも試験研究費の発想だと思っているんです、私の中では。なんで、そこはこけてもしゃあないだと思うんです、成果は出てこないやつだから。でも世の中の在り方に対してのインパクトを与えられるっていうところで言うと、投資でもなく、それこそボランティアでもなく、ある意味、事業としての話で言えば、試験研究の一本の一つ。基軸としては融資の話ってもしかしてとおせるんじゃないのかなって、もう少しファイナンスも絡めて言うとね。であれば、もう少し、どんな人、どんな事業体の人でもできる要素は強いかなとは私は思っちゃいますけどね。
- 佐藤
- 入りがそれだったら協力しようとか、そういう人たちが、金銭面だけでも担いますっていう人もいるからね。いいかもしれんね。何かしら、でも、ボランティアの精神は多分必要なのかなとは思うね、最初。サスティナブルにしていこうと思うとやっぱりお金が回らなきゃいけないから、だから収益化させる必要があるし。もっと社会課題を解決するためには利益をちゃんと出して、その会社で働いてくれるスタッフたちだとかも、みんながちゃんと潤ってる状態を作らないと、次へ次へってモチベーションにもつながらないし。だからこそ、会社としては収益性をっていうと、まあ当たり前の話なんだけども、これ。だけどそういう感じが必要だよね。
- 原
- なんで、入口作るのって、中小企業もそうなんだけど、ESGを前提にしてる上場会社もそこら辺の意識持っといてもらいたいところはありますよね。ただ動きにくいは多分あると思うんですよね。だってボランティアで上場会社は動きにくいからね。
- 佐藤
- そういう部署があればいいかもしれんけどね。一回ソリューション出してみましょうか。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- じゃあ本日のソリューション、こちらです。CSRで実証実験を。まあ、これに限るかな、シンプルだし。CSRで最悪いいことしたっていうことだよ。投資がいいことに変わったっていう。
- 久田
- 逆にでも今CSRでやってることもビジネス化できそうだったら、どんどんしていっちゃえばいいじゃんってことですよ。
- 佐藤
- そういう話だよね。そういうことだね、そっちで既にやってんだったらね。過去にやったことでもいいし。ありがとうございます。まあまあ、そういう意味では、今、なかなか事業再構築もいろいろ難しくなってきているけど、過去にCSRでやってることだったら事業じゃないから、収益じゃないものは再構築補助金で補助金でやれる可能性もあるしね。だから、調達を行政から行うっていうこともできるっていう、究極。
- 久田
- めちゃくちゃいい回避方法ですね。
- 一同
- (笑)
- 原
- ただ、事業性としての在り方っていうのを説明できるかなっていうのはね。
- 佐藤
- そこはだから計画っていうか、戦略的なものが必要になってくる。ありがとうございました。
- 井戸
- ありがとうございます。来週以降の放送はこちらのとおりとなっています。次回も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また来週もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
CSV経営で社会貢献が経営の中心に?社会貢献と収益性を同時に追求するには
2024.04.18 放送分
2030年、ビジネスケアラー対応が問うもの!介護と仕事の未来図を作って⼈材戦略を強化するには
2023.12.07 放送分
脳の多様性が競争力を生む?ニューロダイバーシティを推進してビジネスを発展させるには
2023.11.23 放送分
ウェルネスが新時代を切り開く?あらゆるビジネス分野でチャンスを掴むには
2023.10.19 放送分