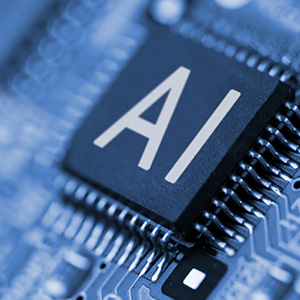2023.12.07 放送分
2030年、ビジネスケアラー対応が問うもの!介護と仕事の未来図を作って⼈材戦略を強化するには
第162回アートリーアカデミア
THEME
2030年、ビジネスケアラー対応が問うもの!介護と仕事の未来図を作って⼈材戦略を強化するには
ビジネスケアラーの重要性と未来のビジネス環境に焦点を当てます。介護需要の増加と労働力への影響を予測、ビジネスケアラーの役割を強調し介護と仕事の両立をサポートする方法について議論します。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、始まりました。アートリーアカデミア。
- 井戸
- 本日のテーマは「2030年、ビジネスケアラー対応が問うもの!介護と仕事の未来図を作って人材戦略を強化するには」。さっそくフリップを見ていきましょう。ビジネスケアラーとは、仕事をしながら家族などの介護に従事する者のことをいいます。高齢化社会を迎える日本で今後増えていくことが見込まれているのですが、問題点が三つありまして、介護保険サービスの限界、企業側の制度整備の遅れ、離職へのつながりやすさといったものが挙げられています。
- 佐藤
- ビジネスケアラーって聞くとなじみない感じに聞こえるんだけど、でも、もう既に家族の方が、認知症だとか高齢化社会が進んでいる中でこれがますます増えていくと。そういった働きにくい状況が続くと、どうしてもやっぱ介護に専念しないといけない人とか、家から近いところで働くとか、リモートワークとかいろいろそういった手段っての今はあると思うんだけど、選択肢として。だけど、企業としてはやっぱり、そこが流出する可能性が高いのかなっていうリスクがかなり高くなってきているところですね。経済損失っていう、チャートっていうかグラフがあるんで一回見てみましょうか。
- 井戸
- はい。2030年の経済損失です。介護負担による生産性低下が、日本全体に与える経済的損失額は、2030年時点で約9兆円と推計されています。
- 佐藤
- というわけなんですけれども、先生、これどうでしょう?
- 原
- 深刻な問題なんですよね。頑張って働こうってする人たちが働けない状況、で、そこで生まれる損失額が9兆円って結構ダメージが大きいし、それに合わせて、先ほどあった国の制度としての在り方でも、手薄さの部分と満たされない部分っていうところがどうしても見えてしまってるからこそ、急務はもう急務だと思うんです。これ2030年っていうふうに年代なってますけど、団塊の世代が2025年問題で退職を迎えるっていうふうになってきて、そこの人たちがどう働くかも踏まえて2030年に備えなきゃいけないから、金額はこの2030年だけじゃなくてもう今の時点でっていう認識はしとかないといけないとは思いますね。
- 佐藤
- これ、この時点で9兆円ってことでしょ?だから、次の年さらにって話になってくる。
- 久田
- そうか。毎年発生していく。
- 佐藤
- 毎年発生してくるんだもんね、この金額は。これ、単純に怖いよね。自分の周りもそうだし、自分事でもあるし。これちょっとどうなっていくんかなっていう、ソリューションがないっていうか。結局、面倒は見ないといけないわけだから、そういった家族の方とかいた場合、介護の対象になる方。だから、変な話、早く薬だとかの、まあニュースとかも頻繁に出るじゃん、認知症の薬がとか。ああいったものが本当に進めば多分いいんだろうけど、でも現時点ではかなり厳しいよね。
- 原
- 厳しい。特に、核家族化が進んでてっていうのもそうだし、晩婚化も進んでいるので、例えば子ども1人で親2人の面倒を見るとか、そういう状況だってあったりするじゃないですか。もうそうすると、仕事なんて行ってられないじゃないですか。だから、そこら辺ってじゃあ国としてどう考えてるって、介護保険のところで何とかできるような感じの話はしてるけど、働くをはぶいて考えることはできないので。
- 佐藤
- でも、これ、少子化ともつながってるかもしれないね。例えば、子どもが生まれるのが早い。で、核家族じゃなくて、例えば昔みたいな3世代みたいな。そしたら孫とかがちょっと面倒を、まあ、面倒を見るっていうか目が届くレベル。
- 久田
- 誰かは家にいるみたいな状態が作れますよね。
- 佐藤
- っていう状況があれば、やっぱり今働き盛りっていうタイミングの人たちは、もうちょっと振り切って仕事ができたりだとか、ってのはあるのかな。何かどうやっても、そこの部分カバーしていく方向にいきがちじゃん。自分の働き方として。
- 原
- そうですね。本来は、だから、介護を受ける方と働く人を当事者にしちゃいけないと思うんですよ。本来、この働く人は働かないといけないに持っていくっていうことが大事だと思うので。それを、例えば企業のほうで見ていくっていうのも、結構しんどいのかなとは思うところではありますしね。
- 佐藤
- だけど、それが結局できないわけだもんね。働かないといけないし、だけど面倒も見ないといけないし。だから、面倒見ない状況ってのが一番いいんだろうけど。でも、やっぱり、そうなかなか言っとれんじゃん。そんな割り切れるもんじゃない、簡単に。
- 久田
- 外部サービスを使うにしても、やっぱりお金がかかる。で、お金がかかる、それどっから捻出するの?じゃあ、働かないといけない。働くために外部サービス。何か、このすごい悪循環が起きてる。
- 井戸
- でも、結構、団塊の世代の人たちって年金もらってません?
- 佐藤
- まあ、でもお金の問題じゃないんだよね、結局は。お金の問題もあるんだけど、要は、昨日までまともだった人がいきなりぼけましたみたいになって、じゃあいきなりぼけたもんで施設入れるかみたいな、そうはならんじゃんね。やっぱり愛情っていうかさ。
- 久田
- 受け入れてくれるところが空いてるかどうかの問題もあるじゃないですか。
- 佐藤
- 極端な話、妹がとかだんながとかいきなり明日ぼけたらさ、あ、施設入れるかってなる?
- 井戸
- なります。
- 佐藤
- あ、そう(笑)。
- 井戸
- なりますっていうか、それはもう多分自分で経験してるからですけど、愛情が持てなくなるんで。中途半端な愛情で面倒見ようとすると。
- 佐藤
- でも、最初の段階のときにさ、じゃあ、お父さんとかやったっけ。
- 井戸
- うん。お父さんも。
- 佐藤
- が、なったときに、もういきなり、よし入れようみたいになったの?
- 井戸
- なりましたね。
- 佐藤
- まあ、人によるんだろうね。
- 井戸
- 人によるというか、やっぱ嫌いになっちゃうんですよ。優しくなれなくなります。こんなに働きたいのに、この人がいるせいで働けないってなってくと、すごく好きだった人のことも疎ましくなってくるのがやっぱり嫌だし、だったら、
- 佐藤
- でも、それそうかもしれない。親子だったらそういうふうになりやすいかも。夫婦だと厳しい。
- 井戸
- 夫婦はね。そう、また違うと思います。
- 佐藤
- 夫婦は違うのよ。親子だったらちょっと違う、印象がまた。
- 井戸
- 夫婦はもっと根深いものがあると思います。
- 佐藤
- 夫婦だったらあるね。親と、確かに違うよね(笑)。だから、そういう状況もあるじゃん。だから、一言じゃ、それで家族がっていうわけで、介護がって、誰の話なのかにもなるもんね。
- 原
- 違ってくるよ。
- 佐藤
- まあ、人口推移があるんでちょっと見てみましょうか。
- 井戸
- はい、年齢階層別ケアラー人数推移です。45歳以降に急激に増加しまして、当該年齢階層のうち17.9%が介護をしている状態になっていくということです。
- 佐藤
- これ、ちょっとわかりにくいんですけど、結局、じゃあ今この40から45の人たちが5年後、水色のグラフになるっていう感じなんだね、上の、層でいくと。だからこの矢印のところ。今、ちょっと緑から緑に向いちゃってるんだけど、緑から水色ってところで見ると、5年後、要は、今、3倍になるってことなんだよね。今の人たちが5年後、40の人が45になったときに介護人口ってのが、ケアラーってのが3倍になるよっていう話なわけなんで、
- 久田
- 親の年齢もともに年取るからってことか。
- 佐藤
- そう。で、10年のスパンで見ると、さらにその下の30から35っていうところが、10年後、40から45のところ、だから二つグラフをジャンプすると、あの緑が濃い青になるところで考えると、これ7倍ぐらいの話になってくるよね。
- 久田
- 一気に増えますね。あの年齢層の17.9%が、介護と仕事を両立することになるってわけでしょ。さっきもありましたけど、その年代って要するに管理職とかそのあたりじゃないですか。でかいよね、穴。
- 佐藤
- いや、穴でかいよ。
- 久田
- めっちゃめちゃ。それが本当に怖いと思う。替えを用意しました、じゃあ人員入れましたで、それで、うん解決だね、1が1と入れ替わってOKだねって話じゃないじゃないですか、そのあたりの人員って、やっぱり。どうやって解決してくんだろうね。
- 佐藤
- だからそこが今回の問題でもあるんだけど(笑)。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- まあ、人それぞれの価値観もあるから、もう割り切って入れますっていう人もいれば、そんなん無理って人もいるし。
- 久田
- そうか、自分で面倒見たい人もいるってこと。
- 佐藤
- そう、面倒見たい人もいるし。
- 原
- あと、介護受ける方の介護度数にもよるよね、どうしても。もう本当に体動けません、移動しか無理ですみたいな方だったら、もう施設っていう話に割り切りは早いと思うんだけど。例えばまだ、まだらぼけで、しかもまだ初期の段階ですみたいな話だと、じゃあすぐに施設がって言っても介護保険料のまかなってくれる金額と合わないから。
- 久田
- 介護認定が受けれればいいですけどっていうところですよね。
- 原
- 受けるまでの段階で、要介助でまだ終わっちゃうと難しいところだしね。
- 佐藤
- それこそ、トイレの面倒見なきゃいけないみたいな状況になったとしたら、本当つきっきりになっちゃうじゃん。そうなるともう本当に。だから、そこまでいったときにだよね。そしたらさすがに割り切るっていうか、そういうふうになっちゃって、じゃあ介護サービス受けますってなると、次、費用の問題になってくよね。難しいよね。家族のことだからね。だけど、そもそも、さっき3世代がって話をしたけど、そういう要因を作ってる部分もあるよね、核家族っていうのが。毎日話してたりだとか、コミュニケーションが盛んにあれば、そもそもそういった要介護の状況を減らしていけれる可能性もあるわけじゃん。
- 原
- 生活の中でってことですよね。
- 佐藤
- そう。要は、もう一人で何もすることないみたいな、そういうふうになっちゃうと、そういうふうになってっちゃう。
- 久田
- 家に孫でもおって、毎日毎日わんわんつき合わされとったら、ぼけとる暇がないもんね(笑)。
- 佐藤
- まあ、難しいっていうか。だけど企業としては、結局、人材の流出だとか働き手不足になりやすい状況になってくから、そこの部分ちょっと考えてかないといけないのかなっていう部分はあるんですけど。じゃあ、次のフリップ見ていきましょうか。
- 井戸
- はい、仕事と介護の両立に伴う影響として8項目挙げられています。
- 佐藤
- 生産性の低下。介護してる人はもちろん生産性低下してるし、周りの人間はそれをサポートする部分なのかな。あとは、企業がそこの部分を補充するコストと負担。あと、働き方の在り方を考えていかないといけないっていう。ある意味、この働き手不足って別に介護だけの問題じゃないから。人口が減ってっているのとか。
- 久田
- もう介護の年代になったら、みんな介護に集中してくれりゃいいよっていうぐらい人間が余ってりゃ、こんな問題にもなってないし。あと、介護業界ってやっぱなりたいっていう人が少ないのもそうだけど、技術的進歩が全然起きてないんですよね。結局、今もいろいろ入ってはいるかもしれないけどIT人材が全然不足してて、そこを、じゃあ人員不足をどう解決しようとか、マネタイズ、別で設けようとかっていうところが進んでないがゆえに、介護サービスっていうのが保険適用内でもあまり受けられないとか精度が低いとかっていう問題になってたり。それを、じゃあ費用入れましょうっていうところの働き手もやっぱり少ない、子どもが少ないから税収も少ないしっていう。ゲームチェンジが全然起きてないんですよね。
- 佐藤
- それは、だから点数の制度でやってるからってことだよね?
- 村上
- 要介護度によって受けれるサービスが違って、国から介護保険が出るよっていうのがもう段階的に明確化されてるがゆえに、それ周辺の部分がカバーできてないっていうところがあって、じゃあその周辺の部分をやるために仕事をちょっと休まなきゃいけないって、そこなんですよね。要介護認定が下りて費用が出れば、もうプロに任せられるんですけどっていう。
- 佐藤
- じゃあ、お金があれば解決すんの?
- 村上
- うん、まあそれで割り切れる、感情論抜きにすればお金があれば解決できる問題ではあると思います。やっぱり家庭内の問題だから、ちょっと愛情がとか、せっかく大切に育ててくれた親に恩返ししたいとか、そういう思いがある方はまた別問題として置いておいて、その費用、外側の周辺部分、介護保険でカバーできない部分の仕組みをちゃんと整備して、サービス提供している事業者さんっていろいろあるんですよ。例えば、お金の管理だったりとか、ちょっとした日常必要なものの買い物に付き添ってあげるとか、そういったところは介護保険ではカバーできてない部分なので、それをちゃんと利用できるような仕組みを、お金を用意しといてあげるっていうところがいいんじゃないかなとは思いますけど。
- 佐藤
- じゃあ、一家に一人、執事がいればいいってことか。
- 井戸
- そうね。そうです。おっしゃるとおり。
- 佐藤
- (笑)
- 村上
- 執事のような動きをしてくれるサービスを雇えるだけの資力があれば。
- 佐藤
- メイドさんがいりゃいいってことでしょ。一緒に暮らしてるメイドさんが。
- 原
- だけど、それが要は普通のサラリーマンのベースで言うと、それが公的に、介護保険料の中でまかなってもらえればいいって話だよね。
- 井戸
- 介護ができる執事がいたら最高ですね。
- 久田
- 国のお金で執事を雇ってくれって結構おこがましいよね。
- 一同
- (笑)
- 久田
- 何言ってんの?って(笑)。
- 佐藤
- でも、それが、技術が発展すればロボットだとかって話だよね。AIが。だからもうそういう話だよね、進んだときの話としては。現時点で言えば、お金があれば、あ、じゃあ執事さんに来てもらえばいいんだみたいな。24時間一緒に暮らしてくれる執事さんみたいな。
- 久田
- 普通にケアしてくれる訪問の人を毎日呼べるとか、そういう話でもいいですし。
- 井戸
- 介護業界、盛り上げられないんですかね。介護施設に入れるのが、何かその愛情がみたいになったりするじゃないですか。むちゃくちゃ楽しい介護施設が、もう入りたいっていうところめっちゃできたら、ちょっと話変わってきません?
- 久田
- 確かに。
- 村上
- ありますよね。すごく高級なケアホームだったりとかね。
- 原
- それこそ高専賃とか。よく言われるのが、一つ一つの部屋がもうマンションの一室になってて、お医者さんが定期的に診てくれて、で、日頃のやつは全部面倒を見てくれるみたいなのって。でも、めちゃめちゃ高いのよ。保証金がめちゃめちゃ高いじゃない。
- 村上
- 億単位で用意しとかないといけない。
- 原
- なかなかそこまで、じゃあ、払える人いんの?っつって。親がお金持ってたってね、っていう話だと思うしね。
- 佐藤
- 億単位でいくんだったら執事雇うな、俺は。
- 村上
- でも、執事がいるのとおんなじぐらいだと思います。同じサービスを、
- 佐藤
- ついでにいろんなこと任せれるわけでしょ?
- 井戸
- 執事にはね(笑)。
- 原
- そうね、介護以外のことも踏まえてね。
- 佐藤
- ちょっと手続きやっといて、とかさ。
- 原
- 代わりにやっといてっていうことが増えるもんね。
- 佐藤
- 秘書みたいな感じだよね、だから。
- 原
- 常駐秘書だよね。
- 佐藤
- それいいな、俺はそれがいいな。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- ちょっと一回戻りましょう(笑)。
- 井戸
- そうですね、一回課題に戻りましょう。「2030年、ビジネスケアラー対応が問うもの!介護と仕事の未来図を作って人材戦略を強化するには」。
- 佐藤
- 執事の話はちょっと飛びすぎてるから置いといて、今、この話の流れで言うと、企業がどんだけサービスを補填できるかだよね?要は。人材強化っていうか採用戦略、人事戦略として。それが福利厚生なのか。
- 原
- あるいは働き方自体を変えていくか。まあ、給料のベースが変わるかもしれないけど。例えば、ワークシェアみたいな発想をもっと強くしていく。現場サイドだけじゃなく、管理職もそういうふうにやっていくのかとかっていうのも一つだと思うけど。でも、会社側がどこまで介護が必要な、従業員の人に対してフォローするかっていう福利厚生の話って、多分その家庭の状況状況によってかなり違うんだろうなと思うところもあるんだよね。
- 佐藤
- だし、それって採用の面接の時点ではちょっと聞きにくいっていうかさ。
- 原
- 聞いちゃいかん話だしね、本来。
- 佐藤
- うん、プライベートの話というか。でも、そこって結構重要じゃん。この話のベースで言うと。そこ聞かんと話にならんし、把握しとらなあかんじゃん。だって企業側としたらリスクを伴ってるわけだから、そこに対して。
- 原
- そう。で、今の法制度で言うと、給料、じゃあそれでそんだけ働かなくなったんだから、働けないから給料カットってわけにもいかないしね。
- 久田
- え?
- 原
- いかんでしょ。だって最初に契約してる金額のところともさ、
- 久田
- でも、契約してる仕事量と明らかに違う量になってますけど。
- 佐藤
- まあ、それは契約チェンジしなあかんね。
- 原
- チェンジにはなる。
- 佐藤
- でも、しなあかんじゃん、それは。
- 原
- で、それは本人が同意しなきゃいけないじゃん。
- 佐藤
- その働き方でね。でも現実的に、本人がこういうふうだからって言や、それは変わるしね。
- 原
- まあ、それはそれであれかもしれないけど。でも、大概が多分、極端な話、月に3分の1から半分ぐらいしか働けませんってなったときに、それだったら多分本人が給与の減額の話とかものむかもしれんけど、
- 佐藤
- でもそれって悪いほうのループに入っていっちゃうから、結局、サービスを使えないとか、今の話で。だからリモートワーク進めたほうがいいと思うんだよね、単純に。結局、要介護っつっとるけど、要は必要になるポイントって、ポイントポイントだったりするじゃん。
- 久田
- そうですね。家を空けれないっていうところ、出張行けないとかもそうですし、あとはやっぱり日中、夜もそうですけど、仕事終わってからもずっと介護に時間を取られてるので、身体的にも精神的にも疲れが残って、仕事に集中できないっていうのも結構問題として大きく挙げられてましたね。
- 佐藤
- そうだよね。リモートワークしたからっつって、じゃあ介護しないわけじゃないから、精神的な負荷は残るわね、確かに。
- 村上
- 何か育児休養とか応用できないかなとかも思うんですけど、大きな違いは、やっぱり育児って何年間も手が離れる時期がきてっていうふうにあるんですけど、
- 佐藤
- 介護ってその人の寿命。
- 村上
- 親の介護ってなるとわかんないですよね。
- 久田
- 終わりが見えないですもんね。
- 村上
- そこが計画立てづらいですよね。どうやってやってく。そこが難しいですよね。
- 佐藤
- 介護と仕事の未来図を作って人材戦略を強化するにはだから、単純にこれがやっぱり個人の視点に行きがち。まあ、でもこれはいいことだと思うんだわ。デザイン思考で考えたときに、やっぱり個人がどうやったら幸せになれるかっていう、働きやすくできるかって会社側が考えるっていう視点に結びつきやすいからさ。リモートワークは一つだし、
- 久田
- 結構手前の問題からすると、どうしても介護で仕事の時間空けないといけないんですとか、集中できなくなりますってなると、その世代って昇進とか、今後の自分のビジネスの先に影響を与えるんじゃないかっていう不安から、自分が介護者であることを伏せる人たちが結構多いらしくて、それで企業自体も把握してないまま人が流出してってるとか、どうも働きが悪くなってってるっていう現状は起きてて、
- 佐藤
- なるほど。理由がわからないまま、違うところに目も行きがちだし、本当のところにたどり着いてねえんだ。
- 久田
- 企業自体がビジネスケアラーを把握できてる割合っていうのが、ものすごく低いですよね、今。で、その調査の中では、企業の7割が今後も別に調査していくつもりはない、把握しない、うちは関与しませんっていうのが出てたりして、そこの何かタブー視されてる部分に関しても結構問題かなと思います。
- 佐藤
- 要は、企業の大きさでスタンス違うと思うんだわ。何万人とかいる会社だったら、単純に市場の動きとしてもマスとして見るじゃん。そりゃ一人ずつ見とれんよねみたいな答えを出す企業も多いと思うんだ。これが例えば中小企業とかになってくると、一人一人、結構パーソナライズした働き方っていうのを許容しないといけないじゃん。そうなったときに、その一人一人がどういう働き方がベストなのかって提供するためには、その人のデータがないと何ともならんやん。だから、まずそこは出していくっていうのは一つだよね。どうにかして、そこは。うちはそういうふうなんで、教えてもらわないと何ともなりませんっていう。その将来的なリスクも含めて。で、それに対して、うちはこういうソリューションを持っていますっていうのをもちろん。だから教えてくださいっていうふうにして、まず透明化させることがファーストステップなのかなとは思うんだよね。セカンドステップは、だから、どういうふうにそのソリューションを出していけれるかだと思うんだけど。あ、じゃあ第一段階のこういうあれだったら、リモートワークで、まずはもう目の届くようにあれしてくださいとか。介護休業だとかも使いながら、ご自身の介護疲れみたいなんを、休んでもらえる日としてこうしてくださいとか。例えば、週に一度はそういう施設だとかデイサービスみたいなやつも使って、ご自身の休暇もちゃんと取ってくださいとか。わからんけど、そういうふうな例えば提案をしていくでもいいし。
- 原
- 要は、企業側の目線で働いてもらうにはっていう話と、どこまでフォローできるかっていう話、まあ、先ほどその線引きの部分が難しいところはあるっていうところだったけども、結局、内情を把握してもできることっていうのの乖離のところを、企業だけで補填できるわけではないと思うんですよね。なんで、介護保険の内容の充実化っていうところが、単身で介護を受ける人と、家族としているけれどもどう面倒を見てもらうかっていうところを変えていかないと、多分、生活感の違いだったり家族構成の違いで、受けられるサービスが違いますって話になっちゃうのはあるのかなとは思うんです。
- 佐藤
- でも、やっぱり家族の在り方っていうのもちょっと見直す必要もあるよね。それって個人の問題だから、なかなかあれはできないんだけど。だけど、極端な話、大家族だったらスケールメリットが生かされて、
- 久田
- (笑)。スケールメリットって呼ぶんだ、大家族のことを。
- 佐藤
- 家族の中でさ、
- 原
- リスク分担だよね。考えるのはね。
- 佐藤
- そう。今日、ちょっとこのプロジェクト走ってるから、俺、面倒見れないんだけどさみたいな。
- 井戸
- 頼むわって。
- 佐藤
- 頼むわとか言って、妹家族が面倒見るとか(笑)。
- 井戸
- そうね、人数がいるとね。
- 佐藤
- そう、人数がいるとさ、そうやって回してけれるじゃん、家族の中でも。で、いよいよそれが何人も増えてきちゃった場合は、それはちょっと施設にしようか、託すかみたいな話になってくると思うんだけど。でも、孤立してってるじゃん。
- 井戸
- 抱え込まないといけなくなってますもんね。
- 佐藤
- 会社と一緒じゃん。だって、3人しかいない会社で1人が倒れましたみたいな感じになったら、2人で支えなあかんくなるじゃん。それが100人いたら、1人、2人倒れても、別にそれは何とでもフォローできるじゃん。だから、そこが段階化してるのが、まず背景としてあるのかなと。
- 久田
- 確かに。共働きも当たり前になっちゃったしね。家にいる人っていう役割の人いないですもんね、もう、今。
- 佐藤
- 共働きならまだしも子どももいないみたいな感じだったら、今度、子どもが例えばおじいちゃん、おばあちゃんの面倒をちょっと見てくれるとか。だから、うまくもしかしたら循環で回る可能性はあるんだよね。上手に運用できれば、家族を。例えば、子どもの育児はおじいちゃん、おばあちゃんたちがやってくれて、みたいな。ある程度年取ってきてぼけだしたときは、子どものほうが今度はおじいちゃん、おばあちゃんたちをちょっと面倒見てみたいな。
- 久田
- 右と左でバランス(笑)。
- 佐藤
- そこで優しさみたいなやつを覚えてって、いい大人になっていくみたいな(笑)、例えばね。いや、これはまあ、人それぞれのパーソナライズの問題だからそうはいかんけど、でも傾向的に何か多いんじゃねえのかなとは思います。
- 原
- もう少し、地域ごとみたいな。昔だと老人会とかあるでしょ?今はもう、そういうのは全然なくて、年を重ねたらそのまま施設に入るが流れになってる状況だけど、もし老人の会みたいな部分の、介護のところの手前でもう少し、
- 佐藤
- じゃあ、それでいいじゃん。会社にそれを作ればいいじゃん。老人介護、
- 井戸
- 託児所と老人(笑)。
- 佐藤
- そう、託児所と老人、だから、一緒に出勤してこやいいのよ。
- 久田
- いいじゃん。
- 佐藤
- うん、俺、何か一瞬よぎったことあるわ、それ。一緒に出勤しやいいんじゃねえの?みたいな。で、人とふれ合うしさ、そのほうが。クオリティオブライフも、QOLも高いし。
- 原
- 何かあったら見れるしっていうね。
- 井戸
- だからやっぱタブー化しないほうがいいですよね、何にしても。
- 佐藤
- そう。何にしてもタブーにするから。今って、こういう過渡期だと思うんだわ。前々前回ぐらいにやったニューロダイバージェントもそうだし、要は助けを求めなきゃいけない、助けを求めてる人たちに対して、何とかしていかなきゃいけないっていう社会になりつつあるんだけど、今、過渡期っていうか変革期だから、タブーになってるものをタブーとして見てる人もいるし。いや、それはちゃんとデータとして扱っていくとか、事象として扱ってって、そういう主観の話じゃなくて。要は課題解決に向かっていくためには、一回全部、蓋を開けなあかんじゃん。何がイシューになってて、何が直すべきことなのかってのが見えん限りはさ。だからそれを開けてくと。で、開けたときにめちゃくちゃいますよっていうことがわかったら、じゃあ隣の倉庫が空いてるから、あそこちょっとリノベーションして、そこで一緒に何かしてもらえるような感じでもいいんじゃない?みたいな。だって、どうせ家いたって、散歩連れてったりとかやらなあかんわけじゃん。
- 井戸
- 一緒に運動もできるしね。
- 佐藤
- そう。一緒にまとまっていたら、今度、ビジネスケアラーじゃなくてリアルケアラーな人、介護士の人を例えば雇ったりしてでもいいわけじゃん。で、何なら、人生100年時代とか言ってるから、その人たちが今度一緒に働いてくれたらいいじゃん。
- 久田
- ちょっと何かここだけ手伝ってもらったりね。
- 佐藤
- ここだけ手伝ってもらえますかとか言って(笑)。
- 井戸
- 労働人口増やした(笑)。いいよね。
- 佐藤
- そう、労働人口も若干増えるみたいな。
- 井戸
- 元気になりそう。
- 佐藤
- もちろん重度とかあれもいろいろあると思うんだよ?だけど、この介護しないの、適用の人たちってのを、この領域をちょっと狭めてけれるじゃん。
- 原
- 自分たちでやらなきゃいけない領域をね。
- 佐藤
- そう。で、そのうち薬だとか技術が発展してって、もっと便利になってきゃいいんじゃないの。ロボットだとか、薬だとか。今、AIがかなり速いから創薬とかも進むの速いじゃん。だから、言ってしまえばこの20年ぐらいの話かもしれないんだよね、この今、話出てるけど。
- 久田
- そうですね。本当、過渡期の問題って感じですね。
- 佐藤
- だけど、今その事実が出てないから保証がないじゃん。絶対そういう薬ができますとかさ、介護ロボットできますみたいな。ないから、そういうふうに話してるけど。でも、もしかしたらそういう施設持ってるところは強いよね、逆に言うと、今。
- 久田
- だって安心して働きに行けますもんね。自分、介護してます、どうしても家離れられないけど仕事やりたいっていう、やっぱ思うし。それでいろいろ話していったときに、あ、うちは全然受け入れ態勢ばっちりですよってとこ、そりゃ入るもんね。で、それが要するに40〜50代でばりばり働いてきた人たちの人員が、それでぽんと獲得できるわけでしょ?超ありがたいもん。
- 原
- 逆に、人材戦略としても、雇用の拡大のほうでどんどん引き込める要素っていうところ考えれるから。
- 久田
- その1は1じゃないのよ。
- 原
- そういうことか。
- 佐藤
- だから結局働いてる人たちが年取ってって、そういう要介護になる可能性もあるわけじゃん、社員が、今度は。大きい会社だとね。そういう人たちを流出するのか、じゃあ、何かそういう受け皿があってやれることがあるみたいになってきたら、またちょっと違うよね。
- 村上
- 介護を受けつつ仕事をする時代みたいになりますよね。
- 佐藤
- そう、それは一番いい循環じゃん。
- 原
- 介護じゃないけど、障がい者施設のA型、B型みたいなことでしょ?
- 佐藤
- そうそう。
- 村上
- そしたら年金問題とかも解決しますよね。
- 原
- 負担だけ重くする必要はなくなるからね。その人たちが労働人口になるわけだからさ。
- 佐藤
- だから、何かわからんけど具体的な施策、できんことないと思うんだわ。今のその障がい者施設の話が近いのかなっていうのもあるし。で、やっぱり会社として、もしそれが人材戦略として強化するっていうふうだったら、そこに対してじゃあ費用出しますよなのか、それともそういうものを作っちゃうか、社員向けの。ってもいいのかなとは思うけど。
- 原
- 中小企業も、連合体でJVみたいな発想で一つそういうのを用意しておくとかね。
- 佐藤
- それこそ、地域の青年会議所だとかJCとか、ああいうのがやってもいいかもしれんよね。よく考えたら。
- 村上
- 家庭内と外のこと、今まで結構日本って分けて、遮断して、それこそさっきの恥だっていう話じゃないけど、そういう時代だったと思うんですけど、今後はオープンにして、家庭内でも人材不足になってきてるから、もうみんなで面倒見て、企業も一体となって、地域も一体となってっていう、オープンにしたほうがいいですよね。
- 佐藤
- そう。だけど本当に進行度合いだとか、そういう介護レベルにもよると思うんだけど、もし軽いものだったらそういうものがあればいいかもしれんよね。特に、不特定多数のっていうところよりも社員同士でつながってるとか、学校のPTAみたいな感じやん、要は。OBみたいな感じで。
- 原
- 限られた範囲内だからね。
- 佐藤
- 家族が利用できるサービスみたいなんを、ちょこっとずつ拡充してってもいいかもしれんよね。それこそ、何か、家族も含めたああいうバーベキューとかさ(笑)。
- 久田
- ああいう感覚ね(笑)。
- 佐藤
- ああいう、ちょっと何か、少しずつ知り合ってってみたいな。
- 村上
- 普段から家族ぐるみのつき合いをする会社にしておくって、スムーズですよね。
- 佐藤
- っていう何かがあれば、そういうのももしかしたら醸成できるかもしれんし。特にちっちゃい会社だったら、そういうところも生かしてくのはいいかもしれんよね。大きくなったときでももちろんそうだし。何でもいいと思うんだわ、何か、ゲートボールだとか、ちょっと動ける人だったらテニスとか、わからんけど。
- 村上
- 子ども会の活動ですよね。それを老人会の、みたいな活動。
- 佐藤
- そうそう。今日はこういうことやるよ、ああいうことやるよとか。
- 原
- レクリエーションがいっぱいあってね。
- 佐藤
- そう。で、そん中でもやれる人はちょっと仕事を手伝ってもらうとか。そこで給与も出すし、みたいな。って感じで回ってくと、すごくいいよね。
- 久田
- いいですね、ポジティブで。
- 佐藤
- ついでに一緒に子どももそこで何かなりゃさ、
- 久田
- 一緒に面倒見て。
- 佐藤
- ちょうど回っていくみたいな感じになるかもしれん。
- 原
- コミュニティが一つできあがるもんね、それぞれの会社の中で。
- 佐藤
- それができるといいよね。少なくとも何人かは減ってくんじゃない?そういう問題は。
- 原
- 離脱する人はなくなるだろうね。
- 久田
- 同じ悩みを持ってる相談相手ができるのもいいですよね。なかなか、介護して仕事してっていってこもっちゃうと、相談できる相手いなくなってっちゃうけど、狭くなっちゃうから。
- 佐藤
- そういう動きってないの?世の中に。子どもの施設を併設しとるとことかあるでしょ?働くお母さんが多いところとかだと。だから、これ、そういう発想でやる人たち出てきそうだよね。あるかもしれんし、もはや。知らんだけで。
- 久田
- 聞いたことないですね。
- 佐藤
- (笑)
- 原
- うん、聞いたことない。
- 井戸
- 聞いたことないけど出てくるかもしれないですね、これから。
- 久田
- あっていいよね。だって、下手したら子どもの預けるより、もっと長い話になるんだから。
- 原
- 民間保育とおんなじだからね、かたちとしては。で、それが社内の中でっていう話になってくるんで。
- 佐藤
- ありなんじゃない?
- 原
- ありだと思うな。
- 佐藤
- そしたら、何か介護事業としても発展していくかもしれんし。
- 久田
- 企業がそれぞれ介護施設を、自分たちで持ち始めて運営し始める話になるじゃないですか。そうなってくると、それぞれの企業文化がまた取り入れられて介護事業自体も発展してくよね。こういうのあったらいいよね、じゃあ作っちゃおうとかさ。それで、
- 佐藤
- だから、さっき言ってたITの遅れだとか、そういったところが発展してくよね。
- 久田
- じゃあ、これいいじゃん、面白い製品作ったからいっぱい売ろっかとか。
- 佐藤
- だから結局そういうことなんよ。企業がもっと、かたちだけじゃなくて、SDGsだとかESGとか、要はローカルとかっていうところに対してもっと積極的に取り組んでいけば、多分、発展してくんだよね。そういうことも含めて変革期なのかなとは思うけど。まあ、でも戦略としては今のアイデアいいよね。
- 原
- そうだね。要素としてあっていいな。
- 佐藤
- ちょっとじゃあ書いてみましょうかね。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- よし、本日のソリューションできました。
- 井戸
- お願いします。
- 佐藤
- 本日のソリューションはこちらです。会社にファミリールームを。
- 井戸
- ファミリールーム、いい名前。
- 原
- ネーミングいいですね。
- 佐藤
- 何か、よく考えたら、介護だけじゃなくて育児でもいいし。で、何かわからんけど奥さんとかだんなさんとか、家族がもう自由に使っていいですよみたいなちょっとした施設っていうかね、作っちゃってもいいかもね。何かめちゃくちゃでかいリビングみたいな。極端な話、だから、スパ施設みたいなん作っときゃいいかもしれん。
- 井戸
- (笑)。漫画とかも読める。
- 原
- そんな感じのイメージだよね。
- 佐藤
- 温泉もあるし、トレーニングジムもあるし。
- 井戸
- めっちゃいいね。ご飯も食べれて(笑)。
- 佐藤
- ご飯も食べれるし、みたいな(笑)。
- 久田
- もう帰らんでいいじゃん。
- 井戸
- 確かに。帰りたくなくなるかもしれんね(笑)。
- 原
- それってよく中小企業で多いのってリゾートトラストとか、ああいうところの会員になったりするじゃない。ああいうのが例えばもっと近いところであったりすると、会社の中でとかってあったりするといいんだろうね。今の話ね。
- 佐藤
- だから、レジャーの前にヘルスケア。ウェルネスのほうだよ。
- 井戸
- いい世の中だ。
- 佐藤
- ウェルネスルームをってことだよ。ファミリーウェルネスを。はい、まとまりました。
- 井戸
- すてき。ありがとうございました。
- 原
- いいと思う。
- 井戸
- いいですね。
- 佐藤
- よきめじゃね?今の(笑)。それはウェルネスだわ、社員の。
- 原
- 心置きなく働けるしね。
- 佐藤
- それはいいかもしれない。やってみよっかな。
- 久田
- いい。文句も出んしね。みんな使えるから。
- 佐藤
- いいかもしれん。それこそ、だから、まかないを作りに来るとかでもいいじゃん。要介護の人がみんなのご飯を作ってくれるとか。
- 井戸
- 確かに、めっちゃいいおふくろの味みたいなの食べれるわけでしょ?
- 久田
- 絶対うまい。
- 佐藤
- 何かあり得そうじゃない?だって、何もかもやれなくなるわけじゃないじゃない、介護されなきゃいけない人たち。
- 村上
- それこそ託児所でお子さんの面倒見てくれるとかね。おばあちゃん、おじいちゃんとか。
- 佐藤
- 子どもに本を読んであげるとかさ。
- 井戸
- うわー、よっぽどいい教育になりそう。子どもたちにとっても。
- 佐藤
- で、必要なものとかは全部会社の経費で、文化処方(?)みたいなやつで、いっぱいあれして。いいかもしれん。
- 原
- 社内で教育もできるわけだから。
- 佐藤
- で、戦時中の体験の人だったら、その戦争の話とかこうだったああだったとか教えるのもあれだし。そうなんだよね。何かユダヤの人たちってそういうのやってるよね?ラビとかっていって。ラビって、そういう伝える人みたいな、リーダーみたいな人がいて。
- 原
- 伝道師じゃないけどね。
- 佐藤
- そうそう。何かやっぱやっとるよね。そういうコミュニティあるもんね?
- 原
- ある。しかも、それ、そのエリアごとにある。
- 佐藤
- エリアごとに。だからユダヤとかだとそうやって世界中に散らばってるから、そういうコミュニティができてるから、そういうのなるんだけど。華僑とか、多分ああいうのもそうじゃん。まあ、そこが介護までやってるかはわからんけど。だからそれが企業単位で考えたときに、企業文化、企業コミュニティとしてそうやってやっていくっていうのはより結束力も強くなるし、本当はいいのかもしれんね、そういうことって。家族同士でそういうふうになって、家族で利用するってなってくりゃさ、それこそどんどん強くなってかん?
- 井戸
- 確かに。
- 原
- 強くなる。会社自体の潜在能力が高くなるから。
- 佐藤
- いいかもしれん。
- 原
- いいかもしれん。ありだ。
- 佐藤
- 何か不祥事起こしたとき、めちゃくちゃ気まずいけどね、社員とかが(笑)。
- 原
- おたくの誰々さん。
- 佐藤
- すぐに家族に筒抜けみたいな(笑)。
- 村上
- だから起きにくくなりそうですよね。家族は家族で感謝してくれるし。お父さん、こんないい会社で働いてくれてるんだ、ありがとうとかいって。
- 佐藤
- だから、一生懸命働かなってモチベーションにもなるかも。
- 村上
- そう、モチベーションになるし、感謝してくれるし。
- 佐藤
- いいかも。
- 村上
- いい、相乗効果(笑)。
- 佐藤
- いろんな視点がまた芽生えてくるね。ぜひご検討くださいっていうところで、ありがとうございました。
- 井戸
- はい、ありがとうございました。次回以降の放送は、こちらのとおりとなっています。来週も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また次回もお楽しみに。
- 佐藤
- はい、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
CSV経営で社会貢献が経営の中心に?社会貢献と収益性を同時に追求するには
2024.04.18 放送分
グリーンオーシャン戦略で開く新たな市場!社会課題をビジネスチャンスに変えるには
2024.04.11 放送分
脳の多様性が競争力を生む?ニューロダイバーシティを推進してビジネスを発展させるには
2023.11.23 放送分
ウェルネスが新時代を切り開く?あらゆるビジネス分野でチャンスを掴むには
2023.10.19 放送分