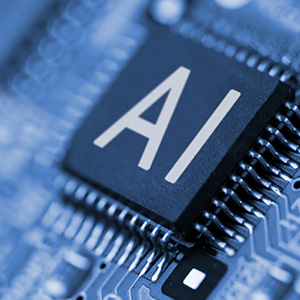2023.11.23 放送分
脳の多様性が競争力を生む?ニューロダイバーシティを推進してビジネスを発展させるには
第160回アートリーアカデミア
THEME
脳の多様性が競争力を生む?ニューロダイバーシティを推進してビジネスを発展させるには
ニューロダイバーシティがビジネスに与える利益に焦点を当てます。創造性、イノベーション、リーダーシップが向上し、競争力が増すことが明らかにされます。多様な視点を尊重し、脳の多様性を促進する方法や戦略が提供され、ビジネス界での成功に寄与する洞察が共有されます。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、本日も始まりました、アートリーアカデミア。
- 井戸
- 本日のテーマは「脳の多様性が競争力を生む?ニューロダイバーシティを推進してビジネスを発展させるには」。さっそくフリップを見ていきましょう。ニューロダイバーシティとは、発達障がいを疾患と見なす医学モデルからの転換で脳の神経の在り方や特徴の違いを多様性と理解し尊重することをいいます。発達障がいはすべての人間の多様な脳特性における差異と見なす社会モデルの考え方で、定型に近づけることを支援の目的とせず、一人一人のニーズに即した支援を基盤とします。
- 佐藤
- 発達障がいの、今回のテーマ、結構今までもやっぱりなかなかメディアとかでも取り扱いにくい話だったんですけど、一方でこういったニューロダイバーシティ人材の活用っていうのは世界的に今、進んでる状況ではあるんです。やっぱ集中力がすごい飛び抜けてるだとか想像力の部分だとか、それこそきっかけは確かIBMかインテルか、いずれにしてもIT企業がデバッグで、ニューロダイバージェントを活用したところ、一般人よりもすごい成果を出してるっていう、それで、もう今チームがあったりだとかしているんで、シリコンバレーの企業とかは。そこはもう活用をもう見いだしてる状況でもあると。だから、どっちかというと経済的な目線で見る、この人材とかをっていうふうに見たときに、この定型に近づけることじゃなくて一人一人のニーズに、もちろんその環境っていうものもちゃんと整えてやらないといけないから、もちろん強いところがある面、やっぱ弱い部分があるっていうところはもう個性として、これは一つの個性と多様性、脳や神経のよう発達の違いってのは、そもそもがスペクトラム、つまり連続体であるって、虹と一緒でグラデーションみたいな、ここでぱちって発達障がいですとか発達障がいじゃないですじゃなくて、グラデーションのようになって、これスペクトラムっていうだけど連続体で。だから、それぞれもちろん重度の方もいるし、中度、軽度いろいろあるとは思うんだけど、そこの問題じゃなくて、要はどんだけ力を発揮できるかっていうところ。で、その力を発揮してもらうための環境というものをもちろん作っていかないといけないっていう、今日はそういったところで話を展開していきたいと思います。で、ポイントとなる点が次のフリップにあります。
- 井戸
- 脳の多様性の八つの原則です。教育研究家トーマス・アームストロングが提唱している脳の多様性の八つの原則から抜粋しています。
- 佐藤
- そもそも、この人間の一番は人間の脳は機械じゃなく生態系に似ているっていうはどういうことかっていうと、生態系って、例えば、ある種の生物が例えば絶滅したとしたら、そこに代わるものが出てくるっていう。要は、脳も結局、例えば事故があって脳の一部が損傷した人とかって、そのぶん、何かが、脳がまたそこを補って、すごい能力にたけるとか、そういうケースとかも今まで医学的にも見られてることいっぱいあるじゃん。そういう意味で、この生態系と似ているっていうことを言いたいらしくて。で、連続体のどっかに位置するっていうのもスペクトラムのさっき話してた話であって。で、この人間能力も、この文化の価値観っていうところで決まると。これも結局日本で暮らしにくい環境だったら、例えば違う海外とかに行ったりだとかすることによって変わることもあるっていう。で、4番、これ障がいと見られるか才能と恵まれるか。これは歴史上のアーティストとか見ても結構あるのかなっていう。それこそ、やっぱゴッホだとか。その時代どういうふうに思われたかっていうのはわからないんだけど、でも、やっぱりこの障がいの部分があったりだとか精神的な部分。だけどやっぱりすばらしい絵っていうのが残っていってるわけで。その才能が飛び秀でてるぶん、ちょっと弱い部分っていうのがあったと。で、この人生で成功する鍵、これ周りの世界のニーズに脳を適用させることっていうのも、結局さっきの環境を変えるっていうことも大切だよと。だけど、それだけじゃなくて周りもそこに対して配慮していくことによって変わっていくっていう。で、このニッチ作り、支援ツールだとか、今、言ってることだよね、だから。人生を豊かにするためにも手立てがそういうの必要だと。で、最後ってのはその努力、そういった部分もすることも必要であって、そうしていくことによって脳っていうのは可搬性があるから、要は変わっていくらしいんだよね。だからポジティブに捉えてたらポジティブに変わっていくし、何か努力してできないことができるようになったら、それができるようになっていくっていうっていうことを、この八つの原則っていうふうにいわれてますと。そもそも、この発達障がいっていう言葉自体が1970年代ぐらいに文献として、そういうのが出るようになってきて、アメリカでも。定義が更新されていって、日本では大体2000年に、そういった言葉を使われるようになってきた。だから昔だったら、例えば、やんちゃな子ぐらいの感じだったやつが、それが2000年代にそういう概念になってきて、要は枠にはめようとしてきている、世の中になってって。だからマジョリティーの人たちに合ってないから違うんだっていう感じだったのは、もう今、いろんな時代背景がある中で人材の問題もそうだし、人材不足の話もそうだし、VUCA時代っていう、何かしら突破するための力が必要だったりだとか、そういったところの背景もあって、もちろんLGBTQの流れもあると思うんだけど、脳の発達もジェンダーの問題と一緒で、やっぱりダイバーシティ、スペクトラムなんだよね。だからそれがどこでどういうふうに判断、周りがどういうふうに判断して自分も判断するのかっていうのは、自分しだいっていう部分あるし、周りの環境しだいのところがあるから、だから個性的なことは間違いない。だから、そんな別に例えば発達障がいじゃなかったとしても仕事がしにくい環境だなとか仕事がしやすい環境だなっていうの、それはあるわけじゃん。だからそういう話なんだよね。スペクトラムである以上、そういうふうに寄ってる人たちもいるし、それはわからないだけの話であって。っていうことで、こういった八つの原則ってのがあるよっていう。で、今、ニューロダイバーシティ人材に取り組むべき理由ってのがある。一回見ていきましょう。
- 井戸
- ニューロダイバーシティに取り組むべき理由です。大きく三つありまして、人材獲得競争への優位性。そして生産性の向上、イノベーションへの貢献、最後に社会的責任といったことが挙げられています。
- 佐藤
- 領域としては未開の領域なんで、今まで。もう始まってんだけど、もう取り合いが。
- 原
- 極端に秀でてる部分があって、そこの部分の逆転の部分で、ちょっと弱い点だったりっていうところの。濃淡の話なんですよね。
- 佐藤
- そういうことなんだよね。だから、とがってんだよね。全体的にフラットな感じの色になってんじゃなくて、もう今、先生が言ったように濃いところと薄いところがあるって話だよね、色で言うと。それを経済的に見たときに活用しますか、どうですかの話だと。簡単なことじゃないと思うんだよ、もちろん。だし、それぞれにやっぱりスペクトラムだから、そこの部分の不自由さのレベルもいろいろさまざまだから。だけど、これは今、社会的にはどんどんこれは活用していこうってなってる。ニューロダイバージェント。だからそういうほかの社員のエンゲージメント向上っていうのもあるけど、多様性によるイノベーションへの貢献。だからイノベーションを起こせるぐらいの才能を持ち得ている可能性が高いっていう話だよね、一般的な人たちより。で、SDGsへの貢献、こういった社会的責任の部分にもなってくるのかなっていう。社会的に見てもあれですもんね、そういった人材が高所得になっていって、で、どんどん経済に税金も払ってってなってくれば、そこの部分の人材っていうのはフロンティアになってくるわけだ。どう思いますか、先生。
- 原
- 確かにそういう意味で言うと、表現悪い言い方するけど、保護としての部分で手当を受けてみえた方が、税を収めることは国としてはプラスになるので、そこは全然ありだと思いますよね。で、そこに対する、じゃあ、ただ、会社が考えることっていうところで言うと、どのように、じゃあこの人に活躍してもらおうか。逆にこの人をじゃあサポートする人も必要になってくる、組織としての在り方だったり。じゃあ、それもどうやってやるっていうところが、各社それがこの方に対するパーソナライズの在り方ですよね。に合わせたかたちで逆に組織を作っていくっていうような体制になっていく。これがもう体制の変化っていうところなんだろうなとは思っているんですけど、それに対する、じゃあ会社それぞれの個々がみんなケースバイケースなので、会社個々のやり方がみんな違ってくるんだろうなっていうふうには思いますね。
- 佐藤
- それはそうだと思うよ。だから人材に合わせて変わってくるから。人的資本みたいな感じだよね、考え方は。だけど、今はまだいいかもしれないけど、これ、どんどんシンギュラリティに向かっていったときに、じゃあそれこそAIと、もうタメ線張って戦えれるぐらいの可能性が、もしかしたらある可能性があるでしょうね、その才能の部分で。それって、じゃあそこが中心になって、もしかしたら、ある組織はそれで、多分そういう会社も多分あると思う、もう既に。今は何となく平凡な会社っていうのが、言い方あれだけど平均的な会社で、もうそんなに個性なくてもやれてるところは、もうロボットだとかAIだとかに変わっていきますってなったときに、いったいどんな価値を提供できるんですかってなったときに、やっぱり飛び抜けた何かってのはこれから会社として求められるんだよね。それが何かによるニューロダイバーシティがどうかじゃなくて、当たり前の平凡的なものってのはもういいよねと。多分何か大手とかに、しゅって買収されてって何か統合されていくか、その売り上げが確保できずに溶けていくか。だからそういった意味でこういった、まあ、一つの在り方として、今、動きがあるよって話なんだよね。じゃあ最後のもう一枚、フリップを見ていきましょうか。
- 井戸
- ニューロダイバーシティ人材の特性です。主に自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、学習障がいといった三つが挙げられています。
- 佐藤
- これ主な発達障がいの方たちの特性、これプラスのところ全部書いてるんですけど、ちょっと読んでいくと大変だからあれなんだけど、言ってくと、ASDの方たちってのは基本的にすごくロジカルなんだって。めちゃくちゃロジカルで、集中力も高くて、もう一般的な人よりももうすごく論理的に考えれる。で、注意欠如多動症の方たちっていうのはどんどん新しいことに、もう興味がどんどん向いていくから、リスク取らずにどんどん新しいことにチャレンジできちゃうのね。で、プレッシャーだとか、もうむちゃくちゃかかるような場面でも、もうめちゃくちゃ冷静でいられたりだとか。あと、学習障がいで書いてある。これ書いたりとか読み書きとか、あと算数だとか、どっちかいうと、そういったところなんですけど、こういった方たちは逆に、そういった部分が弱い代わりに、どっちかいうと、このビジュアル的なイメージのほうがむちゃくちゃ優れてたりする。それこそ今でも読み書きできない人たちっていうのが、世界中で何か8億人ぐらいおるんだよね、確か。
- 原
- そんなにいっぱいいるの?
- 佐藤
- そもそも教育受けてない。教育が受けれない貧しい方とか。っていうのもあるし、歴史的に見ても、読み書きが苦手だったりとかっていう人たちは、逆に絵とかがすごい優れてるアーティストっていうのも、今まで確かいたはずなんだよね。だからそういったところ。で、こういった特性があるよっていう話だなってところです。どうですか、渡辺さん。
- 渡邉
- 僕はよく、ずっと一緒にいる後輩とか女の子には多動症だねって言われます。
- 一同
- (笑)
- 渡邉
- だし、ちっちゃいときから親からも、仁は落ち着きがないと、ケツに虫がついてると言われてきたんですけど、そういう習性なんですけど、だからこそ新しいものに、発見して、どっか何か1人で行ったりとか、衝動的に行ったり。で、そうすると新しいアイデアが浮かんで制作につながったりとか、全部プラスになってるんですよね。デザイナーという仕事、特に自分で独立したブランドを作るようになってから。なので、生かし方かなと思いますね。
- 佐藤
- 本当そうだと思う。だからさっきの八つの原則でいうところの、自分で環境を変えるとか、例えば、もちろん重度、軽度とあると思うんだけど、もう普通に一般的な人でも、ちょっと数学が苦手だなとか、絵が苦手だとか、コミュニケーションが苦手だとか、いっぱいあるじゃん、そんなの。それはスペクトラムだからなんだよね、結局。それは脳の多様性の話で個性の話だから。だから渡邉さんも、だから本当かどうかわからんけど、それ調べたらどうなのかとかあると思うけど、でも、そういったところの傾向を言われてるってことは、そういう傾向があるっていうことだね。だからやっぱりそこの部分、今、書いてあること、やっぱりはまるもんね、結構。
- 渡邉
- 全部はまりますね。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- 注意欠如(笑)。
- 渡邉
- 注意欠如、人の話聞いてないし、テレビ見ててもザッピングばっかするし、うんこしながら歯磨きながら音楽聞くみたいな。
- 一同
- (笑)
- 渡邉
- 何か一気にやってないと、もったいないって思っちゃうんですよね。
- 佐藤
- でも、これって、アーティストとしてのバックグラウンドがあると、なぜか人って、それを発達障がいっていう言い方じゃなくて、何か変わってるけど、アーティストらしいよね、みたいな感じの印象があるわけ。
- 久田
- アーティストな感じになるね。
- 渡邉
- 織田信長もどっかに当てはまると思うんですよね。
- 佐藤
- でも、大概、俺、思うんだけど、この医学的な目線じゃなくて、誰かを攻撃して言うわけじゃないんだけど、大体非凡なことするやつは多分何かしらの発達障がいっていうか、そのニューロダイバージェントだと思うんだよ。
- 久田
- 結局、ステータスをどこに振ってきたかって話ですもんね。
- 佐藤
- そういうことなんだ、結局は。
- 渡邉
- 金玉ってあるじゃないですか。
- 一同
- (笑)
- 渡邉
- 2個あるじゃないですか。1個欠けたやつがいて、で、1個欠けると、何か失った感あるじゃないですか。半分しか生産能力ないんじゃないか。でも、お医者さんが言うには、金玉はいつも1、1作ってるんだけど、1個なくなると、片方が3作るらしい。能力が上回っちゃう。
- 佐藤
- だから脳の話してたんだけど、結局人体って生態系と一緒なんよ。補うから体が。で、それだけまだ、しかも脳って領域ってなると、さらにまだ全然わかってないことが多すぎるから。
- 渡邉
- 何%しか使ってないんですよね。
- 佐藤
- そうそう。20%ぐらいしか使ってないっていうこともいわれてる中で、いや、80%ぐらい使ってるとか、そんだけ意見が違うわけだ。だからこれは今、発達障がい、確かにいってて、確かに今のこのカルチャーの中では、何か生きにくさとか、もしかしたらある方もいると思うんだけど、だからそれも結局それって文化的にそれを作り上げちゃってる話であって、だからこれって今から変わっていこうって時代だから、なかなかこういうことってあんま取り上げにくいんだけど、だけどこれから変わっていく時代の中では、これって、そういう見方になってこなくなってくるんだよ。
- 村上
- 当たり前のことですもんね。これが別に何か取り立てて障がいっていうふうにつけなくても、みんながその多様性を受け入れるっていうところですもんね。
- 佐藤
- そう。だから、例えば働くってなったときに組織の中でどうやってみんながそこに対する理解を持てるかどうかっていうところが、まずニューロダイバーシティの課題になってくるわけだ。
- 原
- 既成の概念を取っ払って、新たな時代に入るのに、じゃあ会社としてどう向き合うんですかっていうところだよね。
- 佐藤
- そうそう。だからそれって、やっぱ自分とは違う傾向の人が多いから、例えばチックな人たちだと何か同じことを繰り返したりだとか、もうぎゃあぎゃあうるさいとか、人によってはそういうふうに見る人たちもいるわけじゃん。だからもちろんそれで誰かの集中力だとかそういうものを阻害しとったら、それはうまく成り立たんじゃん。だから会社としてはそういう環境もちゃんと作っていきながら、どう生かしていくかっていうのを考えていかないといけない。そういう意味で経済的にどう競争力を高めていけるかっていうのが本日のアジェンダになってきます。
- 井戸
- 「脳の多様性が競争力を生む?ニューロダイバーシティを推進してビジネスを発展させるには?」。
- 佐藤
- というわけで、まあ簡単じゃないと思うよ。
- 原
- めちゃめちゃ大変だよ。
- 佐藤
- だけど、それを逆に言うと、あんまりそういう環境がないから、周り。そのニューダイバージェントの方たちってあんまりいないから、逆に言うと、フラットに考えれるんだけど、そんなにもちろん、何度も言うけど、そのやっぱこのダイバーシティも推進するうえで、できる人とできない人っていうのがいるっていうのは経産省も書いてるんだけど、さすがにやっぱ働くのは困難な人もいる。だけど今、でも、リモートワークができるとか、だから環境だとか選択肢が増えてきてるわけよ。自分の得意なとこだけを伸ばしていけれるっていうこともあるし。
- 久田
- 結局会社に来るってなると、今までそれこそ、その体のほうに障がいがある人だと、じゃあトイレの整備をしないといけないとか企業側も構えなきゃいけない、いろいろ準備しなきゃいけないところがあったけど、リモートができるってなると、会社側も設備的にそこまでお金をかけなくても迎えることができるようになってるってことですよね。
- 佐藤
- そう。だし、実はアートリーも昔、リモートでお願いしてたのが、俺の先輩なんだけど、3年ぐらいライターでお願いしてたのよ、リモートで。知ってると思うけど、誰かとは言わんけど。だからもうそれも知ってたうえで、出社はやっぱそういうのがあるから家でやりたいってことで、リモートでSkypeつないでとか、そういうやってたんだよ。それは特別に何かすごく何か能力がっていうのは、そのときは何か別に見いだしたりとか、そういう話じゃなかったんだけど。そういう人とはもう自然と何か友達だったから、で、そういうのを書けるからお願いしてたわけよ。だから別に全然そういうのとか、俺、気にしないっていうか、もちろんそういう気になるレベルだったら、やっぱそれでも活用しなきゃいけないってなったら、もうそういう環境を整えなきゃいけないし、うちじゃないよねっていうふうに選択になるかもしれないけど。だけど本当にう多様化してるから、働き方が。だからこそ、こういう人材も取り入れて実現できるよねっていうことをうたってるわけなんだよね。だけど、やっぱ管理していくっていうのは難しい。体調も崩したり何かっていうのは起きやすいから。
- 原
- そうだよね。だから私、それこそ今回のこのアジェンダのところをいろいろ調べてたときに、例えば大手のそれぞれの会社さんがやっぱりそういう部署を作っていってるんですよ。例えば、TOPPANさんだったりとか、いろんな大手のところで、そういう取り組みをしていて、やっぱり一筋縄ではいかなかった経緯って、いっぱいお話が出てたんで、今現状としては何とかそこを進めていくっていう部分は、それでも変わらないって、会社としては変わらないっていうのはあるよね。なので、そういう意味で言うと、どう受け入れるかっていうところの在り方で、話を聞いてて、それぞれの状況が全然違ったので、何社かのやつ見たんだけど。
- 佐藤
- だから1人ずつでやっていく必要があるっていう話ですよ。
- 原
- やっていくしかないっていう話。なんで、例えば無造作に、じゃあこの人っていうふうでやるわけじゃなくて、やはり就労支援の相談員と合わせながらやっていったりとかっていうふうで、
- 佐藤
- それはすごく何か、あれだよね。
- 原
- だから、いや、それを大手がやってたの。実際にやってた。だからそういうのも踏まえて、きちんとした、それこそやっぱり雇う以上は管理と運用の仕方っていう、これ合わせ手だと思うんですよ。で、会社として求める人材はどういう人かっていうことと、その方がどこまでできる方か、どんな能力のある方なのかっていうところで言うと、例えば就労支援の相談員であったり、部署内でもそこの相談係をやっぱり作るっていうのをやっていく。それはこのニューロダイバーシティの対象となる方ではなく、それ以外の方々に対してのモチベーションが下がらないように、体制としての在り方をなるべく均一化するために、そういうふうに配置していくっていうようなので、一方でこれを中小企業で同じようにやっていこうと思うと、すごく大変なことなんだよね。
- 佐藤
- でも、A型の移行支援の方たちって比較的そういうのって受け入れられやすい人材が来やすいじゃん。しかも、そこでプロファイルのカードもできあがってるんだったら、それはすごくいいよね。
- 原
- そう。なんで、その各企業との相性だったり、求めてる部分の部署だったりとかの部分の話もきちんとできるので、A型は確かにそうだと思うんだよね。
- 佐藤
- もう一つ、俺、思うのは会社の中で、これってゼネラリストの仕事ばっかりはできないのよ。専門特化型だから、これ完全なる。専門特化型で業務が確立されてないと。それはもう基本的に混乱が生まれると。
- 原
- そうだよね。なんで、やっぱり会社っていうのはゼネラリストだけでは成り立たない。これ確かにそう。だけど、スペシャリストだけでは成り立たないのも同じ話なので、どうやってそこの部分の均一化、これ法律としてのところの話にもなっちゃうのかもしれないんですけど、働き方っていうところの国が定めてる働き方の前提条件っていうのも、多分変えていかないと、このニューロダイバーシティに対してリンクしてこないんじゃないのって。
- 佐藤
- っていうのは?
- 原
- 例えば考え方としては、じゃあ就労時間としての在り方だったりとか、で、もちろん人の流動性と言いながら、表現悪い言い方ですよ、どんだけじゃあ就労支援の相談員と話が合わせたとしても、ごめんなさい、その部分で言うと合わない場合の解雇する自由っていうのも、これはあっちゃいけないことだとは思うけれども、相性だったりもあったりするから、それをじゃあ解雇じゃなくて流動性っていう話でどうするっていう話だって、できないといけないんじゃないのかなって思う。
- 佐藤
- だから最初から試用期間でそれトライしてみればいいじゃん。だって、俺、思うけど、これは人的資本経営のときも話したけど、勤めれたから、じゃあその人も安泰じゃないし、会社としても、じゃあニューロダイバージェントだから、逆に特別扱いしなきゃいけないのかっつったら、多分それは違うと思う。サポートする体制っていうのは、その人があくまで才能を発揮してもらいやすいために作っていくものだから、ストレスをなくしていったほうが、あくまで競争力を高めるための取り組みなんですよ。だって、せっかく能力ある人が、ニューロダイバージェントが来たときに、発揮できんかったら何の意味もねえじゃん。働きにくさだけが残っちゃうから。だからそこは考えていかないといけないんだけど、だし、お互いにとって会社も違うなと思ってたら、本人にとっても違うんだと、その場所じゃないんだと。飼い殺すことを一番やっちゃいけなくて。だからそこは試用期間でまずはまるかどうか、ここはもう一般的な普通に、一般的っつっとるけど、結局スペクトラムだから自分たちが一般的って、そんな障がい者の認定か何かがない人も、実はだけどそっちを寄っとったりするかもしれんし、わからんやん、そんなの、はっきり言って。だから、もうそうやって考えていったときに合うか、合わんかは普通に試用期間を作って、やれるか、やれないかっていうふうに見てって、解雇じゃなくて、また違うところにっていう。それはだって紹介してくれるエージェントの、そこの営業の仕方の在り方で違うんじゃねって話だから。
- 原
- 違うっていう話になるんだよ。そうなんだよ。
- 佐藤
- だから当たり前に当たり前の人材だと思えばいいと思うんだけど、俺は。
- 原
- 障がいの有無ではなくてね。
- 佐藤
- そう。じゃあ、これ根本的な話だよ。極端な話言うと、そういう障がいがあろうがなかろうがニューロダイバージェントだろうがなかろうが、能力がある人はストレスを抱えて仕事しとったら、会社にとって損やん。それで辞めていったりとかしたら逆に損失でかくない?
- 原
- でかいよね。
- 佐藤
- でも、これって、もう誰だろうが関係なくない?だから、まずそこに目が先に行っちゃうのはあれなんだよね。だからどっちかいうと脳の多様性の話が先だから、どうやって、その脳の多様性を、逆に言うと俺がもっと何か課題にしなきゃいけないのは、どうやって発掘できるかのほうが問題だと思うわけ。
- 原
- 発掘の仕方だね。
- 佐藤
- そういうこと。
- 村上
- 発掘っていうと、その当の本人さんも、自分はこれを特性として生かせるっていう、早くに気づいてる人があって、でも、それ今の教育の仕組みだったりする義務教育がどうしてもメインで型にはまって、みんな同じように育ってっていうと、結構コンプレックスを抱えてて、マイナスだと思って押し殺してて、それ殺してるまま生きてるみたいな方が多いと思うんですよ。そうじゃなくて、それ解放したほうがより伸びるんだよっていうの、早い年齢のうちに気づかせるような仕組みがあると、そういう方が自分ここを生かせる強みですって堂々と言って、それを欲しい企業がピックできるっていうかたちになると思うんですよね。だからもう教育の仕組みから実は変えていかなきゃいけないとこ。今、実際それが動いてるのかもしれないですけど、そこからだと思います。
- 佐藤
- 本当にそう思うね。だって本当に、要は子どもの頃にその特性に対してほめられてたか、おとなしくしなさいって言われてたのかで、もう全然、この人の育ち方が変わっちゃうわけよ。文化への適用的な部分、社会的な。だけど、まだ出会ってないけど、うちの会社にとってむちゃくちゃプラスになる可能性がある人がいるんだったら出会いたいやん。特別にその人だけの部屋作ったとしてもさ。じゃない?
- 原
- そうだね。
- 佐藤
- それが、だからどっちかというと、どういうふうにしていくかってよりも、弱い部分を何とかしていく前に、強い部分をどうやって引き出せれるのかっていう、どうやってそれをプロファイリングできるのかっていう、ここのジャッジが一番重要なんだ。それがA型の移行支援が、もしそこまでやってるんだったらすばらしいし、だけど、そういうコンセプトのところも何かちょろちょろ出てきてるじゃん。
- 原
- だから人材紹介の延長線上なんだよね、普通にあるのが。
- 佐藤
- そう。だからもう、どっちかいうと才能を開花させるみたいな。あれと一緒だよ。アメリカで何か天才ばっか集めて何かやってる学校とかあるでしょ。IQが高いやつだとか、何か特別なあれ。あれって、もう逆に言うと俺、何かそんなん、そっちのほうをたまたまフォーカスしてもらっただけだけど、ネガティブな部分もフォーカスされとったら、全然また違う歩みだろうね。こっちが発掘されとったら天才の部類になるわけじゃん。だってすごい人とかおるもんね。テレビで何か障がいはある方なんだけど、ヘリコプターで、ばーって上空で見た景色を降りてきて、そのまま全く同じ絵描く人とか。
- 原
- みえますよね。だから才能、
- 佐藤
- だからフォーカス当て方なんです。残念ながら100いいほうに、何か100記憶力に振ってたら、何かしら、「50・50」であらなきゃいけないのに、90こっちに振ってたら、どっか10、こんなシンプルな話じゃないと思うんだけど、当然。だから、そこがもしかしたら何かそういう、それが独自性なのか、そういう機関とかそういうエージェントとかがそれ積極的に取り組むのか、ことができれば、ビジネスの発展につなげていけれるし、企業競争を有利に持ってくこともできるんじゃないのかなとは思うわけ。当然TOPPANの例って、どっちかいうと大企業だから、50人以上のあれもあるから、どうやってそれを集めて活躍させるかの部分のスタートでいっとるじゃん。法律の先行で、この人たちもちゃんと社会貢献的に、あなたたちやらなきゃいけないです、大企業だからみたいなところからスタートしとるわけでしょ。じゃないもんね。今、IBMとかマイクロソフトがやっとるの。もうあえてそこって、もう引き抜きにいってデバッグチーム作ったりだとかして、もうひたすらいろんなユーザーテストとかを永久にやり続けれるわけ、ノーストレスで何時間も。
- 原
- それは企業にとってはいいよね、ありがたいですもんね。
- 佐藤
- だってそんなこと、普通のまともな人間がやってたら、もう精神おかしくなるんだって。もう俺らだって、もうこの会社が立ち上がってやってく中で、もうコーディングだとか、ああいうのを永久にやるとすごいストレスで何回発狂しとったか。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- でも、それが好きでやれる方たちもいるんだよ。
- 久田
- それはもう完全に一つの才能ですからね。
- 佐藤
- そう。もうあれ才能じゃん。あれをずっとやり続けれるんだって。
- 久田
- あれをやり続けるのは本当に才能。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- だからこういうところがある。特にITのところの領域が多分出やすいと思う。知的労働のところでやっぱりすごく活躍ができる。やはり知的労働があんまりメインじゃなかったじゃん。ビフォーITって。だからどっちかっていうと、割とゼネラリストとして動く必要があったじゃん。だからそういうところなのかなみたいな。事業体のDXともここは兼ね合ってくるし、前回やったアートと経済っていうところでも、アートのほうで才能できる発揮するかもしれないし、ジミー大西さんとかみたいに。お笑いやってて、ばかにされてたけど、絵描かしたら何かすごい絵描くなみたいな(笑)、世界的なアーティストになっちゃったりとかした方もいるわけじゃん。
- 原
- 会社としても、どこまで人を輝かせられるか、それが自分の会社とマッチしてるかっていうのを真剣に取り組まなきゃいけないようなかたちになってるんだよね。
- 佐藤
- そう。だし、これは取り組まなきゃいけないっていうか、企業競争を有利にしていくなら今からやるべきだっていうね。だって、これからは社会が変わってったときに学校がそういうのを発掘っていうか、そういうふうに見なくなってくると、自然とそういう人材は出てくるから。
- 原
- そうなるわね。で、結果として、早いもん勝ちの話になる。
- 佐藤
- そうだ。だから結局じゃあ採用の話になったときにどんだけ枠を広げて、言い方悪いんだけど、いろんな人材が紛れてきてもいいように、外国人から、ニューロダイバージェントもそうだし、もう日本人でも何もどんな人でもいい。受け取って、一人一人正しくプロファイリングしていく。で、自社の業務にどうやっていくかみたいな、だからもちろん、いろいろ採用戦略あると思うからあれなんだけど、そういったところはやっぱ考えていくと、何かかすごく発展できる可能性があるんじゃないかなと。っていうね、ちょっと熱くなっちゃったけど。
- 原
- なる内容だよ。
- 佐藤
- 何か俺、もともと肯定派なんだよね。ちっちゃい頃から歴史上のアーティスト好きだけど、いろんなそういう何か、だからもともと個性みたいなさ。だからゴッホのエピソードで耳切って送ったとか、あんなんも何か面白い人だなっていう感覚だもん。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- 送られてきたらびっくりかもしれない。最後、拳銃で自殺しちゃうんだけど。だけど、そういう方の感性だから、ああいう『ひまわり』だとか、あんな絵を描けるわけでしょ。じゃあ一回ソリューションいってみましょうか(笑)。
- 一同
- (笑)
- 井戸
- はい、お願いします。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- じゃあ本日のソリューションはこちらです。ニューロダイバージェントの、だからこそを考えよう。
- 原
- だからこそね。
- 佐藤
- 3回ぐらい前のDXの回でやったと思うんですけど、あの経営フレームワークのところね。だからこそ、もちろんできることを知って、で、だからこそを考えると。だから因果的にはできることっていうのを知ることから始まるんだけど、だからニューロダイバーシティ人材に対する、特性の理解をすること。この弱いところ、強いところ、両方含めて知るところ。で、自分のビジネス経営プラン、事業戦略的に必要なところを考えて、いや、これニューロダイバージェントだからこそできることか、じゃあこうだよなみたいな。で、今、言ってたみたいに普通の人だったらもうストレスでちょっと続けられないことが、集中力が高いからこそ、永久に、永久にってあれだけど、やり続けられると。それだからこその話。そういうふうに考えていくと、結構ポジティブに取り組んでいけれることなんじゃないかなって。
- 原
- 積極的にね。
- 佐藤
- はい。だと思いました。
- 井戸
- はい、ありがとうございます。
- 佐藤
- どうでしょう?渡邉さん。
- 渡邉
- ん?
- 佐藤
- ADHDだとかいって後輩に言われてる(笑)。
- 渡邉
- そうですね。でも、ナッちゃんがさっき言ったように、その周りの環境とか伸ばしてくれる人の影響がっていうのを言ってましたけど、僕は5歳の甥っ子がものすごい絵がすごい好きで、うまくて東京だのの美術館に飾ったりされてますけど、周りの友達といるときは、僕はいつも絵を下手に描いてるって言ってました。わざと。
- 佐藤
- 何で?
- 渡邉
- いじられるから。うますぎて。だから、こういうこともこうやって考えてやってるんだ。でも、これ、めちゃめちゃいい絵だねって言ってくれてる人たちの周りだと、能力を最大限発揮って描くんですよね。だから生かすも殺すもやっぱり周りの人たちの引き立てというか、
- 佐藤
- 必要だよね。何歳だったっけ。
- 渡邉
- 5歳ですね。で、僕はアーティストだって言ってますね。5歳では、自分、あんまりアーティストの意味を理解してないまま言わないのを名乗るとか、
- 佐藤
- いや、理解しとんだと思うよ。
- 渡邉
- っていう、画家だとか絵が好きだとかじゃなくて、アーティストだっていうので、あら、これはその芽を紡ぐ役割を今度自分たちがしていかなきゃいけないのかなっていうふうに思うようになりましたね。
- 佐藤
- 大体、俺、発達障しょうがいのそこ調べてたときに、2歳から3歳ぐらいでまず一発目の、何かそれを見るらしいね。だからそのときって、俺、思うんだけど、2歳、3歳で、人によっても、生まれてきて2年とか3年の間で、みんな一律に成長するわけじゃないじゃん、モヤシみたいにさ(笑)。違うじゃん。環境も違うし、DNAも違うんだから、順番があると思うんだよ。ましてや優れたものを伸ばそうと思ったら、そんだけ時間もかけて、人が何か普通違うことをやってるところを伸ばしてるって考えたときに、これ脳の話してんだよ?その人の話じゃなくて。脳の発達の話で、普通そうじゃね?と思うの。だって大人になってデザインを5年かけてやってた人と、デザインは2年、じゃあ音楽は1年とか、何々は何とかとか、そうやってやってる人より、デザイン5年やってた人のほうが、それ濃度たけえよ。だけど、5年デザインやってて優れとる代わり、音楽とか0年だから、1年のやつにも負けるわけじゃん。で、それで何か発達が遅れてるとか言われたってさ。そうじゃない?
- 原
- そうだね。
- 佐藤
- だから多様的なんだよ、成長の仕方も多様的だから。だから面白いわけで、だから世の中、可能性が増えていくって話だと思うのね。きれいにまとめとるけどね。
- 渡邉
- とんねるずさんも、ずっとタモリさんのことだけ尊敬してるんですよね。高校生のときにとんねるずの2人が、何かお笑いコンテストに出たときに、何やってるかわかんないけど、おまえら面白いって言ってくれたのがタモリさんだけで、審査員の中で。ほかは何か落語家の桂何とかとか、何や何とかがいて、わけわからん、おまえらのやってるのはお笑いじゃないとか、ぼろくそ言われたんだけど、タモリさんだけが何か認めてくれたっていうことで、それだけ信じてやってきたっていう、何かプッシュアップっていうか、何かがあったんですね。
- 佐藤
- だから結局環境のことなんですよね。
- 渡邉
- 環境プラス自分を信じ続けて、自分でやっていくことが結構大事ですよね。
- 佐藤
- うちのおかんも、よく小さい頃、何かしたときに、ばかとかいって言っとると、お父さんがめちゃくちゃ怒ってたもん。ばかって言うな。いいところをどんどんほめて、そういうできないとか、そういうことをそういうふうに言わない。
- 村上
- すてきですね。自己肯定、それで高まりますね。
- 佐藤
- そうそう。だから自己肯定の塊みたいなやつ出てきたんだけど。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- だから、教育とか環境によって、やっぱあるっていうことなんよ。
- 原
- それは大きいよね。
- 村上
- 大切。
- 佐藤
- だからもしかしたら、俺、子どもいないからあれだけど、子どもに対して、当たり前の子どもじゃなくて特別なんだって思ってしていくのもいいのかもしれない。だから何か違ったことがあったとしても、それはよくも悪くも個性なんだ。そういうふうな時代になっていくといいのかなっていうふうには思う。
- 井戸
- ありがとうございます。来週以降の放送はこちらのとおりとなっています。次回も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また来週もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
CSV経営で社会貢献が経営の中心に?社会貢献と収益性を同時に追求するには
2024.04.18 放送分
グリーンオーシャン戦略で開く新たな市場!社会課題をビジネスチャンスに変えるには
2024.04.11 放送分
2030年、ビジネスケアラー対応が問うもの!介護と仕事の未来図を作って⼈材戦略を強化するには
2023.12.07 放送分
ウェルネスが新時代を切り開く?あらゆるビジネス分野でチャンスを掴むには
2023.10.19 放送分