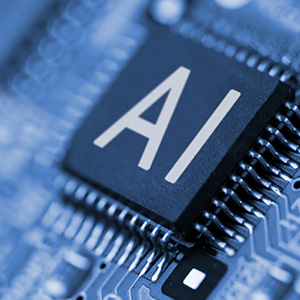2021.02.25 放送分
ゲームのSNS化
第17回アートリーアカデミア
THEME
ゲームのSNS化
オンラインで多くの人と繋がれるようになった現代、ゲーム内のチャットを通じてコミュニケーションを取ることは一般化しました。しかし、若年層が利用するゲームをプラットフォームとし民主活動家が抗議活動を行うなど、今やゲームはその枠を越えて「SNS化」しつつあります。見えない危険性を孕むデジタルプラットフォームに対し、我々ユーザーはどのように向き合えばいいのか。アートリーアカデミアでソリューションを見出します
TOPICS
ニュースの話題
- 佐藤
- こんばんは。アートリーアカデミアの時間です。
- 井戸
- 本日のお題はこちらです。「ゲームのSNS化。香港の民主化運動の舞台は『どうぶつの森』へ。昨年(2020年)4月、香港の民主活動家がコロナウイルスで外出が制限される中、ゲーム『あつまれどうぶつの森』を抗議活動の場として利用したことが分かりました。近年このように、ゲーム内のチャットを通じて、互いに意思疎通する「ゲームのSNS化」が進んでいます。主に利用しているユーザーには10代の若者が多いこともあり、楽しいデジタルプラットフォームに潜む危険性についても監視の目を光らせていく必要があるようです」
- 佐藤
- 本日のテーマは「ゲームのSNS化」です。まずはニュースの補足があれば、徹郎さん(お願いします)。
- 蒲生
- 「香港の民主化(運動)」については、(一時期は)いろいろとニュースで見かけていました。しかし、(新型)コロナ(の世界的な流行)により、外出が規制されまして(今や下火となっているわけです)。とは言え、「サーフェスウェブなどで活動すると、サイバーポリスなどに叩かれてしまいます。(だから、)「アカウントログインのいるゲームで活動するようになった」わけです。(詰まるところ、)「(ゲーム内の空間が)ディープウェブとして利用されている」ことになります。
- 佐藤
- 要するに、「みんなで集まって単にゲームしている」わけではないんだね?
- 蒲生
- むしろ、「ゲームはしていない」と思います。
- 井戸
- 要は「ゲームという体裁を隠れ箕にして」ですよね?
- 蒲生
- 重要なことは、「監視の目を潜り抜けること」ですから。
- 佐藤
- 「何年前なの?」と思うぐらい昔の話になるけれど「セカンドライフ」(というジャンルも) ありましたよね。……だけど、RYUちゃんは「セカンドライフ」と言われても分からないよね?
- RYUICHIRO
- 初めて……(聞きました)。
- 佐藤
- あれは結局、何だったんですかね?
- 和田
- (時代としては)「15年くらい前」かな?
- 佐藤
- (ともあれ、俺が)「学生くらい」だった気がする。(あの当時は)「ハイスペックなパソコンがないとセカンドライフゲームがやれない時代」で。あの類は、「3Dレンダリングがガンガンに掛かっていて処理が重かった」から……。(とりあえずセカンドライフゲームは)「現実世界と仮想世界を分けて、仮想の中で結婚もできる」みたいなことが「テーマ」と言うか「コンセプト」でしたよね?
- 原
- (それぞれのゲームごとに)アバターがたくさん作られて、一時期「すごく流行って」。(ゲームを)される方の中では、盛り上がったジャンルですよね。
- 佐藤
- (俺の)記憶の限りでは、あれが一番最初の「ゲームのSNS化」なのかな? だけど、あれ(セカンドライフゲーム)は「リッチコンテンツ」と言うか「リッチプラットフォーム」のような気もする。確かに、『Instagram』や『Facebook』、『Twitter』、『YouTube』などは「点のコンテンツの集合体」だろうけど。ゲームの場合は、ユーザーエクスペリエンス__ユーザー体験__の面でかなりの費用がかかっているから、「SNS」と言って問題ないのか……。……おそらく、「SNS」なのだろうけど、もはや「別の社会」なのでしょうね。……『フォートナイト』でしたっけ? あれは「アクティブユーザー数がすごい」と言うか「どのSNSよりも(ユーザー数が)多い」らしいよね。
- 原
- 今回の話は、香港では「煽動罪に当たる」と言われているけれど、もはや「広めやすい」ではなくて、「プラットフォームができているから、集まりやすい」のかもしれないね。だけど、「みんなで集まりましょうね」を「どうやって広めるか」が重要でして。そこを踏まえると、「ここ(ゲームの中)には、既に大勢の人がいる」わけですよ。だから、「プラットフォームに簡単に入れること」は、活動家からすれば「アピールしやすかった」のだろうな、と思います。とは言え、問題点は「10代などの若年層に対して、配慮がない状態で広げてしまうこと」だろうと思います。だから、仮に「大人しか入れないプラットフォーム」であれば問題ないような気がします。
- 井戸
- それか、「年齢別にサーバーが分かれている」方式でも良いかもしれません。
- 佐藤
- 話が逸れるけれど、(原)先生の話を聞いていて、ミチオ・カク先生の「マルチバース(多次元宇宙)」という考え方を思い出して。(マルチバースというのは、)「宇宙はいくつもある」とする考え方なんだけど。仮に今、「世界がマルチバース的だ」とすると、「地球の中ではある」けれども、世界は「子どもたちだけの社会」のように、「どんどんとセグメント化されていっている」わけだよ。確かに、「(本人の)体は地球上に存在している」のだけれど、精神的に見れば「(体がなくとも)存在できる場所」が「作られつつある」わけよ。そうなると、「世界がどんどんセグメンテーション(分割)化されていく」可能性もあるわけだよ。
- 原
- 要するに、まとめると「広がりながらもセグメント化がどんどん進んでいくのだろう」と思われます。
- 佐藤
- (とは言え、セグメント化が進めば、)企業によるターゲティングもしやすくなりそうだよね。確か「選挙運動」もそうだけれど、「実際にゲーム内に広告などを出している」んですよね? そう言えば、この間も「『フォートナイト』かどこかで誰かがライブをやって」(とかいう話でしたよね)。(それで)「興行収入が30分で何十億円」みたいな話で。
- 原
- 「米津玄師」でしたっけ? (※米津玄師は2020年8月7日に『フォートナイト』内でバーチャルライブイベントを開催した)
- 和田
- 確か、(彼が『フォートナイト』で)「初めてライブをやった」と思います。ウチの息子も『フォートナイト』をやっていて。(だから、)僕もその中でライブ見て、それ(がきっかけ)で「(米津玄師の)CDが欲しい!」となって、(CDを)買ってます。だから、大人は「(ゲームが)SNS化していることは問題だ」と言うのかもしれないけれど、子供にとっては「友達の家に遊びに行く感覚みたいなもの」だから。おそらく(大人と子どもでは)「(ゲームに対する)見方が違う」のかもしれない。
- 井戸
- (ライブというのは、)「米津さんの使っているキャラクター(アバター)がゲームの中でライブをした」んですか?
- 和田
- アバターではなく、「実際に(本人の映像をゲーム内に)映した」のかな?
- 佐藤
- 確か、「ゲームの中に大きなモニターと言うかスクリーンを出して」みたいな感じでしたよね?(※米津氏のライブは、ゲーム内に設けられたイベント用ステージのスクリーンに上映された)
- 和田
- そうですね。ちなみに『フォートナイト』では、「アカウントを作るとアバターが手に入る」んです。(それで、それ(アバターは))「エモート」という機能を使って「踊れる」んです。だから、会場に集まった人たちは「ダンス向きのエモート」を使って「踊る」んです。
- 井戸
- 確かに、『荒野行動』などでもその手のイベントが開催されていた気がします。
- 佐藤
- (だけど、『荒野行動』は)「もともとは殺し合いをするゲーム」だよね? だけど、「もはや誰も殺し合いせずに単にチャットをしている」だけなの?
- 和田
- おそらく(今でもゲームの)ベースは「殺し合い」だろうと思います。ただ、『マインクラフト』のように「クリエイティブ」と呼ばれる創造性を育むようなコンテンツやジャンルは増えているとも感じます。
TOPICS
テーマ討論
- 佐藤
- 一度、課題を見ていきましょう。
- 井戸
- 「ゲームのSNS化。課題:SNS化するゲームとどう向き合うか?」
- 佐藤
- ところで、RYUちゃんは「ゲームはする」の?
- RYUICHIRO
- 僕はゲームを全くやらなくて。(時代で言うと)『PlayStation2』(の頃 ※おおよそ2000年代半ば)で止まっています。(ゲームは)携帯でもやらないので……。だけど、(ダンススクールの)生徒からは「今このゲームが流行ってるよ」みたいにいろいろと教えてもらっています。そうは言っても、「これやってる?」と訊かれて、「やってないんだ」と答えてしまって話にならないですが。それでも、「YouTubeのゲーム解説動画」は「見せてもらったり」などの理由でたまに見ます。
- 佐藤
- ちなみに、生徒たちの声を総合すると何が一番流行っているの?
- RYUICHIRO
- 今……。白黒の……。顔が動く……。名前を忘れてしまった……。とにかく、「いろいろ」あります。(だけど、)いくつも聞きすぎて忘れました……。(※後でRYUICHIRO本人に確認したところ、『にゃんこ大戦争』であったことが判明)
- 佐藤
- 要するに「ゲーム会社も(販売したコンテンツが)SNS化することによって、コミュニティができるから移り変わりも激しい」んですかね? とは言え「ユーザーのLTVを伸ばす」ためにも「廃れていくまでの時間」は長く設定されているんですか?
- 原
- 『荒野行動』や『フォートナイト』もそうですけど、「ミッションやステージが増えていく」など、「バージョンアップされていく」んですよ。
- 佐藤
- それは、(ゲーム上での)「行ける場所が増えていく」ということですか?
- 井戸
- 確かに、「マップや武器が増える」ことはあります。ただ、「SNS化されるゲーム」は、「オンラインでも遊べる(ことが)大前提」なんですよ。私もゲームはしますが、「すぐに飽きる」んです。だけど、「オンラインでもできるゲーム」だけは未だに飽きていないんです。だから、「誰かと一緒に遊べるゲーム」であれば、「飽きずに続けられる」のかもしれないです。
- 佐藤
- (萌ちゃんは)ゲームをやるんですね。
- 井戸
- やりますよ。
- 佐藤
- (余談だけれど、)普段から接していても、未だに知らないことが多いんだよね。実際、(原)先生の場合、4〜5年くらい経ってから、「ゲーム実況なども見るんだ」みたいな発見があって。
- 井戸
- (そう言えば、)「(ゲームの実況動画を)見ることが好きだ」とおっしゃっていましたね。
- 原
- (ゲーム自体は)「やらない」けれど、「(ゲームの実況動画を)見ることは好き」なんです。
- 井戸
- 分かります。面白いですよね。
- 和田
- やらないのに見るんですか?
- 原
- やらないのに見るんです。例えば、RPGゲームなどで、他人がプレイしている動画を見て、「『ああ。俺、達成した』みたいな気分を味わう」と言いますか……。
- 佐藤
- そういう人もいるよね。
- 原
- 感覚としては、「映画を見ている感じに近い」と言いますか……。
- 佐藤
- 確かに、最近のFINAL FANTASYなどには、そういう傾向があるよね。「ムービーだけ見ていけば、クリアできる」と言うか。だけど、「どこか違う方向性」のような気もする。
- 井戸
- 言われれば、(あれ(最近のFF)は)「見るだけでクリアした気分になれ」ますよね。
- 佐藤
- 「ドラマ」みたいな感覚なんだろうね。どう向き合っていくべきなんですかね。もちろん、「誰が向き合うか」にもよるだろうけれど。
- 原
- 「悪いこと(ばかり)ではない」と思います。(ゲームの中が)SNS化すれば、交流も増えて、会話もたくさんできるので、賛成です。だけど、「どこでセグメントを仕切るの?」という観点が、「曖昧」と言うか「成年か未成年か」ぐらいしかない感じですよね。だから、「もう少し区分けしておかなければならない情報」もあるような気がして。ただ、昔のテレビでは「(多少)過激な(内容でも)放送されていたものが、今では全て規制されている」わけですよ。要するに「どこまで規制するのか」だと思います。要は「考えるベースとしての情報」はあっても構わないけれど、「それ(思考のベースとなった情報)が決断に結び付くか」は、個々で違うはずなんです。だから、「創造性や考えることの妨げにならないこと」を大前提にするべきだと思います。この手の話はどうしても「規制ありき」になるけれど、「規制をすることが大事」なのではなく、「考えるベースをきちんと作ってあげた上でどうするか」も、真剣に考えなければ。土壌が良いのに規制されてしまうのは「もったいない」ので。
- 佐藤
- ちなみに(SNS化したゲームの中で)「犯罪などが起こる可能性」はあるんですかね?
- 蒲生
- ゲーム化しているSNSのユーザーには、「未成年者が多い」んです。だけど、親の世代によってはそうした(ゲームすらSNS化している)ことに対する想像が乏しいことから「監視できていない」という問題もあって。だから、「過激な表現や性的な表現、あるいは詐欺などの犯罪まがいなものを流そうとしている不届きな輩」も「少なからずいる」わけです。だから、そうした「良からぬもの」を子供が選択してしまって、「犯罪に巻き込まれてしまうかもしれない」という懸念がされていると言えます。
- 佐藤
- 「顔が見えない」と言うか「アバターになっている分、マインドだけがスッと入ってくる」みたいなね。以前の放送回でも言ったかもしれないけれど「直接会って、面と向かって悪口は言わないよね」みたいな(話ですよね)。だから、(例え)「ゲーム越しに話している」としても、「顔は見えないけれど、相手のアイデンティは認識した上でコミュニケーションを取る」わけだから。要するに「よりリアルに近くなってきている」からこそ、「上手に使っていければ、マインドが共有しやすくなる」わけですよね?
- 井戸
- とは言え、若者たちに対しては「モラル教育が必要」だろうとは思います。確かに、「SNSを規制」すれば、「おそらく安全」なんです。だけど、(ゲームは)「そもそもが非現実の世界」なので、「それ(SNS化する)なら、それ(SNS化する)で良いじゃん」とも思うんです。確かに(社長がおっしゃったように)、「そもそもは殺し合いのゲーム」というコンテンツもありますけれど、何に付けても「モラルは必要」なので。それから、原先生がおっしゃっていたように、「分別が付く年齢とそうではない年齢でサーバーを分ける」なり何なりはしていかないと難しいでしょうね。
- 佐藤
- それならいっそのこと、「上場企業に対する監査法人」や「世間における警察」みたいな感じで、ゲームの中に「警察のような取締機関」を置くべきなのかもね。……「ゲーム内」であることを考慮すると、(警察役を務めるのが)「運営」なのか「第三者機関」なのかは分からないけれど。要は、(担当者が)アバターとしてゲーム内にいて。「君たち、早く寝なさいよ!」みたいに注意喚起をしていくというか……。
- 井戸
- 面白いですね。「規制」ではなく、「警察がいること」は「アリだな」と思いました。特に、「ゲームの世界観を壊さない感じで存在させる発想」が良いですね。
- 原
- しかも、それ(ゲーム内ポリス)が画面の中で動いていれば、なおのこと(犯罪などに対する)抑止効果はあるでしょうね。「あの人、やられてる!」みたいに。
- 井戸
- 「捕まってる!」や「退場させられてる」みたいな状況が目に見えるようになりますものね。
- 佐藤
- 確かに、そういうアクションがあっても良いかもしれない。それなら「(実際の警察官のように)公務員」でなく、「時給のバイトでも構わない」ような気もする。
- 井戸
- (それなら、警察官でなく)「すごく怖い化け物」が出てきても面白いですよね。
- 佐藤
- だから、やがては世界的に「(取り締まられることにより、)さらに健全に運営されるようになる」みたいなね。だけど、言い換えれば「社会はモラルだけでも成り立つ」わけだよね。要は、(現実世界には)「法律」があるけれど、この世界(仮想現実)には、「誹謗中傷したらダメ」と言った「最低限のルールはある」けれど、「法律はない」わけだよね? だから、言い直すと「モラルが高い」と言うか「自分たちで(居)場所を守っている」わけだよね?
- 原
- 「やりたいことができなくなるのは嫌だ」となると思います。(だから、)「そうした(モラルのない)人たちは弾かれる」傾向にはなりやすいと思う。それこそ、「オンラインゲームでは多い」でしょうね。「スタンドプレーをしたがる人は、周囲から嫌がられる」わけですから。これが表現として適切かどうかは分かりませんが、ある意味では「一種のムラ」ですよね。「コミュニティの作られ方」は、それぞれの地域(ゲーム)で違うかもしれないけど、(例え)ゲームの中であっても「(マナーやモラルを)大事にしたいね」という気持ちを持って、(好意的に)やりたい人たちがいることは、何よりも素晴らしいですよね。
- 井戸
- 確かに、「ゲームを(違法)改造している人たち」は「しばしば排除されて」いますものね。
- 佐藤
- 今の「ゲーム内ポリス」ではないけれど、「ゲーム内でバイトができるようになる」とすると、「本当に外に出なくなる」かもしれないよね。
- 井戸
- 確かに、(ゲーム内でリアルの)物が買える(状況になるのであれば)。
- 佐藤
- 物が買えれば、「リアルマネーも動く」わけだから。
- 久田
- 確かに。すごい!
- 佐藤
- 家庭教師などもできそうだよね。
- 井戸
- 確かに。例えば、「そこ(仮想現実)でUber Eats頼んだら、現実に届く」わけですよね?
- 佐藤
- そういうこと。
- 久田
- そう言えば、『どうぶつの森』で、「草むしりのバイトをする」みたいな話もありましたよね。
- 佐藤
- だけど、それ(『どうぶつの森』での草むしり)は「ゲームの中の話」でしょう?
- 井戸
- でも、「ゲームの中で草むしりをしてくれたら、リアルマネーを払う」というパターンもありましたよ?
- 佐藤
- そういうこともあるのか。……確かに、俺もモンスト(モンスターストライク)にはまってた時に、「覇者の塔(※モンスト内で毎月月初2週間開催されている定期イベント)、勝手に登っといて」みたいなことは、一瞬だけど考えたことがある。
- 井戸
- 「忙しい時にログインボーナスだけ貰っておいてくれ」であったり。
- 佐藤
- なぜそう思ったかと言うと、「(人間は)精神だけでは生きていけない」から。だから、「どうやって(社会との)『密接な繋がりを持てれば良い』のかな?」と思って。例えば、「ゲームの中でバイトができる」にしても、我々は「あくまでゲームとしてやっている」にしても、「リアルとも繋がっていることを認識できれば良い」と言うか。だから、(SNS化しているゲームのメインプレイヤーが)「子どもたち」であることを前提に考えると、「ゲーム内に英会話を教えてもらえる学校がある」というアイディアも良いかもしれない。そうすれば、「こっち(仮想現実)の中だけで完結しなくなる」から、「勝手に疎外されなくなる」よね。そうなると、次は「どうやって社会に繋げるか」が課題になるわけだから……。要するに、(SNS化しているゲームは)「プレイヤーたちが作った1つの社会や学校みたいなもの」のはずだから、「大人たちがもう少し(SNS化しているゲームを上手に)使っていけば良い」気がする。
- 井戸
- さらに「そこ(ゲーム内)でリアルマネーでお金を稼げれば面白いだろうな」とも思いました。
- 佐藤
- (著作権や)「知的財産」の話さえできれば、(何だって)できそうだよね。
- 原
- 「ゲーム内の顧客満足度を上げられるかもしれない」わけですよね。
- 佐藤
- 「LTVを伸ばすきっかけ」にもなりそうだよね。
- 原
- ゲーム会社からすれば、「大歓迎」でしょう。
TOPICS
みんなの声
- 佐藤
- ……それではそろそろ、みんなの声も見てみましょうか。
- 井戸
- すっかり忘れてました。他の生徒の声を聞いてみましょう。『ゲームの事全く知らんっぽいコメント、乱立してる時あるけど。』
- 佐藤
- そうだよね。そっち(SNS化)のほうが「優先」と言うか「先行」していくと、「最初からゲームとして楽しもうとしていた人たち」からすれば……。
- 井戸
- (SNSとしての)「プラットフォームとしてしか利用してない子たち」が「(ゲームに対して)無知なことを曝け出していた」としたら。
- 佐藤
- 「ウザいなあ」と思うかもしれない。
- 井戸
- 次にいきましょう。『もはやチャットないゲームは物足りない』。求めているんですね。
- 原
- コミュニケーション(欲求)を満たしたいんでしょうね。
- 佐藤
- 俺は全然……。そもそも「チャットをしたくない」と言うか「LINEも返したくない」けどね。
- 原
- そういう状況もあるよね。
- 井戸
- 次へいきましょう。『これからは実名でネットゲームする人が増えていくのかなぁ。』
- 佐藤
- だけど、それもひとつ(の手段)ですよね。「責任を持ってゲームするんだよ」と言うか「ゲームという場所を認めてあげること」と考れば、また変わってくるかもね。
- 井戸
- だけど(実名の場合)、「せっかくゲームなのに好き放題にはやり辛くなり」ますよね。
- 佐藤
- それ(ゲームで好き放題したい)なら、無理に「実名」にしなくても構わないだろうけど。「他人とのコミュニケーションに責任を持つことは大切」ですからね。
- 井戸
- 最後の声にいきましょう。『SNS化するゲームもあれば、ゲーム化するSNSもある。』
- 佐藤
- 「ゲーム化するSNS」とは何だろうね?
- 蒲生
- 例えば『LINE』が挙げられるでしょうね。LINEの中でゲームが出てきて、そのポイントを友達に付与できたりしますよね(※おそらく『LINE GAMES』のこと)。そんな具合で『Facebook』や『Instagram』などでも、「その(プラットフォームの)中で、友達とゲームができる」ようになってくるかもしれません。だから、(これから先は)「競争になる」ような気もします。
- 佐藤
- そう言えば、「IT系やデスクワークが主体の会社」では、「ゲームを点けて」と言うか「(ゲームを作業用BGM替わりに)聞きながら」仕事をしている社員が「結構いる」らしいね。
- 井戸
- それは、(PCゲームを)「オート(モード)で点けている」わけですか?
- 佐藤
- 「オート(モード)」ではなくて『YouTube』らしいんだけど……。
- 井戸
- それならいわゆる「実況(動画)」ですね。
- 佐藤
- 実況動画ぐらいなら「構わない」だろうけど。いわゆる「依存症的な子たち」が大人になった時に、徐々にこっち(ゲーム)の世界やチャットでの会話が気になりすぎて、「仲間外れになりたくないから」という理由から、「ずっとそこ(ゲーム)の中に浸かっているという可能性もあるかもしれないよね。
- 原
- (しかもゲーム世界に)「接続しっぱなし」でね。
- 佐藤
- 仮に「ゲームデバイスが『Google Glass』のようなウェアラブル端末が主体になった」としたら、そういう可能性もあり得るよね?
- 原
- (何が問題になるのかはよく分からないけれど、)「何かしらの問題は出てくる」でしょう。
- 佐藤
- 結局、考え方が「まだ黎明」なんだろうね。そろそろ(時間的にも)「ソリューション」ですかね? 「ゲーム化するSNSとどう向き合うか」だったっけ? 今から考えてみます。
- 井戸
- ソリューションタイムに参りましょう。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- 今日のソリューションは、「ゲーム内ポリスを!」
- 井戸
- 珍しい!
- 佐藤
- 流れを変えましたよね。「課題に向かって(考えて)いく」のではなくて、会話自体がすごく楽しかった。
- 原
- たまにはそういう回も良いでしょう。
- 佐藤
- だけど、実際に(ゲーム内ポリスが)「いれば良い」よね。
- 井戸
- 「面白い」「最高だな」と思いました。
- 原
- 確かに、(ゲーム内ポリスが)画面内にいたら「面白い」でしょうね。
- 佐藤
- ゲーム内の先生みたいな感じでね。……もしかしたら「BOT」でも構わないかもしれないけれど。
- 井戸
- 確かに、(BOTでも)構わないかもしれないけれど、実際にいたほうが面白いでしょうね。
- 佐藤
- (ゲーム内に)「実在する」わけだからね。
- 久田
- そもそも今や「(家族以外の)大人に実際に怒られる機会」自体、「なかなかない」はずなので。そういう意味でも貴重な体験になるでしょうね。
- 佐藤
- そうだよね。俺らの子どもの頃は、「電車で土足(靴)で座席に上がっていたら、知らないオッサンに怒られた」なんてことはザラにあったよね。
- 原
- ド叱られましたよね。
- 佐藤
- だから、そういう存在があっても良いのかもね。ゲームの中に「古き良き大人を」と言ったところかな? ……それに変えます。ありがとうございました。「ゲーム化するSNS」というテーマで面白い話ができたように思います。だから、こうして実際の(現実社会との)結びつきが深くなれば、面白いだろうと思います。だけど、そうは言っても「あまりやりすぎてもダメ」だから。ソリューションを書いている時に、「SNSやゲームの中に学校を作ってしまえば良いよね!」なんて思ったりもしたけれど、あまりそちら(仮想現実)に寄りすぎてもね。
- 井戸
- 現実も大事にしてほしい。
- 佐藤
- 何事も「バランスが肝心」でしょうね。今日はこのような感じです。ありがとうございました。
- 井戸
- ありがとうございました。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
【アートと経済】アートと経済の融合がもたらす企業革命!「アートと経済」総集編
2024.08.22 放送分
デジタル⽥園都市国家構想に補助⾦の追い⾵!地⽅創⽣に取り組んで新たなビジネスチャンスを掴むには
2023.12.14 放送分
サーキュラーエコノミーの未来を担うZ世代!新しい消費パターンを取り⼊れてビジネスを成⻑させるには
2023.11.30 放送分
アートがビジネスを発展させる?アートと経済社会について考えて企業価値を高めるには
2023.11.16 放送分