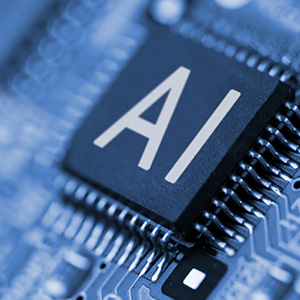2023.11.16 放送分
アートがビジネスを発展させる?アートと経済社会について考えて企業価値を高めるには
第159回アートリーアカデミア
THEME
アートがビジネスを発展させる?アートと経済社会について考えて企業価値を高めるには
アートが企業価値向上に与える影響を探ります。アートは創造性、ブランディング、社会的貢献において魅力的な選択肢です。アートをビジネスに統合し、創造性と革新を促進し、社会に対して意義のある貢献をする方法を議論します。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、今夜も始まりました、アートリーアカデミア。
- 井戸
- 本日のテーマは「アートがビジネスを発展させる?アートと経済社会について考えて企業価値を高めるには」。さっそくフリップを見ていきましょう。アートと経済社会について考える研究会報告書です。経済産業省が日本のアートシーンの活性化に向けて設置した有識者からなる研究会でして、議論のポイントが四つあります。それぞれ、アートと企業・産業、地域・公共、流通・消費、テクノロジーといったものが挙げられています。
- 佐藤
- これ、経産省が初めてアートについてこういう研究会を実施したってことで、アートっていうのが、経済や社会でどういった影響を与えて、どういったポテンシャルがあるのかっていうところが議論の中にあるんだよね。それが企業だとか産業、流通・消費、地域・公共、テクノロジーっていうところの四つの大ジャンルで分かれて報告書が構成されてるんですけど。これそもそも、先進国、他国に比べてアートの市場っていうのが国内むちゃくちゃ小さいらしいんだよね。だから結局、アート市場を作りたいっていうところと、アートを作り出す人たちだとかアート作品とかが、経済社会に対してどういった影響を逆にもたらせれるのかっていうことを研究するっていう趣旨のテーマで、経産省が主催してやってるっていう話なのよ。こういったものが、創造性が求められてる背景っていうものがあるんで、それを見ていきましょうか。
- 井戸
- 創造性が求められる背景です。コストや機能面で競争優位性を作れた時代は、アートやデザインは、経営とは比較的遠くにあったんですが、グローバル化、デジタル化、価値観の多様化、不確実性の上昇といった経済社会の変化に伴って、差別化が困難な時代に突入してきたという背景があります。
- 佐藤
- だから、結局経産省っていうか経済社会自体がアートの力を使って取り入れたい。その背景として何があるかっていうと、まず一つ、その不確実性。VUCA時代といわれているんですけど、アーティストの思考って100年200年とか結構先のビジョンっていうものを予測して描けるっていう特性があるらしくて、それがまさに不確実性で、今、目の前のことを見てても何があるかわからないから、だから結局向かってく先のところっていうところに対して、アーティストの想像力とかを拝借したいっていう考え方があったりするっていうところがまずあるのかな。そこがでも一番大きいんじゃないかな。結局、デジタル化、グローバル化、経済社会の成熟化が不確実性の増加につながってるわけなんで。
- 原
- 行き着くところが見えてこないからってことですよね。
- 佐藤
- そうそう。だから既存のフレームワークだとか、既存の既知の考え方だとか、そういったものじゃこの先の世界は読めないから、だからアート思考だとか、アーティストたちの経営への参画だとかビジネスへの参画とかで、要はその不確実性の世の中を見通していこうっていうのが逆にある。逆に彼らに対してはこれ次の俯瞰図で説明するんですけど、機会を提供していきましょうっていう話なんです。それを見ていきましょうか。
- 井戸
- アートと経済社会の俯瞰図です。
- 佐藤
- っていうふうになってますと。これ下支えにあるのがテクノロジーなんだけど、まずこの企業、地域、これ見方なんだけど、企業、地域、消費者っていうのがいて、で、下支えで経済社会を支えてるのはテクノロジーが支えてますと。で、プラットフォームの提供だとか、新たな表現方法の提供、それをアートに対してしていくと。NFTとかこういうのを挙げられていくと。で、プラットフォーム提供っていうのはマーケットプレイス。それをウェブ上で、ウェブサービスとかでアートが買えるだとか。それで企業に提供していく、データ連携インフラとか。で、デジタルコミュニティの地域活性化で、新たな体験、所有の在り方を提供していくっていう、これもNFTだよね、だから。で、結局アートの目線から見ると何があるかっていうと、企業、地域、消費者から得られるものってのは、この収益源、まずお金の部分と、あとは機会提供っていうところなんだよね。例えば、それこそうちが、アートリーが豊川稲荷でYORU MO-DEってやつにかかわってるじゃん。あれが、例えばもし俺らがアーティストだったとしたら、要はプロジェクションマッピングを作りましたと。そのアート作品を、向こうからしてみたら機会を提供しとるって話だし、それに対して、じゃあプロジェクションマッピング作ってくれたから制作費も払いますと。こういうかたちの構図なんだよね。うちとしては、そのアート作品を地域っていうか企業だとか消費者に、イベントだとか夜間参拝だとか、そこを支えるためのアート作品ってものを提供していますという構図が成り立つってことだね。で、それぞれ何が得られるかというと、例えば企業だったらブランディング、企業価値の向上。ブランディングもそうだし、あとは、ESG投資なのか、この要は社会貢献的な部分で、地域っていうところで言うと、この地域の文化創造、だから要は文化の再解釈的な部分。消費者にとっては社会の創造性の向上、だから消費者だけじゃなくて社会全体の創造性を付加価値で上げていきましょうと。っていうような、こういう俯瞰図で狙いがあるっていう感じですね。これ、渡邉さんどうですか。アーティストというところで。こういったことを経産省は描いてるっていうことなんですけど。
- 渡邉
- 東京コレクションも、楽天がスポンサーになって楽天コレクションというか、ああいうふうになってるんで、そういうデザイナーたちのステージっていうのを一企業がやってますよね、東京だと。それの大きい版でバックアップしていこうという感じだと思うんですけど。ありがたいですね、こういうのがあると。
- 佐藤
- そうだよね。だから結局アーティストたちにお金を還元してかないと活動ができないから。それこそ音楽のミュージシャンとかの話になっちゃうと、売れてないミュージシャンが30、40にもなってまだバイトだとかあれとかしながら音楽をやってるみたいな。それじゃあ創造性フル発揮できないじゃんってのがわれわれバンド、子どもの頃とかやってた時代、そういうあれがあったから。もう働くか、働きながら趣味でやるかとかさ。だからそういう、何かあんまりよくない。でも古くを言えばメディチ家がいろんなアーティストを支えてきたように、要はそういうパトロンみたいな存在があったからそういう作品に集中できたっていう話。それを、例えばローマとかだったら大衆浴場の絵にとか教会の絵とかに、宗教としてそういう絵、天地創造だとかミケランジェロが描いたやつとか、ああいうのをパトロンが支えてとか、それが地域のアート、その時代だってデジタルも何もないわけだから、そこには想像してる、人が、偶像崇拝じゃないけど、するようなわかりやすいものをビジュアルとして置くわけじゃない、教会の中にも。そういうなものに近いよね。だからそれを再解釈して今これがあるっていうかたちだし。で、前々前回かな、やったナイトタイムエコノミーでちょろっと話した、それこそビビッドシドニーっていう、シドニーで3週間、その街全体の夜間の経済を盛んにしましょう。だから、そこも結局プロジェクションマッピングばんばんやってて、いろんなアーティスティックな要素があって、人をひきつける力があるから、アートって。そういった意味でも地域だとか企業、消費者っていうところにもかかわってくるのかなっていう。で、もう少し言うと、それこそ今自治体に提案してるメタバースの案件とかで、要はビジョンとしての要件でいくと、障がい者とアートっていうところを取り入れるっていうこともあったりするんだよね。これ次回やるんだけど、発達障がいの方たちっていうのは、個性っていうふうに捉えたときに、大体ゴッホとかもちょっと発達障がいというか、自分の耳切ってゴーギャンだったけ、誰かにあげたりとかさ、そういうことやったりする、ちょっと変わってる人たち。だけど、そのぶんやっぱり天才的な部分っていうのが。そういったところをアートに活用していくっていう、社会的なSDGs的な部分でもあるし。だから要は個性と捉えてそういう部分のアートとしての活用をしていきましょうっていう行政の、自治体とかの動きとかもあったりするんじゃないかな。だから結構アートってのはすごく注目されてるのが、結局、要は結構根底から人っていう社会の部分にもうあるものってのを再解釈していく。特に日本ってやっぱり弱かったっていうのがあるっていう。
- 久田
- 買わないですもんね、絵とか。
- 村上
- えっ、私?びっくりした(笑)。
- 佐藤
- でもそうじゃん。だけど、うちの会社って結構アートあるの知ってる?(笑)。
- 久田
- うん。あんま気にしたことないけど、そういえば壁にかかってる。
- 佐藤
- 壁に絵がかかってたりとか。
- 原
- 書籍も結構お持ちですもんね。
- 佐藤
- 書籍も、あれは父のものだったりするんですけど。結構、教育の面でも実は言われてて、それこそ坂本龍一さんとか亡くなって、文化資本とかちょっと話題になったんだけど、要は子どもの頃にどんだけ身の回りにその文化資本があるかで、創造性だとかそういったものっていうのが養われるらしいんだ。だから本当に、家の中に例えば美術があるとか骨董があるとか、俺んちそうだったんだけど。そういった文化資本、音楽とかもそうなんだけど、そういったところも結局アートってのは、その教育のところにも結びつくし。だから結構このアートと経済社会ってのは、今さらだけどこういうことをやりだした、話し出したっていう。
- 久田
- アート自体、だって、古くは壁に絵描いたりしてた頃からあるから、やっぱ人間の根幹にあるんでしょうね。
- 佐藤
- そうそう。だってラスコーの洞窟の絵だってそうでしょ。
- 原
- 動物の壁画ですよね。
- 佐藤
- そう。壁画からあるぐらいだから、根源的な人の行動なんだよね。
- 村上
- 普遍的っていうか、変わらないものなんでしょうね、結局。昔からずっと変わらなくて、どんなに世界が発展しても、みんな心を動かすものっていうのは変わらないっていうところなんでしょうね、きっと。
- 佐藤
- そうだと思う。
- 村上
- だからこそ企業と結びついて変わらない、これを見ると人は感動するっていう変わらない普遍的なものを取り入れていこうという考え方なのかもわかんないですね。
- 佐藤
- だから身の回りにアートなんていっぱいあるのよ。だって、古くを言えばピラミッドがまずそうでしょ?王墓があって、ピラミッドっていうのはナイル川が枯渇してるときに民を養うために王の墓を作らせるっていうことで給料を出しとったりだとか。
- 久田
- 国がやる事業だ。
- 佐藤
- そう。国がやる事業としてピラミッドを建設して、ナイル川が荒れたときに民が田んぼとかができないから公共事業としてやらせてたりだとかもそうだし。で、それが街のシンボルとしてなっていくとか。でも、じゃあ例えば、今ビルとか建てるにしてもすごくアーティスティックなビルがいっぱいあるじゃない。東京なんか行ってもさ。愛知県はあんまないかもしれんけど。そういうものもそうだし。だし、それこそ例えばスマートシティだとか、いろんな多様的な人種がいる中で、それこそ身体障がい者の方たちだとか、要はバリアフリーを作っていくためにはどうデザインしていくかっていう、これもアート的な思考になってくるわけだし。必ずしも絵の具を持って書くことがアートなだけじゃないから。じゃあ最後のフリップを見ていきましょう。
- 井戸
- アートへの投資と期待される効果です。
- 佐藤
- これはそう、ちょっと細かいんだけど。芸術活動を支援していきますよっていう軸が単独でもあるんですけど、あそこに。で、事業活動にどうやって投資して期待できるかっていうと、内部活動と外部活動ってところで、社内改革と人材の採用とか開発。で、対外発信と事業開発っていうところで、どうやって応用できるかっていうところを書いてるんですけど。で、大、中、小ってところで、小分類で言うと、エンゲージの部分とインスピレーションの部分。これが内部的な部分で、外部的な部分で言うと、このプロダクト開発だとかブランディングで、コーポレートのブランディング。あと、ローカル、だから地域のステークホルダーたちに対する影響。これ、どういうことができるかっていうと、例えばエンゲージメント、内部活動においては、従業員にとりあえずこのアートにふれさせることによって、まず採用だとかリテンション、リテンションってのはエンゲージメントをキープさせることだよね。
- 原
- リテインか。維持。
- 佐藤
- そうそう。維持すること。で、まず価値観とか、このエンゲージメントを育てるっていうところだとか、社内風土の養うっていうところもそうだし、インスピレーションっていうところで言うと、そういったものをふれさせることによって難易度が高かったり抽象度の高い問題、課題っていうものを解決するための一つの体験、経験としてそういうものをやらせるっていう。あと、プロダクトとかブランディング、この辺はわかりやすいじゃない。車なんかでもどんどんアートのあれを取り入れてるし。製品、サービス。で、コーポレートについては、それこそブランディングでビジュアライズしたものだとか、そういったもので優れたイメージに持っていくと。で、ローカルに対しては、地元のステークホルダーに対して優れたイメージ、自社が位置する地域における文化芸術活動の支援とかってね。だからココイチの、
- 村上
- 宗次ホールですね。
- 佐藤
- クラシックのホールを運営してたりだとか、そういったこととかも挙げられるのかな。これ、先生どうですか。
- 原
- 最初、アートとビジネスって、経産省のやつを見てても、いまいち理解できてなかったんですよ。今、話を聞いて、なるほどなって、ようやく腑に落ちたところだったんだけど。
- 佐藤
- 本当。だから何でぴんとこなかったの?それは。
- 原
- 勘違いしてたのは、アート思考の部分だったりとかもあって、
- 佐藤
- でも、それは含まれるよ。
- 原
- 含まれるよね。なんで、それが多分内部だったりとかいう話になってくると思うんだよね。その一方で、じゃあ製品とアートっていうのが、イメージが工業デザインみたいなイメージが強くって、さっきのバリアフリーとかさ、そういう部分と全然ひもづかなかったの。あとプロジェクションマッピングとかも、言われて、あって思った感じだったから。
- 佐藤
- よくデザインとアート、何が違うのかみたいな部分もあると思うんだけど、デザインっていうのはあくまで意図を持って創造性を持つことなんだよね。俺の会釈では。だからデザイン思考っていうのは、例えばウェブ制作とかも、グラフィックデザイナーとか、まあウェブ制作にしようか。ホームページ作るうえでデザイン思考って考えると、どういうことかっていうと、ユーザーの目線に立ってデザインしていく、絵を作っていくことがデザインなわけよ。だからデザイン自体は相手の、狙ってやってっからどっちかっていうとマーケティング要素のイメージだね。デザインして、だからコンセプトを作り上げるとかビジュアライズするのはどっちかというとアート的な発想ってかアート的な部分だから、クリエイティブになると。どこまでいっても土壌にあるもの。
- 原
- だから、オーダーじゃなくて内から出てくるものだもんね、本来。
- 佐藤
- 創造的な部分っていうのはやっぱアートになるわけだから。組み合わせたりだとか、そういう頭の中にあるものとかを。
- 原
- だから、そういう意味でなるほどなと思って。
- 佐藤
- だから工業デザインはアートなわけ、考え方によっちゃ。
- 原
- そうだね。その形、機能性だけじゃないところっていうところだからね。なんで、そういう意味で言うと、経産省がこれを大々的にうたっていることの重要性みたいなものが逆になおさらって、VUCAの色が濃すぎるんだろうなっていうふうには思ってて。
- 佐藤
- だし、だからもう一つ言えることは、ちょっとデータが、これ見たら出るんだけど、すごく小さいんだわ、日本におけるアート市場が。恐ろしく小さい。
- 久田
- 海外はもっとある?
- 佐藤
- 海外はもう全然ある。だし、だから結構それこそいろんな目線、視点から分析してたからあれなんだけど、何かイギリスと日本を比べても10分の1ぐらいの市場だよね。何かのあれで、4.何%ってイギリスは出してるのに対して、日本は0.4%とか。限りなく少ない。10分の1ぐらいだよ、多分、イメージ的に。
- 村上
- だから、音楽大学とか芸術のそういう専門の学校いかれても、それで食べていける人って本当ごく一握りというイメージしかないんですよね。普通に就職されるとか学校の先生されるとか。それを本業にして、音楽でやっていくとかってイメージがあんまりつかない。そういうことですよね。
- 佐藤
- だけど、最近音楽大学でもアクセンチュアとかが音大の人間をスカウトしてきて、これ前アカデミアでやったんだけど、音楽を読みとく、楽譜を読みとく力って、マーケティングの数字を読み解く力と一緒だから。だからアクセンチュアの人たちは音大生をひたすらスカウトしてきて、データサイエンティストにしていってるということもあったりとか。一回、本日のアジェンダ見ていきましょうか。
- 井戸
- はい。「アートがビジネスを発展させる?アートと経済社会について考えて企業価値を高めるには」。
- 佐藤
- 何か今、今までの話をしてて、アートがビジネスを発展させていくようなイメージがあるのかなって。だから逆に言うと伸びしろがまだ日本には残ってるのかなって。しかも、文化的な資産もたくさんあるから、日本には。日本は日本独自のアートを醸成してきてるから。こういったもので企業価値を高めて、ひいては海外にそれを羽ばたかしていく力もあるのかなっていう。どうでしょう?渡邉さん。どうやったら企業価値を高める。
- 渡邉
- 企業の見せ方の表現の仕方をアートで補うというか、なのかな。アートっていうと、アートと商業って対立して描かれることが多いと思いますし、例えばKing Gnuやってる常田さんっていますけど、King GnuはJ-POPとして商業的なビジネスモデルとして作って、本当にやりたいのはミレパって言われてるmillennium paradeとか、そういうアーティスト集団、本当はこれがやりたいんだけど、その軍資金を得るためにKing Gnu作って有名になって、本当に自分たちの聞かしたい音楽とかクリエイティブを出すと。これは公言されてるわけだし、僕もVEDUTAという和服をストリートのブランドとして高めていく。ただ呉服業界っていうのはどんどん廃れていって、当然パイが小さい中で服を作っても売れないわけで、ここは消費者の需要喚起をするところから始めなきゃいけないっていうところで時間はかかると。これは大きいゴールなんですけど、それをやるために、じゃあ日々の生活費、制作費とかプロモーション費を稼ぐために、同じデザインなんだけど、じゃあゴルフの市場が盛り上がってきた中で、じゃあゴルフアパレルの業務委託を受けて、それで商業的なところは潤わして、それでVEDUTAを走らせ続けるという、分けてるんですよね。だから、ゴッホも死ぬまでに売れた絵は1枚とかいわれていて、甥っ子が広げて売れるようになっていくわけですけど、死後。ただ、びしっと大衆にはまるそのアートが、ドンズバで刺さって売れてるときから、生きてるうちに売れる人と、死んだあとに売れる人といるわけなんですけど、そのバランスが難しいですよね。そこを企業とかがマーケティングとかをして、刺さるポイントを教えてくれた中で、アートの表現で企業ができないような表現の仕方を見せるとか。お互いにないものを補い合って世の中ハッピーにできればお金も動くのかなっていう気がしますよね。
- 佐藤
- 何か今の話聞いててやっぱ思うのは、そのKing Gnuの常田さんもそうだし、渡邉さんもそうだと思うんですけど、要は作品で食おうという考え方になるとそうなるんだよね。イメージ的にはアーティスト、アートに携わった人たちが仕事の幅を広げるってイメージだよね。仕事としてやるって言ってるところと、作品を作るっていうところで、確かに違うっちゃ違うんだけど。だから、さっきの中世の話とかだと、教会の絵を描くとかは、あれは本人からすりゃ作品かもしれんし、だけどこういうもの描いてくれって言われて描いてるわけだから、それって人に頼まれてやってる、デザインといえばデザインだし、それは。だから解釈の違いだけであって、イメージ的にはコラボレーションをするっていうイメージで考えていくといいのかなっていう、アーティストとしては。
- 原
- そうか。純粋に作品としてだけではなく、コラボ作品みたいな感じのイメージで、コンセプトがあってっていうところってことね。
- 佐藤
- そうそう。だから、例えばVEDUTAの服で飲食店の制服が作りたいとか、じゃあVEDUTAの感覚で、着物じゃなくて、この今から作るビル一棟デザインしてもらうとしたらどんな絵になりますかみたいな。で、コンセプトだけ描いてもらうとか。で、それを落とし込んでくでもいいし。だから作品の幅を広げるっていうのができれば、アーティストは苦もなくやれる部分もあるし、逆に言うと、基本的に自分の、要は何かとコラボしたほうがやっぱり早いんだよね。認知されてるものといくから。だから先に、機会提供にもなるんだよね。機会提供と収益源っていう。だから、生きていく活動資金っていう、普通に収入の機会にもなるし、で、そのアーティストがコラボした作品によって、企業的なとか地域的なとかっていうものとコラボすることによって認知が広がると。だからまず企業だとか地域だとかに、アートとアート活動、職業アーティストとして、職業デザイナーみたいなイメージ、職業アーティストとしてそういうもの携わっていく。で、名前がどんどん売れてきて、だけどその人は自分の作品もあります。で、こういう作品が今度は消費者に売れていくっていう。で、それも消費者が、そうやって携わってるだんだん消費者が買いやすいアートって何だろう?みたいな感じにもなりやすいじゃない。
- 原
- 消費者側が要は目を、見つけるっていうところになってきたときに、それを、何を買うっていうところが、コラボじゃないとわからない、理解できなかったところが、その人の本来の作品に行き着いたときに、その価値をどう見るかっていうところなんだね。
- 佐藤
- そうそう。だから渡邉さんの場合、いいか悪いかっていうのはあると思うけど、例えばエルメスのカレみたいに、額縁に入れて絵にする人もいるじゃん。エルメスのあれとか。例えば、着物はなかなか着る機会ないからあれなんだけどっていう、だけど着物が例えば額の中に入って、めっちゃでかいやつがあるとなったら、これは、なら絵として欲しいわって思う人もいるかもしれないし、でもそれは、だから着てもらわんと衣服じゃないもんでっていう話になりゃそれだけだし。だけどそれがコンセプト、要は伝えたいことってのが伝わるんだったらかたちはどうであってもいいっていうんだったらそれはそうだし、それはアーティストそれぞれの考え方だと思うんだけど。
- 渡邉
- 職人さんとのコラボって今までやってきたんですね。有松搾りだとか、石見神楽ってお面の面師さんだとか、いろいろやってきた中で、今、合気道ウェアの会社があるんですね。そことコラボして、VEDUTAとしてストリートウェアとして着れる合気道の道着を作ろうという話になりました。
- 佐藤
- だから、そういう意味ではやっぱコラボっていうのが正解っていうか。結局それなんだよね。でも、これアーティスト視点からの今の話になっちゃってるから、企業側からだよね。企業側からどういうふうに価値を高めれるかって話だから。
- 原
- それこそ企業側からは、逆に、案としてはどうでしょう?しか多分言えないと思うんだよね。こういうものがあるんですけど、これ何かアート性として、その方のアートとしての部分で見たときにどう見えますかっていうのを。表現で言うと、依頼するけどいただく感じに近いのかなと思うんだよね。
- 佐藤
- 必ずしも俺アートじゃなくてよくて、やっぱ参画してもらうのがいいのかなと思うんだよね。その今、プロジェクトならプロジェクトでいいし。単純にアート目線でどうですかじゃなくて、例えば、渡邉さんだったらこれどう考えますかの話だと思うんだ。その道着を着物にする話じゃないから、今の話って。道着をどう再解釈してやれるかの話じゃんね。着物を再解釈してるから、だからそこのプロセスを借りたいわけじゃんね。で、VEDUTAコラボで道着の再解釈の、だから着物のストリートだったけど、道着の今風の武道着なわけじゃん。だからその、渡邉さんだったらどう考えますかのところを要は求めとって、それで一緒に生まれるものがプロダクトのさっきの部分になってるから、の価値の部分じゃんね。
- 原
- なるほどな。エッセンスだ。そういう意味で言うと、考え方。
- 佐藤
- エッセンスっていうか、これも次回につながってくるけど、ちょっと脳の多様性の話なんだよね。特にアーティストっていうのは、今までもやっぱり経済とか社会からちょっと遠いところにあったぶんだけ、だって、渡邉さんですら、その着物のアートを作ってる中で、やっぱり商業とは遠い位置って言ってるぐらいなんだよね。でも本来俺的には近いよって、一緒だよって考えてるわけだから、俺、最初から。アーティファクトリーって名前をつけるぐらいだから。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- ***融合してやってんだけど。だからお互いにそういうふうに見てんだけど、でも実際は近いっていうか。で、一緒に考えたほうがいいんだよね、やっぱり。だからエッセンスってよりはそのプロセスの部分。遠いところにいるからこそ混ざり合うと新しいものが生まれるし。
- 原
- さっきエッセンスという話にしたんだけど、何かというと、核芯が違うものが入るはずなんですよ。それをイショクドウコン(?)するわけじゃなくって、違うものに作り変えるっていうところがアートなんだと思ってるんですね。でも、発信する力だったり拡散させる力自体にそこの部分を使うわけではなくて、それがどれだけ必要なものかっていうところに、逆に反転させた投げかけになるのかなっていうふうに思ったんですね。そのアートとビジネスがひっつくっていうことが。
- 佐藤
- アートとビジネスがひっつくってことは、根本的には視点が違い、視点を広げれるっていうことなんだよね、単純に。そこはまず大きいのよ。だって金にしようと思って作品作ってねえから、最初から。アーティストは。さっきも言ってたけど。だからお金っていう要件がなくなるわけよ。マネタイズするって要件がなくなるから、そうしたら次に何を考えるかの話よ。次、何を考えます?
- 渡邉
- 哲学。
- 佐藤
- 哲学だよね。哲学だとか時代背景だとか、そういうことを考えていくじゃん。社会に伝えたいことだとか。でもこれが今、実はビジネスのシーンで求められてることじゃん。SDGsとかエシカル、ESG、ウェルビーイング、ウェルネスとか。全部だからこれアート思考、アートの話なわけ。もうお金じゃないよの話になってきてるんだよ。だからアーティストの話なのよ。だから要は売れることを先行して考えてるとか、それは経済活動として正しいんだけど。じゃあ芸術はとかの領域に入ってくると、要は概念だとか想像をかたちにしてるだけの話だから、そこに対して。だからそれが今求められている社会の背景にあるよっていう、在り方さえもっていう話なんだよね。
- 村上
- 在り方ですね。
- 渡邉
- 売れることを考えて出したものって、もうあるんすよね、世の中に。
- 佐藤
- そう。だから経済が成熟化してるから、もうあるんですよ。
- 渡邉
- だから割に合わないものほどチャンスがあるっていうのはそういうことで、誰もが手つけてない、すごいコストかかると思われてたり、こんなもん売れねえだろっていうところに実は面白い、今の世の中にない考え方とかアートがあるんですよね。
- 佐藤
- だから俺思うけど、もうこれソリューションとして今思いついたけど、要は100年後200年後、これVUCA時代だからこそ、わかんないからこそ今、だから100年後200年後の世界をイマジネーションできれば、おのずとそこに対してマイルストーンを設定して、要は何をやっていけばいいかってできあがってくるじゃん。だから、企業ごとの100年後をアーティストに描いてもらって、それを事業プランに落とし込んでけばいいじゃんね。要はコンセプトアートよ。車でも商業デザインでも何かボトルでも、何でもプロダクト、プロトタイプ作るときってさ、虫から取ったりとかいろんなもの取るじゃん。大自然のものから取ったりとか、コンセプトとして。それをどうやって現実に実現できるかって、そのコンセプトに基づいて作っていくでしょ。そのまんまにはならないし。だからアーティストに自分の会社のことをヒアリングしてもらって、その100年後200年後、うちの会社はどうなってるべきなのか、どういうビジョンに見えるのみたいな、ってのを描いてくれって、コンセプトビジョンを作ってもらうってのがいいよね、アーティストに。それが企業価値を高めることにつながっていくんじゃないでしょうか。あれ?もう終わっちゃったよ、番組(笑)。
- 一同
- (笑)
- 井戸
- 書いてね。お願いします。
- 佐藤
- OK。
- 井戸
- はい。お願いします。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- じゃあいきます。本日のソリューション、こちらです。未来を描くコンセプトビジョンを共創しよう。
- 原
- 共創、いいね。なるほどなと思ったよ。
- 佐藤
- いいよね。夢もあるし。VUCAにとらわれんでいいし。
- 原
- そうだね。困ってるじゃないね。何か作っていくって、作り上げようっていう、見えてるとこ作り上げようみたいな感じだからいいな。
- 佐藤
- そう。だからコンセプトビジョンだから、そこにお金の概念もないし。要はどういう暮らしの在り方とか、どういうことを社会に貢献していくのかとか、どういう会社の社内のあれになってるかとか。非常にこのアーティスティックな部分の、この抽象的な部分でもかたちにしてもらう、アーティストの仕事。そしたらこれ、だって会社もいっぱいあるんだから中小企業からでも。アーティストたちにどんどんコンセプトビジョンを作ってもらって、それがSDGsだとかにもつながってくるし、ESGとかにもつながってくるし。それがいろんなかたちで表現できてもいいよね。絵であってもいいし、音楽であってもいいし、それが共創体でもいいわけだからさ。
- 村上
- 何かわくわくする感じですね。
- 佐藤
- 展示会にしてもいいんだもんね。絵とかそういうの、わあっと作ってって世界観作って、アートリーワールドみたいな、アートリー美術館みたいな。
- 一同
- (笑)
- 久田
- 館長やらなきゃ。
- 佐藤
- っていう感じです。ありがとうございます。
- 井戸
- ありがとうございます。
- 原
- 面白い回だね。
- 佐藤
- 面白い回だったね。
- 原
- すっげえわくわくした。
- 村上
- わくわくします。
- 佐藤
- わくわくした(笑)。何か経産省もこういうことやってるから、だんだん。だけどアーティストの方たちもやっぱり、だからやっていけれる世の中になるといいなと思うけどね、インフラが。だから、結局切り開いてこなきゃいけなかったから、今までの時代って。俺もだってそういうな環境があるんだったら、多分そこに従事してやってたもんね。絵なのか音楽なのか、何なのかわかんないけど。だけどそれじゃ食ってけれんもんで、で、勤めにいってもくびになるし、すぐ。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- バイトとかでもくびになるから。もう自分でやるしかねえみたいな感じで無理くりやってきてる感じだから。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- そりゃあいいよね。そんな世の中だったら。
- 原
- 確かに、そうだね。
- 佐藤
- だから渡邉さんだって大変だと思うよ。自分のやりたいことと商業的なことと、はざまで生きてるじゃん、アーティストたちって。
- 渡邉
- そのほうが、でもやりがいありますよね。こうして、学校の先生になってれば食えてけるしとかあるけど、見えちゃうからつまんないですよね。だからそこに、見えないからこそ予測不能なものに目指して一生をかけたほうがおもろいなみたいなところのロマンですかね。
- 佐藤
- そうだと思うよ。だってアーティストなんて自分の人生をアートだと思っとる。作品だと思っとるから(笑)。
- 渡邉
- 自分が勝手に映画になると思ってます。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- ありがとうございました。
- 井戸
- ありがとうございました。来週以降の放送はこちらのとおりとなっています。次回も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また来週もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
【アートと経済】アートと経済の融合がもたらす企業革命!「アートと経済」総集編
2024.08.22 放送分
デジタル⽥園都市国家構想に補助⾦の追い⾵!地⽅創⽣に取り組んで新たなビジネスチャンスを掴むには
2023.12.14 放送分
サーキュラーエコノミーの未来を担うZ世代!新しい消費パターンを取り⼊れてビジネスを成⻑させるには
2023.11.30 放送分
夜の経済にイノベーションを!ナイトタイムエコノミーを再解釈してチャンスを掴むには
2023.10.26 放送分