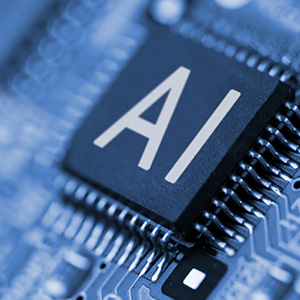2023.12.14 放送分
デジタル⽥園都市国家構想に補助⾦の追い⾵!地⽅創⽣に取り組んで新たなビジネスチャンスを掴むには
第163回アートリーアカデミア
THEME
デジタル⽥園都市国家構想に補助⾦の追い⾵!地⽅創⽣に取り組んで新たなビジネスチャンスを掴むには
テクノロジーと持続可能性の融合に焦点を当て、農業、エコシステム、デジタルイノベーションに関連するビジネス機会を探ります。この構想が社会や経済に与える影響と、それを活用する戦略とは何か。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、始まりました、アートリーアカデミア。
- 井戸
- 本日のテーマは、「デジタル田園都市国家構想に補助金の追い風!地方創生に取り組んで新たなビジネスチャンスを掴むには」。さっそくフリップを見ていきましょう。デジタル田園都市国家構想とは。新しい資本主義の重要な柱の一つで、デジタル技術の活用により、地域の個性を生かしながら、地方の社会課題を解決する取り組みをいいます。デジタルの力を活用した地方の社会課題解決に対して、構想を支えるハード、ソフトのデジタル基盤整備。デジタル人材の育成、確保。誰一人取り残されないための取り組みといったものが挙げられています。
- 佐藤
- このデジタル田園都市国家構想って過去にもアカデミアでやったことあるんですけど、そっからだいぶ進展して、今、補助金が出てたりだとか、実際に取り組んでる自治体も結構多いんですよね。これそもそも何なのかっていうと、これ現内閣、岸田内閣が掲げてる新しい資本主義っていう大きなビジョンの中で、このデジタル田園都市国家構想。要は地域、地方と東京との格差なくしていくっていうか、人口減少の問題とかがあるから、そういったところを、要はITの基盤とかを作っていって、全都道府県全体でこういうITのライフスタイルがもっと豊かになれるようにしていくよっていう、一応構想になっているというかたちですね。次のフリップ見ていきましょうか。
- 井戸
- 背景と目的です。人口減少、少子高齢化。都会と地方都市の格差。東京圏への転入超過といった背景がありまして、ウェルビーイングやサステナビリティを実現し、国内のどこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会へすることが目的となっています。
- 佐藤
- 田園都市国家構想の背景っていうところですね。地方の人口減少、少子高齢化、これが一番の問題。働く場所がないしみたいな、っていうところがあるから都心に出るしみたいな、これが東京圏への転入超過しているよっていう。人が集まるってるところと人がいないところじゃやっぱりその行政のサービスとかも違うし、そういったところをデジタル田園都市国家構想っていう、補助金だとか使いながら自治体とかにまず公金を流していって、企業がそこに提案してってみたいな、で、よくしていくみたいなっていうようなイメージなんだよね。だから、これ実現すると地方のほうも人口拡大、だから、すなわち東京に一点集中しているものが解消されていくっていう、人はだから分散、今ワーケーションだとかリモートワークとかも積極的に取り入れられてるんで、そういったところも目標値にあると思うんですけど。で、伴って都市に匹敵する情報やサービス、どこまでやれるのかって正直あると思うんだけど、でも一応目指してるところとしては、国内のどこでも誰でも便利で快適に暮らせるよっていう社会を目指していくっていう。じゃあ、次のフリップも見ていきましょうか。
- 井戸
- デジタル田園都市国家構想推進交付金。デジタル化を活用した地域の課題解決や魅力向上に向けて、以下の事業の立ち上げに必要な経費を単年度に限り支援してくれるそうです。
- 佐藤
- これはタイプ1、2、3で分かれてて、それぞれやる難易度、1ってのが要はよそ事例を持ち込んだ場合で、2ってのはデータ連携基盤、オープンソース化ってかオープンデータ、データをオープン化していってどんどん地域投資へのプラットフォームを強化していくよってイメージで、3がマイナンバーを活用した、タイプ2に加えてさらにマイナンバーの活用方法みたいなってところで、それぞれ6億、2億、1億っていうところで。なんで、補助金としては、3分の2だから4億出る、1億出る、5000万出るみたいな、っていう感じにはなっていますと。だからここで結構企業とかがそこに自治体の取り組みにどんどん提案してくことによって、売り上げなども向上したりだとか、認知度を高めていくっていうこととかもできるのかなっていう。これ、先生どう思いますか。
- 原
- これ、それこそタイプ1ってもう既に、既存にあるものを横展開する話なので、いろんな企業が、企業のレベル感はあるかもしれないけど、どんどん展開させやすい話だから、それで1億までの上限あるって、結構提案しやすい内容なのかなっていうふうには思うんですけどね。
- 佐藤
- そうだね。さっき3分の2補助で4億っつったけど、そうか、3分の2補助で6億までってことだよね。ってことは、9億のプロジェクトに対してってことか。
- 久田
- そういうことか、なるほど。
- 佐藤
- そうだよね。失礼しました。だから9億のプロジェクトに対して6億円補助してくれるよって話で。
- 久田
- 1プロジェクトってこと?めっちゃ出るじゃん。
- 佐藤
- だけどこれ、何か限度があるんだよね。1億のやつやっちゃったら、申請上限数は上記タイプの合算値っていうことになってるから。で、都道府県が9事業、市町村で5事業だから。
- 原
- 限られてくるか。
- 佐藤
- そう。だから県全体で言うと9事業しかやれない。市町村の事業としても5がマックスとかだから。
- 久田
- 1、2、3、全部それぞれ足して。
- 原
- 足してだもんね。
- 井戸
- 少ないね。でも、そんなぽんぽん出るものでもないか。
- 佐藤
- だからなるべく全事業やってこうと思うと、全部タイプ3でやったほうが国費としては出るから。
- 久田
- 出るけど、そんなタイプ3やれるような事業者そんなにない(笑)。
- 佐藤
- そうだね。でも、マックスでこれ9事業やって6億やったとしたら54億出るから、1県に対して。
- 原
- すごいよね。
- 久田
- めっちゃ進みますね。
- 佐藤
- そう。だけどこれ全部タイプ1でいっちゃった場合9億しか出んから。でも9億使ったとしても2分の1補助だから一応18億のプロジェクトにはなるよね。これも3分の2だから9か。9×9で81億円マックスで予算としてはある状況だよね。
- 原
- それでもすごいな。
- 佐藤
- でもこれタイプ3とかもタイプ2も5カ年のプロジェクトになってくるから。だから初年度に限り支援だから、単年度に限り。
- 久田
- あとはもう自治体側で出せよってことですね。
- 佐藤
- そう。だからイニシャルの部分で要はランニングの部分だとか運用費の部分とかもこっそりインクルードでやってねみたいなのは出やすい話かなってのはある。見方を変えると5年間でっていうふうにもなるから。
- 原
- これ、読んでて思ったのが、要はそのあとのずっと継続する部分、その5年以降の話、タイプ3の場合でもね。その部分に関しては各自治体でやりなさいよっていうスタンスだから、継続性もやっぱり全体的に絶対必要なのかなっていう。
- 佐藤
- 必要。5カ年でって、で、初年度しか出さないけど、でもそれに対して実施報告とかもしないといけないから。だから当然その成果は出せなきゃいけないから、ある程度。
- 原
- そうだよね。だからPDCAの成果っていうところはどうしても、それも報告としては必要になってくるよね。
- 佐藤
- そうじゃない?これ、七菜子もさっき言ってたけど、別にそんな大したことやってないんだよね?
- 久田
- そう。タイプ1の事例を結構見てたんですけど、本当にデータ入力のデジタル化とか、あと、今コンビニとかで出力できたりするじゃないですか、住民票、あの辺とか。結構メタバース使ったりとか面白そうなことやってる自治体もあるけど、都道府県レベルとかまでいくと面白そうなことやり始めてたりはするけど、市区町村レベルで言うとまだデジタル田園都市国家構想っていうレベルってよりは、本当IT化って感じ。
- 佐藤
- そうだよね。これ、俺、この間、コンペに参加したんだよね、この案件。ある都道府県の。そのときやっぱ、それメタバースの案件なんだけど、データ連携基盤ってやつがあって、県ごとにっていうか。で、それが別に内容そんな大したもんじゃないんだけど、それとの連携性だとかそういったところが結局重要視されるんだよね。あと言い方あれだけど、仕込みで要はもう提案してるもの、基本的には提案があって、そのベースをこの国家構想として申請するから、それで公金が出るよってなったタイミングでコンペみたいなかたちになるんだよね。だけど最初にその仕込みっていうか、最初から提案してるところがやっぱ圧倒的に有利じゃん。当然まくったりもできるらしいんだけど、やっぱり有利。
- 久田
- 採点基準作りにいってますもんね。
- 佐藤
- そう。要は基準を作りにいっとるじゃん。予算はだからここはこう、出した見積もりに対しての予算がつくし、だから、よそはそれより安くやらないといけないし、当然。安くやらないといけないってか安くやったほうが点数は高いし。
- 久田
- A社さんはこういう仕様でやるって言ってます、それを満たしてほしいんだけどB社さんはどう?っていう話になるってことですか。
- 佐藤
- そういうこと。だから全部採点基準もあるんだ。何点何点みたいな。そこに対しての点数をチェックされていくから。要件も、いつリリースしてこういうふうだとか全部決まってるから、もうスケジュールが。
- 原
- そうなの?
- 佐藤
- そう。もう決まってんだよね、だから。こういうプロジェクトやってくから、何か納品がいつとか、コンペがいつとかで、そんなもう1年前から仕込んでるようなところ、最初からもうやってけれるじゃん。もちろんそれ、おじゃんになったらそれ無駄になっちゃうからあれだけど。
- 久田
- そういうことか。だからまくられる可能性も逆に言ったらあるってことだもんね。
- 佐藤
- あるから。でもその辺はバランスなんだよね。言ってたけど、採択しんかったら、そのまくる側、そしたら結局誰ももう出来レースじゃんつって参加しんくなっちゃうから、ある程度そういうことはやるけど、でも多分前提的にはもう、何ていうの、自治体側もだって一緒に1年間話し合いしてたところとやったほうが安パイじゃん。いきなりコンペで金額だけでとかああいうので、ぴゅって選んで、
- 久田
- 怖くてしょうがない(笑)。
- 佐藤
- 怖いじゃん。
- 原
- 前提条件見えんもんね。
- 佐藤
- そう。だからよほどかっちりしてどんっていかんとやっぱ厳しいんじゃないかなみたいな。逆に言うと、だから提案を持ちかけにいく、だから結局その行政の誰と話をするかっていうか、パイプが重要なのかなってのはあるよね。額が額だからね。だし、結局基盤的な話の部分をやってくれの話だからさ。
- 原
- だから県なり市区町村からすると、基盤というか、インフラのベースに入り込む、業者を入り込ませる感じのイメージになるわけでしょ?
- 佐藤
- そうなるよね。
- 原
- そういう話になるんだよね。そりゃ選ぶわね、ある程度ね。
- 佐藤
- うん。だから、それでもタイプ2、3の話が強いっていうか、やっぱタイプ1って簡単っていうか、さっき七菜子も言ってたけど、データ入力をどうたらこうたら、よそでやってるやつの模範的な部分だから。これ、先生どう思います?1、2、3。
- 原
- これ難易度の違いがそのまま金額に表れているとは思うんですけど、本来でも市区町村が、各自治体が求めてるのってマイナンバーのひもづけなんだろうなっていうのは大前提では思ってて。
- 佐藤
- これ要件として出てきたのは今年度からなんだよね。初年度はこれマイナンバーの話なかったんだ。
- 原
- そうなんです?
- 佐藤
- そう。途中からこれマイナンバーの活用を盛り込めみたいな感じになったんだ。
- 原
- それ、だから内閣府のほうから出てるって話なんだ。
- 佐藤
- 新しかった。これ調べてる中で、マイナンバーのところの要件は後出しだった。
- 原
- じゃあタイプ2までが前の要件?
- 佐藤
- いや、タイプ3もあったんだよね。
- 原
- マイナンバーとしての表記いかんだったのがっていうことですか。
- 佐藤
- マイナンバーが要件にあったのは3。3として要件になったのは最近だね。
- 原
- そういうことですね。
- 久田
- じゃあ、もともとは多分新規性の高い取り組みとかだったってことですよね。
- 佐藤
- そうだね。どっちかというと連携基盤の強化の部分のほうが強かったんじゃないかな。
- 原
- だからなおさらか。
- 佐藤
- これ、奈津美さんどうですか。これやってて地方は豊かになりますか。
- 村上
- 地方こういうのが、私の主観的な考え、感じですけど、進んでないから、ブルーオーシャンですよね。どんどん開拓が、企業側からとってみればどんどん出ていくチャンスだというふうに思うんですよね。
- 佐藤
- でも9事業しかないもん。各県にね。
- 村上
- そうですよね、すごく狭い。狭き門。
- 久田
- 47都道府県だっけ。
- 佐藤
- だけど考え方によっちゃあ、自治体がそういうふうになります、特に過疎ってる地域、地方は、こういう新しい取り組みやって、地方の新たなビジネスモデルの創出だとかにつながってく可能性はあるよね。アイデアの創出っていうかさ。例えばその愛知県の春日井市だったら無人のバスみたいなのが走ってんでしょ?だからそのバスが無人で走ってるってわかれば、企業側も無人でバスをこうやって走らせれるんだったら俺らも何か無人でやれないの?これ、とかさ。
- 村上
- 1個突破口が開けるとそこから、この補助金が得る得られないが別として、突破口は開けますよね。
- 佐藤
- それ体験する人たちがまたいたときにさ、じゃあこれって便利なんだなってふうになれば、じゃあ普通に民間同士でそういうビジネスモデルを作ったりとかして、結局新しいビジネスチャンスに向けて、何か明るくなる可能性はあるのかなっていうふうには取れるよね。一回次のフリップ見ていきましょうか。
- 井戸
- はい。実現に向けた目標値です。デジタル実装に取り組む地方公共団体を2024年度までに1000団体、2027年度までに1500団体となるよう目指しているそうです。
- 佐藤
- これ、先生どういう意味なんだ?結局、田園都市国家構想としてはってことなんだよね。
- 原
- そうだと。
- 佐藤
- 今のこの公金の話じゃなくて。
- 原
- じゃなくて。なんで、今がそこまで、だから、その田園都市国家構想に乗っかってない団体がそんだけいっぱいあるってことだから、それを促すために目標値を出してるっていう話だよね。
- 佐藤
- そうするとじゃあ、これ今は9事業とかやってるけど、これ、また第1段の可能性あるってこと?
- 原
- あると思うよ。
- 佐藤
- うまくいったらもっとお金出してくよっていう話だね。
- 原
- そう。だって、1500団体って普通に考えたら少ないでしょ。
- 佐藤
- そうだね。
- 原
- 全部じゃないもんね。
- 佐藤
- どれぐらいあんの?日本に。
- 久田
- だって新たなモビリティサービスを行う地方公共団体70%、約3万5000事業者って書いてある。めちゃおる。
- 原
- めちゃめちゃある。だから追加はしていかないと。多分、促進はさせにくいんじゃないかな。
- 久田
- だんだんお金減ってきそうだよ。
- 佐藤
- でも、その下の子ども家庭センターが1740市区町村って書いてあるんだね。それで全国展開目指すだから、1700団体ぐらいか、全部で。日本全国で言うと。そうすると2027年度までにかなりのカバーをしにいくってイメージだよね。あとこれ、ただこれデジタル実装っつってるけど、どこまでがデジタル実装なのか。さっき言ってたデータ入力がどうとか、コンビニで住民票取れるとかそんなレベルの話してたらさ。別にLoppiでチケット買えるようになったぐらいの話だよね。じゃあそれって、果たして本当にDXって呼べるの?デジタル田園都市って呼べるの?って話になりやすいよね。
- 原
- ただ単に、お金のばらまきにもならないようにはしなきゃいけないはずなんだよね。
- 佐藤
- それこそ会場とか体育館をメタバースのサテライト観戦のライブビューイングみたいなとか、一応わからんけど、じゃあそこに集まって何か擬似的に東京ドームに参加できるとかさ、ってなってくりゃ、例えば工業目線とかでも、それって本当、どこでも誰でも質の高いとか、体験ができるみたいな、ちょっと言ってても、おおーみたいな感じはあるもんね。Loppiレベルだとどうなのかなって話はあるよね。
- 原
- それでじゃあ1億円使いましたって、2億円使いました、見えてる範疇になっちゃうから。
- 佐藤
- そうだね。これ光ファイバーの世帯カバー率、これはもう高いんじゃないかな、99.9%。5Gまだ使えんところも多いしあれだけど。サテライトオフィス、これは結構あれだもんね、1200団体。この間、鳥取県に行ったときも結構立派なサテライトオフィスとかワーケーション施設があったりだとか。砂丘の目の前にあったりとかしてた。サンドボックスとかいってさ。
- 井戸
- あれ?聞いたことある。
- 久田
- しゃれてんな。
- 佐藤
- サンドボックスってシステム開発のときに、研究みたいな感じの、テスト実施する単語なんだけど。大体サンドボックスっていうんだけど。砂場みたいな、いろいろ実験してできるイメージ。砂丘の目の前にそういうのがあって。
- 原
- かけてんのね。
- 久田
- サンドでかけてる、しゃれてる。
- 佐藤
- サンドボックスとかいうのあったけど。ああいうイメージだね。で、物流DX、これも2024年問題か。ドライバーが、労働基準法の改正で長距離運転できなくなっていくから。これ、すなわち自動運転のほうだよね、イメージ的には。あとギガスクールだとか、ギガスクールは100%って言っとるもんね。この重要施策分野ってところでやっぱ子ども政策部分と教育DX、観光DX、ここはそうだよねと思った。で、テレワーク。子ども政策で、あと地域交付のリデザインと遠隔医療か。だから結構ライフラインの部分だよね。ここら辺がちょっと変わってくれば、確かに変わるようなイメージはあるけどね。これ、何が懸念されますか、先生。
- 原
- これ、まず目標値としては在り方は大事だとは思うんですけど、結局地方に人を流入させることをやっぱりさせていかないと、結果的にはデジタルだけの話になっちゃうと思うので、要は税収が深まる、まあ増やせる要素も併せて考えないといけないと思うんですね。つまり職場だったり労働環境、言ってみれば人が集まる、あるいはお金が集まる要素をこの自治体ごとで作っていくことも併せてでやっていかないと、ただ単なる形骸化になってしまうっていうところが私は懸念事項かなとは思うんですけどね。
- 佐藤
- どっちに転ぶと思う?
- 原
- 形骸化。
- 佐藤
- (笑)
- 原
- だって人が簡単にじゃあ、だってサテライトオフィスだったりテレワークベースは進めやすいと思うけど、じゃあそこでお金落としてるわけじゃないじゃない、結局はさ。だからそれは住むだけの空間なのかなになっちゃうからさ。
- 佐藤
- でもスタートアップとかも増やしてくこと狙ってんじゃない?そういったところは。
- 原
- 狙ってるのは書いてあったよね。でもそれって収益が生まれる場所じゃないとだめじゃない、スタートアップの場所ってさ。人工数増やさないといけないし。
- 佐藤
- そもそも今日のニュースも見たけど、ユニコーンをたくさん作りたいとかそんなようなこと言ってたしね、首相が。掲げてることはすごく、われわれ特にIT分野の人たちになじみやすい言葉ばっかり言ってくれるからすげえいいんだけど、誰一人取り残されないものっていうのはやっぱ実現していこうと思うと、まあ、公金はありつつも、やっぱり企業としてはちょっと違う視点で見てかなあかんよね。公金があるから動くんじゃなくて、今そういう流れだから、自治体は結構そこ熱気がある状態だから。
- 原
- やりたいもんね。
- 佐藤
- そう。自治体に提案するのももちろん一つかもしれないけど、その公金ありきの話になりやすいし、予算がないしとかなりやすいから。だからやっぱり、ちょっとこういうもので、左になったものに対して企業はどう仕掛けていけるか、意識が変わっていくから住民のっていうところを乗っかるし、あとは便乗するしみたいな。どこまでチャンスが作れるのかなっていうところなのかなっていう感じだね、ポイントとしては。本当に形骸化しちゃうから、結局これ自体は。ムーヴメントさえできてれば意味があることになるから。
- 原
- そうだね。継続性が出てくるからね、そうすると。一発屋で終わっちゃう可能性がある内容はちょっとなとは思っちゃうけど。
- 佐藤
- 今だったらこの御旗を揚げれるから。要は行政が、やってくよみたいな感じで旗揚げてる状態だからさ。大義名分でそれやってきますよって言ったら、社会的には進んでるなっていう見せ方はできるよ。一回じゃあ本日のアジェンダ見ていきましょうか。
- 井戸
- はい。「デジタル田園都市国家構想に補助金の追い風!地方創生に取り組んで新たなビジネスチャンスを掴むには」。
- 佐藤
- これ、従来の地方創生ってどういうイメージがあったんだろうね。どういうことをやってたんだろうね。なっちゃんとかどう?
- 村上
- 例えば子育て世代が移住すると、そこでお子さんの費用とかがかなり優遇されるよとか、ほぼ実質費用負担ゼロで子育てができるよみたいな、そういう移住施策が多かったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
- 佐藤
- なかなか鋭いとこ突くね。結構言われるのが関係人口っていうのを言われるんだよね、関係人口を増やしていくみたいな。
- 原
- 関係人口っていうのは?
- 佐藤
- 要は県に関係する人たち、出てっちゃった人たちとか上京した人とか、ああいうのも関係人口になんだね。関係人口を例えば取り戻すもそうだし、多分ステップ的に関係人口を増やしていって要は移住の人たちを増やしていって税収を取るっていう多分感じたと思うのね。先生さっき言ってたように、税収がキーになるよっつってたじゃん。要は回収のスタンスの部分で。多分それはそういう話なんだよね。だから、結局でも移住するってなると仕事の話になるから、だから結局そこの企業が進出する部分のところで補助金出すよとかそういう話なわけでしょ。で、ここにきてソサイエティー5.0だとかスマートシティ構想だとか、そういったところになってきてるっていうことなんだよね。そこにどういうビジネスチャンスがあるのかっていうことか。
- 原
- そうだね。
- 佐藤
- 公金に参加できりゃある程度お金も入ってくるだろうけど。
- 久田
- 単純にチャンスだと思ったらいっぱい提案して、だませそうな地方自治体を狙っていけばって話。
- 原
- (笑)
- 佐藤
- どんどんね。だけど上限があるから結局、9事業。結局自治体も慎重になるよね、何のあれをするのかみたいなさ。なるべく多くお金もらって使いたいっていうのがあるはずだから。
- 原
- しかも内閣府のほうで言ってたやつは、これ一応、精査が結構ハードルがあるって言ってた。
- 久田
- 自治体のの一存ではないんのか。採択するかどうかも一回チェック入るんだ。
- 佐藤
- 国の事業のあれでとかいって、いくつかプロジェクト、メタバースのやつでもあったじゃん。あれってこれだったかもしれんね。
- 久田
- あり得ますね。
- 佐藤
- 結局採択されんかったからだめだったみたいなさ。自治体エキスポに出るっていうのが答えじゃね?
- 久田
- でも、本当そうっすわ。
- 佐藤
- (笑)
- 久田
- 結局その最初のコンペの話じゃないけど、どこの部署とどのコネクション作れるかどうかの、そこは企業もそうだけど、大企業も。結局、夢見る平社員としゃべっとっても何も進まんしコネクションも何もないし、じゃあこれでコンペ持っていきましょうもならんやん。できたらいいですねとか。
- 井戸
- 夢見る平社員(笑)。
- 久田
- コンペに持ってける立場の人と話ができて、まずそこじゃん。
- 佐藤
- だね。そこだと思う、結局。だからもう展示会に出ようぜ。
- 原
- そういうことか。
- 佐藤
- (笑)。だから自治体が一番活性化してるわけじゃん、要はね。彼らが、主語が自治体になってるから、結局この話ってどこまでいっても。だったら自治体の人と、今の話だね、接点作れば必然的にビジネスチャンスが生まれやすいんじゃない?って。
- 久田
- あと自治体の悩みって、言ったらあれだけどほとんど一緒じゃないですか。
- 佐藤
- 一緒だと思う。
- 久田
- だから1個ケース作っちゃったらまじで横展できるんだよね。それがうまみかなと思う、企業としては。
- 佐藤
- じゃあ一回ソリューション書いてみましょうか。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- はい。じゃあ、本日のソリューションこちらです。
- 佐藤
- 展示会に出よう。
- 井戸
- シンプル。
- 佐藤
- もうこれしかない。
- 久田
- 出たらいい。
- 佐藤
- やっぱり接点作って、自治体の人と接点を作って仕込むしかないと思う。
- 原
- こっちで出来レース作るしかねえっつって。
- 佐藤
- お金はあるからね。そんな感じかな。
- 井戸
- はい。ありがとうございます。
- 原
- お金は出るんだけどっていうところだね。
- 佐藤
- やる人はね。でも、何においても多分行政のこういう施策って多分左の部分だけでしょ、結局は。結局経済ってか、ビジネスマンたちが多分動かんと広がっていかないから。興味のある方はお調べくださいということで。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
【アートと経済】アートと経済の融合がもたらす企業革命!「アートと経済」総集編
2024.08.22 放送分
サーキュラーエコノミーの未来を担うZ世代!新しい消費パターンを取り⼊れてビジネスを成⻑させるには
2023.11.30 放送分
アートがビジネスを発展させる?アートと経済社会について考えて企業価値を高めるには
2023.11.16 放送分
夜の経済にイノベーションを!ナイトタイムエコノミーを再解釈してチャンスを掴むには
2023.10.26 放送分