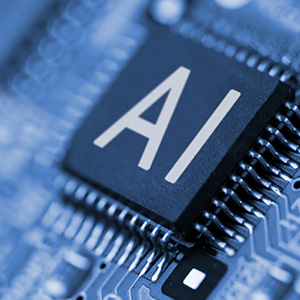2024.01.04 放送分
アテンションエコノミーからの脱却!注⽬の競争を超えて、持続可能なビジネスを築くには
第166回アートリーアカデミア
THEME
アテンションエコノミーからの脱却!注⽬の競争を超えて、持続可能なビジネスを築くには
注目を集める戦略から脱却し、信頼に基づくビジネスを展開する方法について議論します。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、今回のアートリーアカデミアは。
- 井戸
- 「アテンションエコノミーからの脱却!注目の競争を超えて、持続可能なビジネスを築くには」。アテンションエコノミーとは関心経済、注意経済と呼ばれており、注目や関心を経済的な価値に変える経済システムのことを指します。SNSのタイムラインや広告、ニュース、コンテンツ配信などが挙げられており、インターネットやSNSの普及により注目を集めることに企業や個人が重点を置くようになっています。
- 佐藤
- アテンションエコノミー、注意の経済。それがそもそも経済になってんだみたいな。
- 原
- そこだけが商いみたいなことができる状況になってるからっていう解釈ですよね。
- 佐藤
- なので、実際に企業にとっても個人の方にとっても、プラットフォームからお金をもらったりだとか、コンテンツを、要は注目だとか再生回数だとか、そういったものでお金になるっていうことの事実もあるし、ニュースですら注意を引くようなキャッチコピーとかね。やっぱりアクセス数を取ってみたいな。結局、何でこういう構造になってるかっていうと、そもそもアクセス数が取れるってことは広告媒体としての価値が上がるっていうことなんで、だからメディア側っていうのは気を引くような自分の自社のサイトだとか、自社のコンテンツに引っ張ってくるような施策をばんばん取るし、マーケティング的に考えると、ユーザーにとっての一日の時間をどれだけ取り合えるかみたいなっていうところがすごいポイントになって、そこでアクセス数っていうものに還元していって、それが広告になっていって、それが収益になっているっていう。こういうシステムになってるから、変な話、くだらないニュースだとか、それこそ何年も前のニュースとか、見てたら、ええ?みたいな、5年前の記事じゃんって。コロナの頃の情報で釣られたとかさ、そういうこともあったりするじゃないですか。そういうようなカオスな状況になってるっていうってことがあります。アテンションエコノミーっていうところで、企業にとってもどんどん競争が激しくなってきてっていうところがあるので、アテンションエコノミーの課題っていうところが次のフリップになります。
- 井戸
- アテンションエコノミーの課題です。競争が激化し注目を集めるためのコストが増大していることから、持続可能なビジネスの構築が困難になっているといわれています。消費者の注意が限られた資源であり、過剰な広告や情報過多が消費者の疲弊を招く可能性もあるといわれています。
- 佐藤
- 先ほど言ったんですけど、消費者の注意っていうのが、要は資源っていうかたちになっちゃってるんですね、経済の中で。だからそういった意味で実際、もう情報が氾濫してんだよね。その中でユーザーもだんだん麻痺してきてるから、だから、どんどんどんどん過激になって過剰になっていくような状況で、そもそもこの世は持続可能なビジネスっていうところで考えていくと、ショットで注意を引いて売り上げにしていくってよりは、本質的な価値っていうものをちゃんと作っていかなきゃいけないし、逆にそういうところを作ってるところの企業さんってのは広告が下手。注意を集めるのが下手だったらものが売れないっていう状況なんだよね。だからこの世は経済自体が、要は、ユーザーにいいもの、社会にとっていいものっていうのが届きにくい状況になってる。注意力さえ高ければそれが売れていくっていうことなんですけど、毛受さん、どう思いますか。結構美容って分野なんかでも激しいじゃないですか。多分、競争は。
- 毛受
- 美容は本当にありますよね。過剰な関心があるからこそ、自分の悩みのワードが出てくると見に行って、それが大きい子、本当に注意引かれるとちょっと見ちゃうっていうところはあるかなと思うんですけれども、結局、中身たどっていって、何だこんなものかって思うと逆にイメージが悪くなって。だまされたまではいかないんですけれども、このパターンかみたいな、割とパターンもわかってきているので、このパターンで売ろうとしているね、もう買いたくないっていうのはあるかもしれないですね。自分がアテンションエコノミーを使ってないかといったら、それはないかなと思っていて、やっぱりインスタ、私だったらSNS発信する際に、よりキャッチーなワードをつけないとっていうところはあったりとか、あと、あおるではないですけども、みんなが悩んでるところ、ずばっと刺す言葉は何かなっていうのは、やっぱり常に考えますよね。
- 佐藤
- だから必ずしも注意を引くことが悪いことじゃないんですよね。
- 毛受
- やっぱりそこに中身がなくて本末転倒になってしまう、バズることだけが目的になってくるとこれからは無理なんじゃないかなっていうの思いますね。
- 佐藤
- そうですよね。結局は注意を集めないと、そもそもがネット上でマーケティングができないとか、広告でマーケティングできないっていうところで、やっぱりビジネスはすごい難しくなっているっていうところがあるのかなということですね。実際に毛受さん、ユーザーとしての気持ちもおっしゃっていただいたんですけど、実際にデータとして今持ってきてますので、次のフリップでやっていきましょう。
- 井戸
- はい。デジタル広告に対する意識調査です。デジタル広告を出稿する企業やブランドに対し、好感度が下がった経験について、何度もあるが29.5%、数回程度あるが38.9%、一度だけあるが6.3%、全くないが13.7%、わからないが11.6%ということで、あるという答えが7割を占めているというところです。右側が好感度が下がった原因について、表現が過剰だった、表示頻度が多い、信用性、信憑性が低かったといったものが挙げられています。
- 佐藤
- 先生、これはどう思いますか。
- 原
- それこそ毛受さんがおっしゃられたとおりなんですけど、中身がない、とりあえず注目だけっていうふうになってるので。それこそ一つのSNSの媒体見るだけで何回も何回も同じやつが出てきたりとかね。ぱっと見て、何これって思ったら本当にどうでもいいようなやつって結構あったりするけど、でも最初は見ちゃうんだよね、最初だけ。でも、またこれだと思うと消しちゃうんだよ、すぐ。
- 佐藤
- そうなんだよね。これ、本当に仕掛ける側としての、プロとして目線と、実際ユーザーとしてうざいなと思う両方の目線があるんだけど、結局、人って行動経済学上で言うと一貫性がないから、気持ちにおいて。で、それを狙っていくんだよね。だから、今、反応しなくても、次に反応するかもしれないし、ほかのことに意識を奪われてだったら、じゃあ、ほかの意識向いてないときにのタイミングでもう一回いったらいけんじゃねえかみたいな。
- 原
- それで回数が増えるの?
- 佐藤
- そう。これが対、人だったらあまりにも同じことをされたらうざいやつになるじゃん。だから結局一緒のことなんだけど、だけど対、人じゃなくてコンテンツでそれやってるから。で、無作為にやってるじゃん。だから気づかないんだよね。
- 原
- 出してるほうも。
- 佐藤
- 出してるほうとしては。
- 原
- 反応が見えてるわけじゃなくて、
- 佐藤
- 反応してくれる人だけいりゃいいやみたいな感じにやってる反面、だから、あいつなんか全然相手のこと考えてねえブランドだみたいなってきちゃってような感じもある。
- 原
- 出したい側が出したいもので、見せたいもので出していくから、温度感も見えんもんね、見る側はね。だから受け止め側のところが全然違う場合があるってことなんだね。
- 佐藤
- そういうことなんですね。でも、これ実際、こうやってどういうふうに思ってるのかってすごい重要で、それこそちょっと話変わっちゃうんだけど、メールマガジンとかもめちゃくちゃ注意引いてくるじゃん。で、うぜえなと思ったタイミングでこのメール配信停止をしたときにログインしてくださいっていうタイプが主流だったんだけど、最近はログインしなくてもそのままそのメールアドレスに対して停止できるブランドが増えてきてるじゃん。それは結局、メール配信サーバー側の意向とかもあったりするんだけど、大体がAmazonのAWSサーバーってやつを使ってて大量配信できるようになってるんだけど、メール自体は。Amazonのポリシーとしてユーザーにとってよくないから、そういう無作為のやつやめてくれっていうところもあるし、でも事実そうやってやってるところに関しては、やっぱりユーザーにとっても、気安く気軽に配信停止させてくれるって、逆にだからいいブランドみたいな感じに好感度が上がるっていうのがあるんですよね。
- 毛受
- いつまでもできないとかなると、ちょっと怖いとか、しつこいとか思うけど、逃げれば追うじゃないけど、あっさりそこやってくれたほうが好感度上がるかもしれないですよね。
- 佐藤
- だから注意経済、アテンションエコノミーっていわれながらでも、やっぱりそういうユーザーのエンゲージメントっていうものも事実存在してるから。これ、なっちゃん、好感度が下がった原因についてっていうところで、面白いものがあったりとか気になるやつあったりしますか。
- 村上
- 最近の話題でステマってあるじゃないですか。ステルスマーケティングっていって、影響力を利用して芸能人だとかインフルエンサーの方に、この商品いいよ、この化粧品いいよとか、このサービスよかったよとか発信させて、実は裏からその企業からお金をもらってる手法。それが今年の10月からそれも景品表示法違反だよっていうふうに取り締まられる対象になったんですね。これは消費者、ユーザー側の正しい情報を得てそこから合理的にちゃんと判断できるように、それができるようにっていうことで消費者目線で作られた法律で、実際の表示と異なる認識を与えるような、実際の中身ですね、商品サービスの中身とか金額と異なる捉えられ方をするような表示がだめですよっていう、そういう法律なんですけど、それにステマも含まれて禁止されるようになった。
- 佐藤
- もう法的にだめになった。
- 村上
- はい。罰金が課されるようになりましたっていう。
- 毛受
- それは両方に入るんですか。
- 村上
- 両方というのは?
- 毛受
- 罰金が企業とやってるインフルエンサー両方だめ。
- 村上
- 両方だめですよっていうところに。
- 佐藤
- 発注もだめだし、
- 村上
- そうです。受けるのもだめですよってことですね。
- 佐藤
- 法的にもそういうふうになってきてるってこと。これ見てて面白いなと思ったのは、広告のクオリティが低いからブランド対して好感度が下がっているっていう。内容に共感できなかったとか。でも必要以上の広告コストで価格が割高になってるっていう。だから見てるユーザーも賢いし。結局ジェネレーションの差もあって、TikTokとかインスタとかFacebookとか、それぞれ属性が違うんだよね。Facebookとかだったらビジネスマンが多いとか、TikTokだったらZ世代が多いとか。TikTokが出たときにすげえ面白いなと思ったのが、広告に対してコメントをするユーザーが多かったっていうか、それが衝撃だったんだ。
- 久田
- 広告にコメント入れるんですか。
- 佐藤
- そう、広告にコメント入れてスレッドみたいになっててんだよね。そこで会話になってんだよ。もうこの広告見たとか、広告がダサいとか、この広告はかっこいいとか。ローラかわいいとか、そういうのがあったりだとか(笑)。
- 村上
- 評価が一瞬にわかりますよね、広告出してる側としても。この広告受けるんだとか、これだめなんだなっていうマーケティングがそこでできちゃうっていうのがいいですよね。
- 佐藤
- だから結局広告もどんどんクリエイティブになってきて、注意を引くにしても、好感度が上がる注意の引き方が必要っていう話なんですよね。ただ単純に、何だろう?気になるとかじゃなくて、誰かが何々して事件になったとか、そういう引き方とかネガティブじゃん。でもネガティブなほうが反応しやすいんだよね、人って。簡単だからさ。クリエイティブなものを作って注意引こうと思うとそこに対して考えていかなきゃいけないから。
- 原
- コメントも変わってきますもんね。受け止め方のね。
- 佐藤
- そういうことが必要なんじゃないのかなっていうふうには思うんだよね。この好感度が下がった原因についてっていうところで言うと。ただ単純に頻度が多いとか、ばらまいてるからとかじゃなくて。メッセージの在り方が大切っていうことなんだよね、アテンションエコノミーの中って。
- 毛受
- 意識を引けなかったら広告する意味ないですもんね。まず意識を、注目浴びるために広告って打つわけだから、頻度も大事だし本当に言葉の使い方も大事なんですけども、そこにクオリティいうことが今すごく求められてるっていうことですよね。
- 佐藤
- 政治家の演説みたいな感じですかね、選挙活動みたいな。
- 村上
- あいつ口だけじゃんね、みたいなだと、すぐばれちゃうよ(笑)。
- 佐藤
- 最初だけ言ってるあれだし、みたいな。
- 原
- でも、選挙終わったあとにみんな忘れてるんだけど(笑)。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- そうだね。広告も、あれうざかったなあっていうのがあったとしても忘れちゃうから。
- 原
- 一時的にはなりやすいんだよね、どうしてもね。
- 佐藤
- そうですね。というわけで注意経済から脱却するにはっていう最後のフリップがあります。
- 井戸
- 注意経済から脱却するには、短期的な注目を集める戦略から長期的な顧客関係の構築へ、社会的責任を果たしブランド価値の醸成を目指すことが必要とされています。注目以外の価値を提供すること、顧客のニーズを深く理解すること、顧客との信頼関係を築くことといったことが挙げられています。
- 佐藤
- 注意経済から信頼経済じゃないけど、アフターサービスだとかもそうだし、さっき言ってたこのブランドイメージ、どう思われるのかっていうことが重要なんですね、その広告に対して。ただ関心を引いてクリックを集めるだけじゃなくて、そのあとユーザーが役に立った、この情報、みたいな感じで、注目からの先だね。注目の先の価値だよね。顧客体験価値を向上させるだとか顧客の悩み課題を解決する。あるじゃん、ネット上のコンテンツとかでも、情報としてはニキビの対応はこういうのがいいよとかさ。その先にはこのメディアは信頼できるってなって、その先に私たちがおすすめする商品はこういうものですみたいな。だったら、あっ、そうなんだみたいな。信頼度が高ければ買うわけじゃん。
- 毛受
- でも、もともとこれがないものって本当に商品じゃないですもん。商品、サービスではないじゃないですか。ここがあってこその、これを売るための注意をどうやって広告に出していくか、ここがまずすごく大事ですよね。もともと本当に、どちらかが先じゃないですけども、こっちが先だと私は思いますね。これがあって、私たちのサービスこうなんです、商品はこういう誰の悩みを解決するんですがあって、じゃあこれをみんなに知っていただくために埋もれないように、どういうふうにアテンションしていくかっていうことだから、それをわかっていないと、注目を浴びたはいいけど売り切りで終わりとか、定期で買わせるのをクリックさせて終わりとかになっちゃうと、やっぱりよくないんじゃないかなっていうのはありますよね。
- 佐藤
- だから毛受さん言ったように、本当に中身がないんだったら、ただクリックだけで広告型のメディアみたいな、それでも信頼が下がってくし。だけど、今言ったように、顧客のニーズを深く理解するっていうのは重要なんですよね。顧客がその広告に対してどう思ってるかっていうのと一緒で、会員にしてもらうような土台を作って、要は、なぜ会員になるのかっていったら、よりよいパーソナライズされた価値だとかサービスを提供しやすいようにですっていう話だし。それをすることによって、うざいなこの広告とか、うざいなこの訴求、メッセージとか、このコンテンツっていうのをなくしていく。そのユーザーとっていいものを知るためのベースを作っていくってのは重要なんじゃないのかなとは思いましたね。
- 原
- それこそアテンションって本来、注意とか関心っていう話の表現にはなってるんだけど、見せ方と中身っていうのが不一致だから、購買から離れるだったり、離脱率が高くなってるんだと思うんですよ。ここが本来の会社、企業側がどうやってお客さんとの本来のニーズを探っているのかっていうところを見せていく、それに向けてどういう取り組みをしているのかっていうのを広告でもっともっと出していくと、本当は訴求効果としてはそっちのほうが、自分たちに向いてるんだ、お客さんからすると、っていうような流れに本来になると思うんですよね。これが、この三つあるやつでどこまでいくかは、それぞれの会社の見せ方しだいだったり、データの取り方しだいだと思うんですね。
- 佐藤
- そうですね。ただ難しいのがさっきも言ったように、そのように時間の取り合いだから。競合は単純に直接的なライバル企業だけじゃないのよ。ゲーム、ニュースだとか動画サイトからテレビから、ありとあらゆるものなわけ。その中でどうやって勝ち取っていくかっていうところが今回のアジェンダになってきます。
TOPICS
テーマ討論
- 井戸
- 「アテンションエコノミーからの脱却!注目の競争を超えて、持続可能なビジネスを築くには」。
- 佐藤
- タイトルから既にソリューションを誘導して(笑)、
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- 価値を高めていきましょうとか、そういう話になっていきやすいんだけど、だけどアテンションエコノミーはなくならないから、多分。人の価値としてアテンション、注意っていうのは絶対なくならないじゃん。だって、もともとは危険予知だとかさ。本能的にだってそれを察知しないといけないわけだから、アテンションって。古くだと原始時代だとかああいう時代だったら、例えばコミュニティで生活してる中で誰々が病気になったとか、誰々が仲が悪いとか。そういうのは例えばヒエラルキーを作っていくうえですごい重要だったわけなんですね。学校とかでもそうじゃん。情報に対してゴシップネタだとか、そういうものってキャッチしとかないと、自分の社会的ポジショニングが優位に立てないとか危ぶまれるみたいな、そういうのが本能的にあるから。だからアテンションっていうのはなくならないんだよね、結局は。だから、なくならないことは前提として、どうやってそれを活用しながら持続可能なビジネスを築いていくのかっていう、今、既にいろんなアイデアが出たんだけど、七菜子さん、どうでしょう?
- 久田
- 私も最近ずっとECサイトを追いかけてて、毎日毎日見てたサイトがあったけど、アテンションが一気に切り替わって全然見なくなっちゃった。それが別の服屋に変わったわけじゃなくて、それがゲームに変わったりとかテレビに変わったりとか、市場をまたいで一気に注目っていうのの割合が変わっていくから、競合相手って、さっき丈亮さんもおっしゃったとおり、服屋だったら相手は服屋とかじゃもうなくて。そう考えると本当に取り合ってるな、世界でって思う。過激なのをやめないといけないね、ブランド価値は下がっていっちゃうから。一発の当たりみたいなのに頼ってっちゃうと。
- 村上
- 自分がどんなサービスを提供したいのか、何を売りたいのか、本質は何かっていうのをすごい土台固めしてから、その本質を突くようなキャッチーなものを、ぴってピックアップできるといいですよね。そうすると信頼も下がらない。で、それに誘引された人が土台部分、ちゃんと誘引された言葉どおりだっていうものが提供されると、信頼が上がって評価も上がるんじゃないかなとは。
- 原
- そこはこっちがでも醸成しないといけなくなっちゃう。例えば広告の媒体ベースで見たときに、そこって基準値って同じように持っていける?っていうところ、ありません?
- 村上
- 取る側がそういうふうに受け取ってこれるかっていうところですかね。
- 原
- そうそう。どうしても企業側からの目線でものを見てしまうんだけど、注意はさせていかないといけないし、このお客さんに刺さるけど、このお客さんに刺さらないって、だんだんわからなくなってきてると思うんですよ、企業側も。
- 村上
- そこは向こうからの反応。それこそTikTokですぐ反応がきて、会話が成り立つよっていうのを利用してキャッチアップしていって、発信していくといいんじゃないかな。双方向でどんな内容が注目を浴びるかっていうのができあがる、醸成していくといいんじゃないかなと思います。
- 毛受
- 企業もちゃんと再現性を見ていくってすごい大事だと思うんですよ。1回、2回じゃ、もう何回も何回もやって、この言葉だったらこういう結果が得られるっていう再現性をたくさん作っていかないと。それが例えば過激な言葉でもうまくいくんだったらいいじゃないですか。うちは過激派だみたいな(笑)。
- 一同
- (笑)
- 久田
- 過激が悪いわけではない。
- 毛受
- それが合ってたら、それを求めてるファンとお客さんいるんだったらよくて、すごく品がいい言葉を使ったほうがいいっていうのが合う企業もいるので、それって何回も何回も回していくっていうリスクがない、リソースがあるだけでやっていくっていうのが一番いいんじゃないかな。そうすると多分長期的なって考えると、以前やったファンが顧客になってくれるっていうファンビジネスにつながっていくんじゃないかな。ファンになってもらったらもっと注目したいと思ってるから、ファンの方が。もっと注目させるような施策を考えれるっていうのがいいじゃないかな。
- 佐藤
- いいですね。今、話を聞いてて思ったのは、端的に考えるんじゃなくて戦略的に考える必要があって、それが中長期のビジョンっていうか持続可能であるっていうことなんで、まず何がだめなのかっていうと、一発屋同士でばんばんばんばんエスカレートしてって、で、中身が伴ってないみたいな、っていうエコノミーが一番だめなんですよね、アテンションエコノミーが。
- 原
- 醸成もしにくいもんね。
- 佐藤
- そう。だからまず何が大切なのかっていうと、自社にあった対話っていうのは何なのか、自社のカラーとかブランディングにちゃんと無理がない、持続できるメッセージの対話の仕方なのかどうかっていう話だと思うんですよ。毛受さんおっしゃるように、企業もマーケティングで、その人の一人一人違うニーズにどうやって答えていくかってことが必要なんで。そこは多分、広告をポートフォリオ化していく必要があると思うんだよね。
- 久田
- どういうことですか。
- 原
- カテゴライズする感じ?
- 佐藤
- イメージ的に、例えばマーケティングを擬人化させて考えると、基本的にまずマーケティングって市場に対しての対話だと思うんだよね。継続的な対話がマーケティングだと思っていて、だから一発限りのメッセージの広告で終わりじゃないわけ。これはその人の、そういう話し方をした、じゃあこれからはこんなアイテムがくるぜみたいな、熱血系のような対話をしたとするじゃん、そのブランドが。それはそのブランドの一面でいいと思う。
- 井戸
- 伝えたい人に合わせて変える?
- 佐藤
- 変えるっていうか、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんっていうしゃべる人を用意しておくイメージ。ブランドアイデンティティは。だからアテンションエコノミーの中で広告を出していくにしても、誰がしゃべってるのかっていうブランドアイデンティティを用意していく必要があるのかなと思うわけ。それが1人だとしたら1人だし、資生堂みたいにプロダクトごとに変えていく。だから、この商品をZにもとか、高齢者向けとか年配の方とかわかんない、どの層にっていうふうに考えていくのも一つなんだけど、この理論で考えていくと、もう実践してると思うんだけど、多分先進的な企業って。プロダクトごとに変えちゃうのよ。中身が一緒であっても名前を変えちゃって、広告もそこの一貫性を持って、プロダクト、広告、ターゲットっていうものを全部一貫性を持って、これをポートフォリオ化していくことによって、アテンションを引いてても、このキャラでいてもおかしくないみたいな感じになってくるのかなと思って。
- 村上
- 1人の人がそれをやってたら、あれ?キャラ違うじゃんとか、一貫性ないじゃんになっちゃうけれども、いろんな人を起用するといいよねっていう感じですよね。
- 佐藤
- そうそう。っていうふうにしておけば、アテンションをめちゃくちゃ引くのがうまいやつ。全員アテンションを引くのがうまくなくてもいいわけだから。アテンション引くやつのトップバッターみたいなやつがいて、それを先ほど毛受さん言ったように、この反応はいいよね、このユーザーにとってこのデータでアテンションの仕方はいいよね、強いよねっていうの。じゃあ、それはいいじゃないって話だったら、それはそれでどんどんやってもらって。で、そいつが引っ張ってきたやつを、要は、実はこういうやつもいてみたいなとか、もうちょっと温厚な話し方をするやつとか。ここにきたやつに対してちょっと温厚めでいくとか、っていうふうに戦略を組んでいく必要があるのかなと思うんだけど。
- 原
- 一旦、仮定を置くじゃないですか。仮定を置いて、そこからバリエーションを増やしていく感じなんだと思うんですよね。仮定で例えば5本、最初に走らせました。ここがそこから先のマーケティングで持ってきたデータが、そっから二つずつ増えていって10バリエーションになって、そのうち当たらないやつを削っていくっていうのを続けていく感じなのかなと思うんですよね。
- 佐藤
- それはね、多分フェーズによって変わるのかなと。例えばこの商品で市場を切り開きますってなったときに、今からポートフォリオを作っていこうってなったときに、話し方の。それはテストマーケティングとして、キャンペーンとしてそれを展開していくと。ABテストでこういう話し方で話した。その中でよかった話し方だとか対話に対して確立させていって、あとは無理がないように持続可能に一貫性を持ったメッセージ。企業もわけがわからなくなってくるじゃん。このランディングページ作ってこういう話し方した、このランディングページ作ってこういう話で、もう一発で終わってたりとかもするし。よかったからもう一回やってみるかとかじゃなくて、もっと定義していくと簡単になってくるし持続可能なのかなと。気を引くやり方も全部テンプレート化してくるからやりやすいし。
- 原
- だんだん廃りはやりもあるじゃない、表現の仕方。だからそこも加味して、
- 佐藤
- そこは加味して変化していけばいいから。
- 原
- でも、これポートフォリオとして、みんながみんな同じようなかたちでできるかっていうと、そういうわけじゃないと思うんだよね。
- 佐藤
- だから持続可能なビジネスを築くって、簡単に考えると価値を高めていきましょうだし、本質を高めていきましょう、少しずつユーザーを集めていきましょう。それが多分当たり前の話ではあるんだけど、そうすると商品力だと価値の戦いになるじゃん。これはこれでいいんだけど、だけどそれだけじゃ市場ってつまんないじゃん、競争って。マーケティングは面白いし、セールストークがクリエイティブだから売れてもいいと思うんだ。
- 原
- 引きの部分のところの話だね。
- 佐藤
- そうそう。ただそれがユーザーが疲弊するような市場にしちゃいけないんだよね、ばんばんお互い試しあって。そういうのはやっぱり選ばれなくなってくるから、排他的に消えていくだろうし。だけど、その中でもいい要素もあるわけじゃん。注意喚起っていうかさ。え?このままだとこういうふうになっちゃうかも。今すぐ何々をするにはみたいな。まあ、アートリーアカデミアとかもやっとんだけど、そういう言い方で(笑)。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- アテンションめちゃくちゃ引いてることやってんだけど。
- 毛受
- さっき丈亮さんおっしゃってたけど、アテンションを得られる人っていうのは、魅力の一つでもあるんじゃないかなと思うんですよ。ばしっと注意を与えれる人。それがプラスでもマイナスでも何かちょっと強さがあるというか、魅力の一つでもあるので、そこを上手やっていくっていう中では、もうちょっと見る視点を変えていく。顧客が今、何を悩んでいて何を求めているかっていうのもしっかり見て、そこにかけていかないと、あの企業があのやり方やったからやってみようとかだとばれるよねっていう。今あれがはやってるから、じゃあ踊ってみるとか、それで当たればいいんですけど、やっぱりそこって違うんじゃないかなっていうのは思います。しっかり見る、あとは魅力を高める。アテンションかけて、ばしっとくるような自社だったり、人の魅力を高めていくっていうのもいいんじゃないでしょうかと思います。
- 原
- それはブランドだったりアイデンティティーをもっと明確にしていくってこと?
- 毛受
- も、一つですよね。
- 佐藤
- 要は信頼っていうところが多分最終的な着地になると思うんだけど、注意を得られるにしても、持続可能にするためには信頼。信頼がないと持続的な人間関係が作れないじゃん。エンゲージメントが作れないじゃん。信頼に基づいているから、本質で言うと。だから注意を引いて目立つことは重要なんだけど、その先には結局、信頼経済の、さっき言ったんだけど、信頼を落とし込まなきゃいけない。だから、さっき毛受さんが言ったように、はやってるからそれやったらばれるよねっていう、合ってないことばれるよねの話で、それが当たればいいんだけど、当たるってことは信頼関係のうえでやってもおかしくないからいいわけじゃん。だから信頼関係が崩れるようなメッセージの仕方はしちゃいけないっていう話なんだよね、多分。
- 村上
- 本質とその中身っていうのと、その発してる内容っていうのが一致しないとだめだなんですね。
- 佐藤
- そうそう。一致しないといけない。だからキャラクター性、ブランドアイデンティティが大切になってくる。ブランドアイデンティティの信頼感を、信頼残高をどうやって高めていくか、蓄積していくか。メッセージがそのブランドアイデンティティにとって言ってることがおかしくないかっていう話なんだよね、多分。
- 毛受
- そうですね。そうすると持続可能っていうようなものにつながるんじゃないかなと思うんですよね。アテンションエコノミーとは何かっていうよりも、そっからの持続っていうところにつなげていくには、注意を引くだけでは難しいんじゃないかなとは思うので、じゃあそれするにはどうしたらいいかって信用信頼、あなたの約束を守りますよ、あなたとの約束を守りますよっていうところがあればいいんじゃないかなと思いますけどね。
- 佐藤
- じゃあ一回、それでソリューションを書いてみたいと思います。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- はい、本日のソリューション、こちらです。
- 井戸
- お願いします。
- 佐藤
- 注目の責任を。
- 一同
- おおー。
- 久田
- 美しい。
- 佐藤
- かなと。一言でまとめると。注目を引く以上、責任もちゃんと伴うように、注目してみんな見てるんだから、そのあと何をするか。信頼してもらえるような言葉をとか、信頼してもらえる価値を提供していこうっていう話。だから注目にちゃんと責任を取らないといけないっていう。そうすれば持続可能なビジネスができるんじゃないか。どう思います?(笑)。
- 原
- やりっぱにしないってことだね。
- 佐藤
- やりっぱが一番いけない。だから意味がわからんっていうか価値が低くなっていっちゃうから。
- 毛受
- 責任ですね。
- 一同
- (笑)
- 久田
- 美しくまとまった(笑)。
- 毛受
- しみじみ(笑)。
- 佐藤
- すごくいい言葉だね(笑)。
- 原
- 一気に重くなったからね(笑)。ほかの同業種ではなくて他業種とも争わなきゃいけない中で、その責任ってやっぱりコンプラ上も本来あっていいと思うんだよね、会社のコンプラ上で。
- 佐藤
- そうですね、それも責任だもん。
- 原
- 責任の中でさ。そういうのって、やっぱりコーポレーションガバナンスの中でも、結構今後出てくるのかなって今の話を聞いて思ったんだよな。
- 佐藤
- 大体、炎上しててとかっていう、YouTuberとかでも炎上したりだとかするじゃん。結局あおるだけあおって責任が取ってないから信頼残高が下がっていって、持続可能なYouTubeができないわけじゃん。それこそ、ずっときてるHIKAKINさんとかなんかさ、あんまりそんな過剰な企画はやらないじゃん。やったとしても多分責任取ってんだよね。あおりに対しての責任を取ってるから。アテンションって、だから言い方を変えるとあおりにもなるわけだから。あおりに対して責任を取ってる人は持続可能で信頼してファンが継続していくから。過激な言い方をしてもいいんだよね、キャッチーな言い方してもいいんだよね。だけど、ちゃんと責任が取れるんですかっていうところが。
- 村上
- 結局、自己責任ですよね。自滅してっちゃいますね、ただ過激なことを言って逮捕されちゃう。
- 佐藤
- そういうことよ。というわけで、責任のあるアテンションをということで。
- 井戸
- ありがとうございました。次回以降の放送はこちらのとおりとなっています。来週も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また、次回もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
プレイフルネスで中小企業の創造性を高める!楽しく成果を生み出す、新しい働き方を実現するには
2024.07.18 放送分
オーセンティシティでブランド価値を高める!真実性と透明性で顧客の信頼を得るには
2024.07.11 放送分
ベンチャークライアントモデルでスタートアップとの連携が鍵に?成功のための戦略と実践方法を見つけるには
2024.06.27 放送分
デジタルノマドの誘致合戦が開幕!世界中からプロフェッショナルの才能を得てイノベーションを加速するには
2024.05.23 放送分