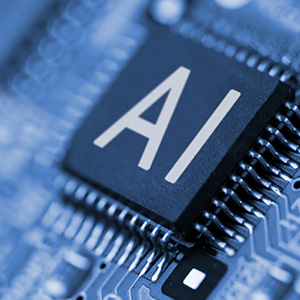2023.04.20 放送分
【リテールメディア】リテールメディアでチャンスを掴むには?
第128回アートリーアカデミア
THEME
【リテールメディア】リテールメディアでチャンスを掴むには?
リテールメディアとは、小売業者が所有するデジタルプラットフォームや店舗内のチャンネルを活用して、ブランドやメーカーが広告やプロモーションを行う手法を指します。近年、消費者の購買行動や情報収集の方法が多様化する中、リテールメディアはブランドと消費者との新しい接点として急速に重要性を増しています。では、このリテールメディアの潜在的なチャンスを最大限に引き出し、成功を手にするためにはどのような戦略が求められるのでしょうか。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、今夜も始まりました、アートリーアカデミア。
- 井戸
- 本日のテーマは、リテールメディアを活用してビジネスチャンスをつかむには。さっそくフリップを見ていきましょう。リテールメディアの仕組みの資料となっています。広告主は、小売事業者が持つ消費者データを活用してターゲット層に広告配信することが可能です。
- 蒲生
- 昨年の2022年からよく耳にするようになった言葉になります。こちら、小売事業者が運営するECサイトだったり、店舗アプリ、リアル店舗のサイネージを広告プラットフォームとして提供するビジネスモデルが新しく生まれてきたっていう、そちらの概念になっております。
- 佐藤
- これはよその広告が入ってくるってことですね。
- 蒲生
- そうですね。
- 佐藤
- そうだよね。結局、リテールテイメントとかで店舗の本質的な価値っていうのが、それこそ店舗に来て、商品だけ見てネットで買うみたいな、安いところでみたいな、そういうこととかもあったりするし、店舗も結局広告収入が入るって話だよね、これは。
- 蒲生
- そうです。これまでの事業活動とはプラスした新しい収益のかたちです。
- 佐藤
- 新しい収益モデルってことだよね。
- 蒲生
- が生まれてるんですね。
- 佐藤
- イメージ的にちょっと違うけど、タクシーとかが広告出してるよね。ああいうようなイメージ。結局、ウェブっていうか、インターネット広告側も、要は出稿する先っていうのは需要と供給が合ってないから、広告市場の、需要のほうが多いんだよね。要は、ウェブメディアに企業が出稿する広告を耐えきれるだけの看板と場所がないわけよ。
- 原
- 足りないっていうことですか。
- 佐藤
- 足りないっていうのは前からいわれてて、時間の問題でリテールだとか、普通に居酒屋とかだって滞在してて、ウェブサイトだって何分とかの滞在の世界で、居酒屋とかで飲みに行って滞在してたら何時間とかじゃん。
- 井戸
- 確かに、チャンスがいっぱいあるってことですよね、見てもらえる。
- 佐藤
- そう。ペルソナとかもハッキリしやすいし、だから結構理にはかなってるよね、仕組みとしては。
- 蒲生
- 昨年から耳にするようになった流れとしては、サードパーティークッキーが規制されたりとか、コロナ禍でEC需要が高まってったりとか、あとテレビ離れっていうのが重なって、こういうビジネスモデルが注目されてるっていうところで、今後のリテールメディア広告の市場についてのフリップがございます。
- 井戸
- リテールメディア広告市場規模の推計と予測となっています。縦軸が金額、横軸が年度となっておりまして、緑色がデジタルサイネージ、オレンジがオンラインメディアを示しています。
- 佐藤
- これ、先生どう見ますか。
- 原
- 数字的な、金額的な部分は、こんなにこんぐらい上がるのかっていう見方にはなるんですけど、思ったのが、今の需要と供給のバランスじゃないけれども、新たなリアル店舗からすると、収入のベースが増えるっていう見方になっちゃうけど、広告を出す側からすると、情報が要はもらえる中、どんな客層か見える中で打ちやすいというところの反映のさせ方、どのような、じゃあ、商品がいいのか、どんなサービスがいいのかというのは、よりわかりやすいところで、伝えやすいというところで、自然と広がりやすい市場なんだろうなというような見方にはなってますよね。
- 佐藤
- 安い市場。
- 原
- あと広がりやすい。
- 佐藤
- 広がりやすい市場。
- 原
- 広がりやすい市場なんだろうなって。
- 佐藤
- 属性がはっきりしてるもんね。例えば、じゃあ、ユニクロはちょっとあれかもしれんけど、H&Mとか、割と価格層とかもわかりやすいんじゃん。そこへ対して、例えばアパレル以外の、それこそ化粧品だとかもそうだし、そういったものとかを差し込みやすいよね。
- 原
- そうね。しかも意識関係がしやすいというか、目に入りやすくなりますもんね、興味がもともとあるところだから。そういう意味でも効果は大きいんだろうなっていうのもやっぱり思いますもんね。
- 佐藤
- そうだね。
- 原
- だから、すごい需要広がるんだろうなって。
- 佐藤
- これ、渡邉さんどうですか、リテールメディアっていうところ、可能性で言うと。
- 渡邉
- これってセレクトショップの、もしくはブランドのショップの新作のPVみたいなのを映してるのはよく見るんですけど、アパレルで別の広告のを流す場合も、もう今あるってことですか。
- 佐藤
- 広告、メディア側がOKだったら、要は媒体側。
- 渡邉
- 関連する、
- 佐藤
- 店舗側がOKだったらって感じじゃない。それどこまで進んでるかわからないけど、インターネットだとアドネットワークっていうのがあって、プラットフォーム化してんだよね。要は、広告の場所を入札したい人たち、出稿したい人たちと、あとは広告メディア側、媒体側としては広告を入れてほしい側、それはアドエクスチェンジっていうんだけど、広告をそれがリアルタイムビッディングっていう、RTBっていう仕組みがあって、リアルタイムで入札がかかるっていう。だから、何が表示されるかってのはわかんない、メディア側としてはね。だけど、そこは一応例えばGoogleだとか、そういうところがユーザーとかのデータを持ってるから、ある程度属性に合った広告っていうのが表示されるような仕組みになってるんだけど。それとは別に、例えばプレースメント広告っていうのがウェブ上にはあったりして、要はここのメディアに出稿したいですっていう。
- 原
- もう指定がある?
- 佐藤
- 指定ができるっていうこともできるんだね。もちろんそれのほうが入札単価は上がってくるんだけど、そこまでの仕組みがリテールメディアのほうにあるのかどうかっていうのはわからないんだけど、だけど価値としてはウェブサイトと店舗との違いってそんなないから、そういう目で見ると。そういうものが導入されていく可能性もあるし、より最適化、リテール側もメディア側としても広告主を探しにいかなくていいっていうメリットはあるよね。だけど、今言われたように、競合の広告が流れる可能性もあったりするから、
- 原
- 入札だったらそういう可能性ありますよね。
- 佐藤
- そう、だけど、その辺はNGワードとか、そういうNGとか、そういうのはあらかじめ、例えば同業のあれはなしとか、そういうことは設定的なことはできるのかもしれないけど、でも恐らくそこまでの仕組みよりは、直接買いつけてくるようなイメージのほうが、今は主流なのかもしれない。そこまでのプラットフォームというのがあるっていうのはあんまり聞いたことないから。
- 原
- 逆に要は特定のっていうところで上げていきたいっていうところが、明確に広告主としても、媒体側としても、そこは明確になりやすいってことなんですね。
- 佐藤
- そうだと思う。恐らく広告代理店が入って、それこそ電通とかが、じゃあ、H&Mだとか、ユニクロだとか、まあわかんないよ、っていうところに提案しにいって、これを全店舗でとか、そういうことはあるかもしれないね。どうですか、じゃあ、VEDUTAのショップがあったとして、じゃあ、看板の代わりだよね。そこで家賃だけでも浮くとか、そうなってくると、ひもづけすると結構出店もしやすい状況というのは作りやすくなってくるもんね。
- 原
- ブランディングフィーが入ってくるもんね。大きいですよね。固定費の部分をまかなえるための広告収入ベースっていう計算できますもんね。
- 佐藤
- そう。だからそういう全く新しいビジネスモデルを取り入れるようにしたから。今までだと、コロナ禍であんまりユーザーっていうのが、どっちかというとオンライン、オンラインのECサイトとかも含まれるけど、そっちのほうはよく目にするんじゃないですか。だけど、これからリアルのほうのリテールのほうもメディア化していくっていうところもあるかもしれない、今後はね。
- 渡邉
- カルティエがカフェをカタカナでカルチエっていうカフェがあって、
- 佐藤
- あれポップアップストアだね。
- 渡邉
- ポップアップストア。あれも何かリテールのメディア化みたいにいわれてるんですけど、あれとこのサイネージはまた別物ですよね。
- 佐藤
- そう。メディアっていうのは、結局、人が集まるだとかっていう意味になってくるんだけど、媒体っていう意味になってくんのね、メディアっていうのは。
- 渡邉
- あれは写真映えスポットいっぱいあって、そこを写真撮ってSNSで来た人がばーっと拡散するみたいな意味でのメディアっていう意味って書いてたんですけど。
- 佐藤
- 捉え方、メディアっつってもやっぱいろんな意味があるからあれだけど、ただ、今、インターネット広告業界からするとメディアっていうと、媒体のことだから。だから雑誌だとかテレビだとか、そういうものとあんまり変わらない、見方としては。だからそこのカルティエのポップアップストアで、例えば、メルセデスとかの広告とかが流れたりだとかしてたら、それはここで言うリテールメディアになるのかなっていう。でも、どうなんだろうね。これ市場規模として何かもっともっと可能性があるような気がするんだけどね。805億円でしょ、これ?
- 井戸
- うん、です。
- 渡邉
- アメリカですとこの100倍ですもんね。800億ドルとかですもんね。日本は100分の1、市場規模。
- 佐藤
- そう考えると、どうですか、先生。
- 原
- もっと、じゃあ、伸びそうだよね。
- 佐藤
- 市場規模としては、だいぶ小さいよね。
- 原
- 小さいよね、これ見てるところって。だって、もっと電通とかは躍起になってやる。だって市場としてはここから魅力のある話じゃないですか。だから、余計もっと広がる要素はあるよね。金額としては、それはアメリカまではいかないのはあるにしても、1兆とかのベースの話なんじゃないのかな、本来動き回るお金の量ということでは。
- 佐藤
- まあ、そうだね。その意味ではどう思う、七菜子は。
- 久田
- 広告業界として見ると、もっと広がっていってもいいかなっていう気はしますけど、ただ、ウェブのメディアとは違ってリアルの店舗って、どうしてもサイネージを置かないと流れないじゃないですか。そこの設備投資を、じゃあ、すべての小売りがやれるのかっていうと、結局看板の数の話になってくのかなっていう気は、伸びにくいというか。
- 佐藤
- そうだよね。
- 原
- 限られてくるっていうことですね。
- 佐藤
- あんまり置きたくないのかなっていうのも、
- 久田
- ごちゃごちゃしそうですしね。
- 佐藤
- 感じられる。
- 久田
- 結局、じゃあ、同業を除外は当然するとして、VEDUTAのお店に行って、ピンクでふりふりのものとかが流れてたら、何かこうブランドが壊れるじゃないですか。そこのリスクはある気がする。
- 井戸
- 世界観ね。
- 佐藤
- そのあたりが、だから、うまく同調するといいんだけどね。
- 久田
- そこはもうプラットフォーマーが出てきて、うまくしてあげると、より参入しやすくなりますよね。
- 佐藤
- そうなんだよね。だから、ECサイトとかになってくると、本当にあれって店舗ってよりは棚のイメージがあるじゃん、陳列棚みたいな。店舗ってなってくると、体験っていうのを提供するために出店するわけだから、人も選んで、内装も金かけて、そこでやっぱ崩れる可能性があるとか、大体デジタルサイネージがそもそも合わないっていう場面もあるかもしれないし、なかなか全部が全部とは言いきれない。
- 原
- 業種によるでしょうしね。売ってるものとリンクどこまでさせるのって話ですよね。
- 佐藤
- そこら辺のボーダーをやっぱり海外とか、アメリカだとか、中国ってのは超越してんじゃないかなって思うんだよね。
- 原
- 特化してるところはありますよね、確かにね。
- 佐藤
- 市場はやっぱ思ってるよりも小さいなっていう感覚はある、予想としてはね。これ、いつの資料かにもよるけどね。コロナ禍がまだ終息が見えない状況でのあれだったのかもしれないし。
- 蒲生
- 資料自体は1年前なんですけど、おっしゃるとおり、日本の市場が極めて低いです。渡邉さん言ってたように、800億円とかいわれていますけど、今年の時点で全世界的にはこれ160兆っていってます。
- 佐藤
- やっぱそうでしょ。
- 久田
- 円?160兆。
- 蒲生
- 円。
- 佐藤
- だから、やっぱそうだよね。それぐらいの話だよ。
- 蒲生
- 極めて低いですね。
- 佐藤
- インドとかは結構盛んだったような気がするんだよね。
- 久田
- インド?
- 佐藤
- インドは海とかにデジタルサイネージを浮かべて、そこに広告流したりだとか、そういうのをやってるのとかあるし。
- 原
- やること違う。
- 井戸
- 規模が(笑)、すごい。
- 佐藤
- そう。やっぱりグローバル的に見ると、グローバル企業っていうのがやっぱり現地に対してローカライゼーションでやっぱそういうこと、発展途上国とかは逆にそういうので外貨を得たいから積極的かもしれないよね。
- 原
- 取り入れやすいし、取り入れたいになりますよね。消費を促したいですしね、国内で。
- 佐藤
- あんまり発展途上国、じゃあ、ブランドっていうところに対するリテラシーが醸成されてるかっつったら、そこはまだクエスチョンだし、何となく。
- 久田
- やり方自体が多分まだ固まってないですもんね。いろいろ試していこうって中だから、取り入れるのも。
- 佐藤
- ある種、そこは感覚がカオスになってるってのあるじゃん、残ってるじゃん。
- 原
- 人口数の多いところにそれをやるっていうふうにやると、結局検証はしやすいですから、なおさら一遍やってみようの話は多分出てきますもんね。
- 佐藤
- だから欧州とかやってくると、日本もそうかもしれないけど、ただやるだけじゃなくてスタイルを求められる。
- 久田
- 欧州うるさそうっすね。
- 佐藤
- うるさそう。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- どこの店へ行っても追っかけてくるみたいな、サードパーティークッキーみたいに、何か。
- 久田
- また何か言い出すじゃん。
- 原
- これまた見るのみたいなのがね。
- 佐藤
- リターゲティング広告されてくる。どこの店舗行っても全部同じ広告が流れてくる。。
- 一同
- (笑)
- 原
- この人はこれ好きっつって。
- 佐藤
- で、これ結局どこで買えるのみたいな。買えるわけじゃないから。
- 井戸
- 広告でしか知らんみたいな。
- 佐藤
- 訴求されてるのに買う方法がない。
- 原
- それはそれで不満になるかもしれないね。
- 一同
- (笑)
- 蒲生
- 続いて、企業の活用事例がございます。
- 井戸
- リテールメディアの活用事例です。ファミリーマート、レジの上部にサイネージを設置して、売れ筋商品や広告、ニュースなどの情報を流し、視認率を計測して改善につなげています。Amazonは、ECサイト内の検索ワードに対してマッチする内容の広告(スポンサー枠)を出すようなシステムでリテールメディアを提供しています。
- 原
- あれ、レジ上のディスプレイですよね。あるね。
- 井戸
- ありますね。
- 原
- 3台ぐらい置いてありますよね。
- 佐藤
- あれ、でも、自社の広告っぽいけど。
- 原
- ぽいよね。
- 佐藤
- でも、コンビニは相性よさそうだけどね。何かもう割とごった返してるから、コンビニっていろんなジャンル。それはいいよね。Amazonは基本的にスポンサー枠っつっても、自社で売ってるやつを出してるだけだから、リテールメディアっていうよりは、レコメンドエンジン的な感じだよね。
- 原
- 促す側ですもんね。
- 佐藤
- まあ、なかなか難しいよね。このメディア側も結局要はマネタイズがされてるメディアだったら、やっぱりよそに飛ばしたくないっていう思いもあるし、特にこういうモール型になってくると。だから、どっちかというと、やっぱりブランドサイトとかが広告を入れていくっていう。
- 井戸
- ブランドサイト。
- 佐藤
- そう、オウンドメディアで結局はブランドサイトみたいな。
- 原
- だから、もうある程度限られてるところですよね。
- 佐藤
- っていうところの枠がはずれてくると、ちょっといろいろ。ただ、流出する可能性があるから、結局ね、そこが問題だから。
- 久田
- 扱ってる商品が違うとはいえ、気が散ってどっかへいっちゃうのはすごいデメリットだなって思うんで。
- 佐藤
- だから、そこがポイントだよね。
- 久田
- ウェブは特にもう、店舗は体が店舗にあるからどっか行っちゃうことがないじゃないですか、メディア流してて。それ、そもそも、だから、さっきの話じゃないけど、どこで買うのっていう話だし。でも、ウェブはもうクリックした瞬間飛んでいけちゃうから、すごい離脱が増えるんじゃないかな。それって小売側としてデメリットのほうが大きいんじゃないかなっていう気はしますけど。
- 佐藤
- クリックできない広告にしときゃいいかもしれない、テレビCMみたいにね。
- 久田
- 飛んでいけないってことですか。見るだけ?
- 佐藤
- 要は刷り込み系の広告だよね、CM、コカ・コーラとかさ。ああいうやつとかは向いてるかもしれない。
- 原
- 飛ばせないやつ。
- 井戸
- 見るだけ。
- 佐藤
- 車とかさ。基本的にすぐ購入できんじゃん、車。
- 久田
- 確かに、すぐ買わないものだったら違和感ない。
- 井戸
- すぐ買いたいものだと、飛べんのだけどってなるけど(笑)。
- 佐藤
- だから、プリウスとか、例えば今だったら、新型プリウスとか。動画っていうのがポイントだからね。
- 久田
- 動画前提なんですか。
- 佐藤
- まあ動画も流せるじゃん、デジタルサイネージだからでしょっていう。
- 久田
- サイネージだったら動画ですね。
- 佐藤
- だから理解促進させるような広告とかだったりとか、プリウス新しいの出てるよみたいな。知ってる人たちは知っとるわけよ。じゃあ、何が変わったのかっていうのを流すとか。
- 原
- ブランドイメージをつける動画もあれば、細かいことを伝えるやつもあったりとか。
- 佐藤
- タクシー広告とかそうだよね。あれもクリックできるわけじゃないし、ああいう感じに近いものだったら使いやすいかもしれんな。一回ちょっとテーマ見ていきましょうか。
TOPICS
テーマ討論
- 井戸
- リテールメディアを活用してビジネスチャンスをつかむには。
- 佐藤
- ビジネスチャンスをつかむにはってことなんですけど、渡邉さん、どうですか。VEDUTA、アパレルブランドっていうところで、よくポップアップストアとか、今度も伊勢丹さんで、また毎年決まってる、3年目です?
- 渡邉
- 3回目。
- 佐藤
- 3年目。
- 渡邉
- おかわりきました。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- どうですか。じゃあ、ご自身のポップアップストアに置くっていうようなイメージになってくるんだけど、例えば。
- 渡邉
- いや、ぶっちゃけ僕はそれより丈亮さんたちにやらしてもらった、ファッションショーの動画をプロジェクターで流したり、言ったんですよね。人にかまってられないんで、
- 一同
- (笑)
- 渡邉
- 自分の本業をまず広めないとっていう。別に家賃が発生するわけでもないので、ポップアップショップ。なので、でも、手段として、自分でお店を家賃出して構えるってなったときに、関連性のある盆栽の動画流すとか、伝統工芸の制作風景とか、そういうのだったらいいかなとか、海外を着物着て旅行会社と提携して旅行会社のCM流すとか、そういう着物を着た先の機会の創出の企業、それを支える企業のCMとかだったらいいかなとか、そういうのは思いますね。
- 佐藤
- そう考えると、あれかもしれんね。インテリアとして成立する広告じゃないと厳しいのかもしれない。リーテールメディア、リアルの店舗。
- 渡邉
- なじむというか、世界観を壊さないやつだったらいいかな。
- 佐藤
- そうだよね。だから、それこそ企業がそのビジネスチャンスをつかむっていうところで言うと、3者あるんだよね。結局、広告を出稿する側、広告を表示する媒体側、あとはそれを受け持つプラットフォーム。この3者がこのビジネスチャンスっていうか、市場が出てくる話になってくるんだよね、結局は。
- 原
- どこでどこに入るかっていうところ。
- 佐藤
- どこに入るかっていうところはあるよね。
- 原
- じゃあ、今、逆にこの市場としては膨らむ要素が大きいところだから、プラットフォーム側にって名乗りが出てくるところは次々にまだ出てくる可能性があるってこと?
- 佐藤
- だし、そこで言うと、もう既にウェブのプラットフォーたちがいっぱいいるし、それこそ多分そういったIT関係のベンチャーだとか、そういったところがアナログに展開広げるっていう、もう既にオンライン上ではリテールメディアやってるからっていう方法もあるし、じゃあ、今度はリアル店舗に強い、例えば電通だとかもそうだし、場合によっちゃあ不動産屋とかがそこに参入してくると、結構面白い感じでしょうね。
- 久田
- つけて賃貸する。
- 佐藤
- そうそう。だから、逆に言うと、ここ条件つきでとか。結局、ビルのオーナーからしてみたら、利回りが上がる話になるじゃん。
- 原
- そうだね。場所が広ければ、そのぶん見てもらえる、認識させてもらえる部分も、
- 佐藤
- 人通りが多い場所だとかだと、そういうこともあるし。
- 原
- 昔の立て看板の考え方が、不動産である貸し物件とかのところにリンクしてくるって話なんですよね。そういう話だもんね。
- 佐藤
- そういうこともあり得るし。
- 原
- 不動産、そこら辺は広がりそうですよね、実店舗っちゅうところで言うと。
- 佐藤
- 例えば、交渉が入ったときに、家賃交渉とかが入ったときに、じゃあ、これリテールメディア化させて、その広告収入を取らせてくれとかっていうような場面とかね。
- 原
- 交渉の材料になるって、面白い話だけど。
- 佐藤
- 例えば、コロナ禍がはやったときに家賃控除って入ったじゃん、たくさん、いろんなところが。もしそういうものが普及しているのであれば、じゃあ一斉にそういうものを入れるとか、でも、人が来ねえから、結局、って話なんだけどね。
- 久田
- 小売りと相性いい、小売りというか、薄利多売とすごい相性がいいなと思って。ブランドになっちゃうと価値が別のものになるから、どうしても自分のブランドとの兼ね合いが出てくるけど、言ったらあれですけど、ファミレスとか、その辺で別にそんなに自分のブランドを守らなきゃいけないものがないから、で、飲食とかになれば滞在時間も長いし、美容院とか、飲食とかの滞在時間長いもので、ブランド価値はあんまり重視しない薄利多売系のものだと、すごい相性いいなって、聞いてて思いましたけど。
- 佐藤
- 百貨店とか、デパートとか、スーパーマーケットだとか、ああいうところは特に相性がいいだろうね。
- 原
- 多数の人が来るし、世代層も広がってるからですよね。
- 佐藤
- そうそう。だから、モールだよね、いわゆる。アナログで考えると。
- 原
- イオンとかそういうところは、逆にむしろ積極的に出してくる可能性がある。
- 佐藤
- 出してくるんじゃない。だから、そこに対して出稿できるよっていうのが、リアルだと難しさはあるね、やっぱり。そこの店舗ですぐ購入できるとか、そういうところがやっぱ求められるから。
- 原
- 求められちゃいますよね。ネットだったら、その場でクリックだったのが、そういう時間差出ちゃいますもんね。
- 佐藤
- そうだね。だから、多くの会社はどっちかいうとメディア化していくほうにチャンスがあるんじゃないかなとは思うね。大きい会社とか、モール、イオンとかそんなもの簡単に導入して、そこの中でビジネスモデルが成り立っちゃうじゃん。自分とこの店舗だとか、ほかのイオングループの広告流してやるとか、それで成り立っちゃうじゃん。そうじゃなくて、そういうのって今までもやってきてた話であって、じゃあ、これからの価値って何かっていうと、そういった個店さんとかでも、そういったものを取り入れることによって、利回りが上がるっていうよりは、どっちかというと家賃をそれでまかなえるとか、
- 原
- 発想としてのね。
- 佐藤
- そう、これはある種、だから、考え方によってはサステナブルなんだよね。結局、自分とこの商品が売れないとか、やっぱりその販売力っていうところがまだやっぱ醸成されてないような個店さんとかが、小売店とかがそういうものを導入することによって、プラスの収益になるから。だから、選択肢の幅が広がるっていう話だから、
- 井戸
- ほかのところに費用を使うっていう選択肢もできるわけですもんね。収入得られたぶん。
- 佐藤
- そう。だから、渡邉さん、先ほどポップアップストアだから、お金もかからないしっていうところで、伊勢丹でって話だったんだけど、じゃあ、例えば、伊勢丹よりももっと、例えば表参道の路面店、1カ月いけます。だけど、じゃあ普通に考えりゃばか高いじゃん。家賃何百万の話になるけど、だけど、それをリテールメディア化してやることによって、例えばそれが30万まで抑えられるんだったら、ちょっとチャレンジしてみたいなっていう選択肢が増えることになる。だから、そこ、普段、普通だったら入れないようなところが、それを活用することによって入って、そこはブランドっていう世界観としては、確かに100%表現することはできないのかもしれないけど、それがあることによって認知機会を得るっていう、トレードオフとしてっていう可能性はあるのかなっていう。
- 渡邉
- それはありますね。
- 久田
- でもありですよね。すごいいいですよね。
- 佐藤
- だから、そういう意味では、それこそスタートアップの会社だとか、大手にはかなわないような小さい会社とか、ブランドたちが、チャンスをもう一発取りにいけれる可能性があるよねっていう。しかも、そこって多分思うんだけど、もちろん例えば場所がよければ、ある程度店舗が変わったとしてもデータが残ってるじゃん。で、ここは例えばこの時期になると、この季節、例えばゴールデンウィークになると、こんだけ人が入るとか、こうだとか、ああだとか出てくるじゃん。そういうデータとかも取れるから、店舗側も逆に提案しやすい可能性もあるし、仮に前テナントが入ってたところが立ち退いてってときでも、大体過去のデータがっていうところで、それを居抜きじゃないけど、それとしてデータをあとの人に提供するか、提供しないかっていうところの活用も出てくるかもしれないし、選択肢が増えるんじゃないかなって思うよね。
- 原
- 考えてたのは、ものを売る側の発想でどう活用するかっていうふうに考えてたんですね、ずっとこれ、調べていく中で。でも、そうじゃない、今の話を聞くとね。
- 佐藤
- そうじゃないよ。だって、メディア化するってことは収入が増える話だから、だからサイドビジネスの話なのよ。
- 原
- そういうことだよね。
- 佐藤
- サイドビジネスがひもづきでやるからこそ、普段ハードルが高かった場所に出店できるとか。これってウェブ上だったら、本来はアクセスを取って作ってから、アクセス数が価値になるから。だけど、路面に関しては、要はイニシャルとランニングが耐えれるかどうかっていうところでジャッジして、人が最初から入るところに飛び級で入れることができるわけじゃん、お金さえ払えば。今まではそこが難しかったから、なかなか小さい店舗とかは入れんかったけど、
- 原
- 可能性が高くなるもんね。これ、今の話。だって、固定の支出が減るのに、やれるベースはきちんと作れるってすごい魅力的だよね。
- 佐藤
- そう、だから、例えば、じゃあ、VEDUTAが表参道のこういうとこに入りますとか、例えば銀座のこういうとこに入りますってなったときに、じゃあ、そこの層って、例えばVEDUTAに反応する顧客がたくさん歩いてて、相性いいよね。だから、「「場所」×「人」×「そこに入るブランド」」、ここの三つの要素を並べたときのポテンシャルっていうところを見て、一回やってみようかっていう。で、いろんなところが協力して、そこに突っ込んでみようと。そこから得られる収益の可能性が享受できる人たちが多いからさ。これ、はやるよねとか、刺さるよねとか、ここにVEDUTAってこういうブランドがここに店舗入るんで、例えばどこどこさん、一回ここのリテールメディアとして、そこに広告出稿しませんかっていう、ここに仲介人がいれば、そういうのを成立させることができるよね。で、この人は、VEDUTAのそれこそ売り上げなのか、家賃なのか、わかんないけど、そこから収益を取るっていう。この店舗、このブランド、この店舗入ったら絶対売り上げ増やせるじゃんみたいな、イニシャルでちょっと払いにくいから、よそのやつを引っ張ってきて、要は出資させるような感じね、広告として。
- 原
- 本当に、だから、スポンサーだよね。
- 佐藤
- だから、本当のスポンサーとしてっていう。っていうようなプロデュースの仕方はリテールメディアでもあるし、場合によってはリテールテイメントとしての考え方になるし、これは結構プロデューサー側としては結構面白いし、プロジェクトを実現するためのツールになりやすい可能性もあるのかなっていう。
- 原
- そうだよ。目的じゃないんだよね、これ手段だよね、本当にあくまでもね。でも、発想的な部分で言うと、今までのリアル店舗のやりにくさみたいなところがどうしてもあったじゃないですか、コロナ禍の状況下で。でも、それがだんだん変えやすい要素になってきてるので、すごくいいことだなと思っていて。お金の回し方自体の在り方が、小さいショップでも出せる、立地的な部分もそうなんだけど、広げやすいっていうところもイコールになるじゃないですか。なので、一遍に多店舗にいい立地のところに出すっていう発想もイコールで出やすいっていうところもあるかもね。
- 佐藤
- そうだね。特に最初のうちって、やっぱ店舗出店するって博打的な部分あるじゃん。果たして入るのかどうかっていう、様子も見たいし。それが最初からこういうリテールで、メディアとして活用できるんだったら、ある程度データがあるから、そこに対して見込み、予測値っていうのはもうちょっと解像度が上がった状態で、出せる可能性は出てくるよね。
- 原
- 実際にそれをつなげる側としては、データドリブンしたうえで、こんだけの要素があるからさっていうのも逆に言えるわけですもんね。要素としていろんな部分を持ってこれるから、だから金額だけの話じゃない。
- 佐藤
- (笑)、先生突然目覚めたね。
- 一同
- (笑)
- 原
- 話の切り口が広がったんで、なるほどなと思って、すごい楽しいになって。どうやって売るかっていうことばっかり考えてたの、これ広げて。でも、違うわと思って、すげえ楽しい、今。
- 佐藤
- 一回、ソリューション出しましょうか。
TOPICS
ソリューション
- 井戸
- では、お願いします。
- 佐藤
- 本日のソリューションできました。本日のソリューションはこちらです。WEBメディアから始めよう。リテールメディアって結局ウェブ上であっても、リアル上でも、リテール、小売店をメディア化しようという話ですと。さっき言ったように、小さいブランドだとか、スモールビジネスだとか、スタートアップでもチャンスあるよみたいな話なんだけど、それはそれとしてリスクもあるし、とはいえ、でも、そこの解像度を、データを持ってれば、そういうのも実現しやすくなってくるじゃん。だから、まずはウェブメディアから始めて、ある程度アクセス数を作った状態で、そこで広告をウェブ上の広告リテールメディアから始めていって、大体こういうユーザーは、うちのユーザーはこういう広告に対して反応しやすいですよっていうデータが最初からできてれば、広告代理店とかもそこを持ってきやすいし。
- 原
- 拾ってもらいやすいし、こちらからも打ち出しやすいいみたいな。
- 佐藤
- そうそう。だから、アーティストとかインフルエンサーみたいな感じ。ある程度SNSで先にもう人気出しといてやるっていう。
- 原
- そのほうが反応させやすいもんね、確かにね。
- 佐藤
- どのみちウェブメディアとリテールメディア両方あれば、両方のデータの行き来もできるし。
- 原
- 広がりますもんね、取れるデータ情報が。
- 佐藤
- そうそう。だから、OMOマーケみたいなのもやりやすいし、という感じです。
- 井戸
- ありがとうございます。
- 佐藤
- さあ、いかがでしたでしょうか。
- 蒲生
- 僕も原さんと同じく、どう売るかっていうふうな考え方、僕ら広告代理店事業をやってるんで、どうクライアントに提案するかっていうのをいろいろ考えてたんですけど、確かに三つのかたちがありますよね。出稿主とプラットフォームと小売りと、その全部を含めて最終的にはそういうソリューションでよかったんじゃないかなと思います。
- 佐藤
- そうだね。まあ、販促に活用当然できるんだけど、それってやっぱ販促っていうのはビジネスモデルの一部でしかないから、新しいビジネスのチャンスを作れるのかなっていうね。
- 原
- いろんな角度から見たときに答えがあって、すげえ思った、ああって。
- 佐藤
- くそって感じでしょ。
- 原
- 思ってる。
- 佐藤
- もっと思慮を深めてれば、もっと話したかったみたいな、そんな顔してるもんね(笑)。
- 原
- 調べたときには、出てくる案がここしかなかったのがちょっと悔しかったなと思ってるよね。
- 佐藤
- 先生もちょっとリテールメディアしたほうがいいんじゃないですか。
- 原
- 本当ですよ。
- 佐藤
- (笑)、どういう意味。
- 原
- 本当ですよ。上げとかな、自分で。
- 井戸
- どういう意味?
- 原
- メディアとして上げとかなあかん。
- 井戸
- ニュアンスでしかない。
- 佐藤
- ありがとうございました。
- 井戸
- はい、ありがとうございました。次回以降の放送はこちらのとおりとなっています。来週も木曜日の夜10時にお会いしましょう。また次回もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
コミュニティサイトがマーケティング戦略の中心に!強力なコミュニティを形成してビジネスを成長させるには
2024.06.15 放送分
ダイナミックプライシングで収益最大化?リアルタイムに変動する価格戦略で企業の競争力を高めるには
2024.06.07 放送分
MFAサイトが生成AIで量産される!悪質なコンテンツファームに負けないマーケティングを成功するには
2024.05.10 放送分
ビジネスをゲームチェンジ!ゲーミフィケーションで顧客体験を変革するには
2023.11.09 放送分