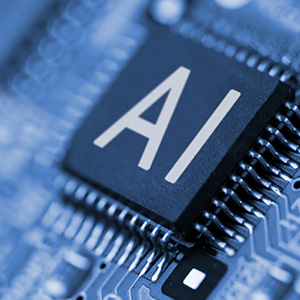2023.08.04 放送分
【リスキリング】リスキリング教育を実践して社員の力を伸ばすには?
第144回アートリーアカデミア
THEME
【リスキリング】リスキリング教育を実践して社員の力を伸ばすには?
急速な技術進化や業界の変動、グローバルな競争の中で、企業が持続的な成長を遂げるためには、社員一人ひとりのスキルの再定義や更新が欠かせません。リスキリングとは、これらの変動に対応するために、既存のスキルセットを再評価し、新しい能力や知識を獲得する教育の取り組みを指します。アートリーアカデミアでは、どのような答えを見つけたのかをご覧ください。
TOPICS
フリップ解説
- 佐藤
- さあ、今夜も始まりました、アートリーアカデミア。
- 井戸
- 本日のテーマは、リスキリング教育を実践して社員の力を伸ばすには。さっそくフリップを見ていきましょう。教育におけるリスキリングの位置づけの資料となっています。
- 蒲生
- リスキリングとは、大前提、企業が時代に合わせて必要なスキルを社員に教育をするっていうことが前提になっておりまして、スキルアップとか、リカレントっていうのも検索するといろいろ出てくるんですけど、スキルアップは現状のスキルを磨くこと、リスキリングは新しいスキルを身につけるというので、そこが違うところです。リカレント教育っていうのは、個人が身につける、個人が身につけるものを選ぶ。リスキリングは企業がこれを身につけといてって与えられるもの。生涯学習はまたちょっと違って、個人の趣味、興味に基づいて、ボランティアとか社会活動の中で学んでいくことということになります。
- 佐藤
- これ、先生どうですか。
- 原
- それこそリスキリングって言葉が、今、すごくちまたでは多く出てきてるし、会社としての体制で見たときに、どこまで会社として身につけてもらうのかっていうところに、会社の在り方っていう、ここをそれこそ明確に線引きできるものと、できないもの出てきそうだなっていう気は、私はしていて、どうしても企業主導になると、この業務に適したっていうふうになるから、そこら辺の部分、教育の体制の在り方って、会社も例えばそれこそDXとか、ああいう部分で言うと、どんどん会社って取り組んでんだけど、結局外部委託だったりって多い話なんだよね。そこら辺で、個々が望んでる、従業員の人たちが望んでいる部分のところまで満たしたものを教育としてやれてるのかどうなのかっていうのも、一つの課題点ではあるのかなというふうには思うんですけどね。
- 佐藤
- だから、よそに求めてるスキルだとか、成果物を、最初はそういうかたちで導入はするんだろうけど、ちゃんと中まで進んでいるのかっていうことですね。
- 原
- そうそう。
- 佐藤
- ってところが疑問視されてるっていう。
- 原
- そうですね。かたちだけになってないかっていう話ですね。
- 佐藤
- そういうことだよね。
- 蒲生
- 続いて、改めてリスキリングの定義と、こちら必要とされる背景についてフリップがございます。
- 井戸
- リスキリングの定義と必要とされる背景です。リスキリングとは、時代の変化によって、これから必要とされる新たなスキルや知識を、従業員に身につけさせるために行う教育のことを指します。
- 蒲生
- こちらDXとか、脱炭素社会とか、あらゆる変化を伴うにつれて、従業員のスキルが陳腐化してっていっちゃいけないと。陳腐化していくと、結果的にそこの企業のポテンシャルも陳腐化していく。それを打開するために、リスキリングが必要というふうにいわれております。
- 佐藤
- 脱炭素社会で言うと、多分能力値を上げる必要があるんだよね。電気を基本的に使わないとか、そういう話になってくるでしょ。
- 原
- そうなる。
- 佐藤
- だから、より短時間で今までやってたことをやれよって話だもんね。
- 原
- そうなってくるよね。
- 佐藤
- だから、言ってしまえば、働く人たちのスキルをもっと全体的に上げていこうよっていうのが国策的にあるってことだよね、思惑として。
- 原
- そうです。
- 蒲生
- このようにビジネスの環境の変化に対応していく企業というのが大事になっておりまして、リスキリングを遂行するうえでのメリット、デメリットが次にございます。
- 井戸
- リスキリングのメリット、デメリットの紹介です。メリットが企業の競争力を向上させる。従業員の働きがいを創出できる。雇用コスト、離職コストを削減できるといったことが挙げられてまして、一方でデメリットのほうには、教育コストが発生する。学んだスキルを生かせない可能性がある。モチベーション維持が難しいといったことが挙げられています。
- 佐藤
- これ、七菜子、どう?
- 久田
- リスキリング、何かうまくいく体っていうか、リスキリングしようとしても覚えれない可能性があるじゃないですか、結局本人の資質だったりっていうところで。そこが一番デメリットな気がするなっていう気がしますけどね。
- 佐藤
- 本人の受け皿的な部分だってこと?
- 久田
- そうですね。企業の思惑と本人のやれるやれない、
- 井戸
- 才能とかもありますね。
- 久田
- 才能とか、
- 井戸
- ポテンシャルが。
- 久田
- で、結局リスキリング教育を行ったけど身にならないとかってなってくると、その1番もそうですけど、すごい教育コストっていうのは発生する。
- 佐藤
- でも、目的はもちろん従業員のスキルが今の時代に合ったかたちに、即したかたちになっていくっていうことなんだろうけど、これが、だけど、特定の人の成果っていうところじゃなくて、そういう取り組みをやってるよっていうふうになってくると、全然多業種からどんどん職が失われていくこの時代背景があるじゃん、AIだとか、主にAIなんだけど。そういうところで絶対離職してくる人間たちを、じゃあ、あそこの会社は自分たちでも雇ってもらえるんだみたいな、採用戦略的にリスキリングやっているよっていうふうなかたちで捉えるんで、企業って絶対個で見んから、言っても。要は効果で見るから、だから結局リスキリングをやって、そいつらがうまくいってるかどうかっていうよりは、大体何割ぐらい生産性が上がったよねとか、多分そういったところの問題なんだよね。当然、その素養だとか、受け皿が多分高い人たちがいて、それでそいつらの、より効果が高まればいいことなんだろうけど、企業としては、じゃあ、その人がうまくいかないからっていう考え方じゃないほうがいいのかなとは思うんですけど、どう思いますか、その点で。
- 原
- 私、その点、それこそ佐藤さんと同じ意見で、多分教育コストが発生するとか、やれる人とやれない人がいるのは、多分今までもあったんだよ。要は配置換えとかでも当然あったところなので、そこはもうやむを得ないのかなと思っているんです。ただ、ここから人手不足だって、労働人口が減っていく中で、じゃあ、ほかの職業をやってる人がうちにくるときに、こういう教育体制があるんです、ここまで落とし込めるんですって見せれることがまず一点。もう一個が、時代の流れに合わしてる会社だっていうのを、対外的に見せていくっていうことも大事だっていう話も会社としてはあると思うので、そこの視点がもう一個あるのかなというふうに思う点ではありますね。
- 佐藤
- 本当に、だって、これリスキリングって言葉が出だした頃に、リスキリング採用とか何かできるんじゃないかなとか思って、そういう広告をSNSでばらまいたろかなと思ってたんだけど、割とアカデミアって早いうちから取り扱ってたじゃん、このワード。今、当たり前にやってるもんね、リスキリング採用、リスキリング転職とか、広告打ってますもんね。だから、それぐらいやっぱりリスキリングやってるっていうことだけでも、企業の競争力を向上、1番にあるように、ここが多分一番大きいのかなとは思うけどね。
- 原
- ここを第一にまず考えなきゃいけない状況になってるしね、実際に。
- 佐藤
- そう。だから、結局このデメリットで言うと、教育コスト発生するのはしょうがないんだけど、このスキルを生かせないとか、モチベーション維持は難しいって、これどっちかいうと、リスキリングの問題よりも、採用の質の問題になってくるもんね。要はそういう人たち選んでんでしょみたいな。じゃあ、そういう人事にリスキリングしたほうがよくね、まず。
- 一同
- (笑)
- 原
- 採用のベースのね(笑)。
- 井戸
- そのリスキリング採用って具体的にどういうふうにやってるんですか。この募集している職種に対して、未経験でもいいよっていう打ち出し方なんですか。
- 佐藤
- 多分そういう感じよりは、単純に今はやりのパワーワードだから。
- 井戸
- 前面に出していってるってことですか。
- 佐藤
- だから、異業種に転職するっていうところを、IT業界にリスキリング転職とか、そういうような感じがキャッチーですね。
- 井戸
- キャッチーですね。
TOPICS
テーマ討論
- 佐藤
- 一回、テーマ見ていきましょう。
- 井戸
- リスキリング教育を実践して、社員の力を伸ばすには。
- 佐藤
- 企業として取り組みはっていうところはもちろんそうなんですけど、実際に、でも、成果の部分を入れていくとやっぱ社員の力、ちょっと矛盾しちゃうけど、さっき言ったことと。だけど結局は社員の力を伸ばすっていうのが最終的なKGIになってくると思うから、これなんかどうでしょう?渡邉さん、どうですか、リスキリング。
- 渡邉
- 丈亮さんと仕事するようになって、経営目線とか、プログラミングまではできませんけど、顧客のデータ分析とか、そういうのは意識して勉強というか、学んで、売って終わりじゃなくて、解析したりとかして、次に商品開発に生かすようにはしていますかね。
- 佐藤
- でも、そうだよね。だから、結局そういうモチベーションのある方っていうか、やっぱ取り入れたいと思う力を持ってる人たちだったら、そもそも従業員がとかじゃなくて、協力会社がとか、パートナーがとか、勝手にだからそうやってリスキリング、今までも勝手にされとったいうことなんですね、多分。
- 原
- そうです。言葉としてはリスキリングっていう言葉がなかったけどねって話だと思います。
- 渡邉
- 足りないものを吸収して、
- 佐藤
- っていうのが、普通に人としての在り方じゃん、多分、生きてくうえで。今はだから、どっちかというと、平成の時代、いわゆる大手に勤めることが一番よしとして、生涯安定みたいな。だから、もうリスキリングもくそも、入ったらもうOKみたいな、終わりみたいな感じな風潮があったんじゃないの、流れ的に。
- 原
- あったと思う。
- 佐藤
- その結果、だから、競争社会、グローバル競争の社会で遅れを取ってきているという結果になっちゃったと。隣の韓国や中国からもそうだしみたいな。アジアを代表する国だった日本が、今はもう結構、とはいえだとは思うけど、そこを危惧して、じゃあ、ちょっとやっぱおまえらももうちょっと頑張って再教育せなあかんのだよっていうような流れになってくるんだね。
- 原
- そうだね。年齢層もだからちょっと話を聞いてる限りでは、年齢層高めなんですよね。
- 佐藤
- そうなんだ。リスキリング対象がね。若いと勝手に、だから、触発し合う。
- 原
- そうそう。慣れちゃうじゃないですか。でも年齢いってて、俺この仕事だったっていう人たちが、リスキリングの対象になってるから、言葉としては走ってる感じはしますよね。
- 佐藤
- じゃあ、キャリア持って踏んできた人でも、やっぱ自信のある方たちでも、実績作ってきた方でも、今、時代的に自分要らないよっていう、その仕事要らないよ、AIやれるよ、外国人やれるよみたいな。
- 久田
- 容赦なくリスキリング対象、
- 佐藤
- になっちゃうわね、今。
- 久田
- (笑)
- 原
- 年齢層、ある程度、だから、それこそ私、今、47なんですけど、私よりもちょっと上の世代、第2次ベビーブーム層よりもちょっと上の層はリスキリングの対象にはなりやすいんですよね。
- 佐藤
- じゃあ、定年迎えるだけだった人たちが、もう人生100年時代とかいって、もう70〜80まで働けみたいな感じになってきてるから、もうちょっと新しいことにリスキリングしましょうっていうふうになってるってことだよね。
- 原
- そうです。
- 佐藤
- ちょっと話は戻って、社員の力を伸ばすにはっていう、何かさっき反対意見だったけど、逆の目線で見るとどう?
- 久田
- とりあえず危機意識というか、まず置かれてる状況、もう本当個人に対してになってきますけど、置かれてる状況もリアルに説明して、だから、このリスキリングが必要なんだよっていう、個人が、じゃあ、絶対にこれを習得しようっていう気持ちを持たせないと、結局リスキリングするってことは、元の技能があるわけじゃないですか。そこの技能にいつでも帰れるんだって思って、じゃあ、何かちょっとお遊びで覚えようかなぐらいのテンションでいると一生育たないから、とにかくもうおまえは元の位置には戻れませんから、今すぐ新しい椅子を獲得してきてくださいっていう感覚を持たないと、きついのかなっていう気します。
- 佐藤
- なるほどね。でも、これリスキリングは、思うんだけど、2パターンありそうだよね。要は、このポジションになってほしいっていう場合と、適正スキルを見たうえで、その人のために仕事を作ってあげる場合と。大体中小企業の場合って、こういう経営戦略的にこのポジション全部必要だからっつってそろってるっていうことがないでしょ、基本的には。会社組織として成長させていくっていう中で、じゃあ、人事ができてくるとか、採用の広報ができてくるとかっていう話じゃん。そういう、だから、このポジション足りてなかったよねっていうところを、リスキリングで埋めるっていう、その人の適正スキルを見てっていう。結局、だから、普段からその人をプロファイリングする必要があるとは思うけどね、やっぱり。
- 原
- これ人事の面から見たときに、そこをどこまで落とし込めるかっていう評価制度だったり、先ほどの素養の話で言うと、能力としての診断テストみたいなやつありますよね。ああいう部分を、じゃあ、こまめに見ていって、リスキリングできる要素がここにあるっていうのを、会社のほうで先に積んどいたうえで、ここの部分足りないからこっちっていうふうに言える状況を作っていくっていうのが、それこそ実践していくうえで、教育やっていくうえでの前提条件として必要という考え方にしたほうがいいっていうことなのかなって、今、話聞きながら思ったんだけど。
- 佐藤
- だから、常に、会社には、今後こういう必要な職業がありますよっていう、こういう役割の仕事をする人たちが必要ですよっていうのを先に出しておくと。
- 原
- 出しておく。
- 佐藤
- そうだよね。すごくロジカルにめちゃくちゃシンプルなこと言ってるけど、そうやって会社に必要であろう職能と、職務と、この人一人ずつのプロファイリングを持ってリスキリング対象の人たちみたいなっていうのを照らし合わせていきゃいいってことだよね。
- 原
- まず、そうだよね。必要だよね。じゃないと、思ったように成長してくれないに今度なっちゃうもんね。
- 佐藤
- そうだよね。リスキリングするっつったって何かしらのリスキリングする方向性が必要だもんね。これ、実際リスキリングやってる会社っていうのはどういう取り組みをしてるの?
- 蒲生
- 実際は大手が主なんですけど、もう大手ですから、社内で研修プログラムを開発しちゃって、それをもう全社員10万人とかにやって、それのスコアが人事評価につながってたりとかですね。主にDX人材の育成のテーマがよく見られる感じです。
- 佐藤
- 世の中的にDX人材をリスキリングするっていう、リスキリングっていうのも大体DXの話になってくるのか。
- 蒲生
- 大テーマですね。
- 佐藤
- なるほどね。だから、デジタル人材の話なんだ、結局。
- 原
- そういうことになるね。
- 佐藤
- だから、アナログやってきた人たちをデジタルにさせると。なるほど(笑)。
- 原
- これはこれで結構、でも、難しいところだよ。
- 久田
- ちょっと話変わってくる。
- 佐藤
- そういうことか。そうするとあれだね。でも、うちって結構DX化させてきてない?
- 久田
- いや、私もともとめちゃくちゃアナログ人間ですからね。もともとファッションデザイナー志望で、専門も出てるし、アートリー入って、
- 佐藤
- DX化されてるね。
- 久田
- プログラミング、DXされて、DX人材な。
- 佐藤
- そうだよね。だから、割と、だって、DX、全然畑違う人連れてきて、
- 久田
- ずっとやってましたよね。
- 佐藤
- 俺、ずっとやってきてるわ、それで言うと、DXのリスキリング。やっぱ経営者って普段リスキリングする人多いんかな。
- 原
- 少ない。むしろ定着化させたい、一つの業務に、ほうが多い。むしろ、だから、佐藤さんみたいに考えるタイプのほうが少ない。
- 佐藤
- そうなんだ。
- 原
- だって、役割に合わして人を入れるの感覚だから、基本がね。
- 佐藤
- でも、それはあるじゃん、当然。
- 原
- もちろん。でも、そこの部分をそこから、じゃあ、こうだねって、なかなか横展させれない。
- 佐藤
- じゃあ、特殊だね。
- 原
- 特殊だね。スイッチが早いんでしょうね、そういう意味で。
- 久田
- 何か感覚布教ですよね。
- 佐藤
- 布教(笑)。
- 久田
- モチベーションもビジョンとかを埋めて出荷されてくるから育てやすいですよね。
- 佐藤
- そういうことだよね。
- 原
- 土壌が、だから、整ったうえで送られてくるんだから、従業員の人としても変わりやすいんだよね。
- 佐藤
- そこがないと、だから、いかないよね。だから、社内の人たちをポジション変えるにしても、一発布教入れてから、教育のほうに走らんとだめなの。
- 井戸
- 布教っていうワードがすごいしっくりきた。
- 佐藤
- (笑)
- 久田
- 本当に布教ですよ。
- 佐藤
- そういうことだよね。
- 原
- そうだね。だから、教育のやり方の前の段階が重要だって話だからね、今の話は。
- 佐藤
- そうだよね。それがないから、果たして布教っていうワード、今、何か通称布教になってるけど(笑)、
- 原
- でも、浸透のさせ方、
- 佐藤
- リブランディング的な、インナーブランディング的なやつをやってから、リスキリング入らないとだめなわけだよね。
- 原
- そうですね。
- 久田
- そりゃそうですよね。不満っていうか、出やすいですよね。何で?みたいな。
- 佐藤
- だから、考え方的な方向性を調整したりだとか、多分そういうこともあると思うんだけど、だから、人材エージェントとかがやってるようなことに近いかもしれない。その人のスキル見たりだとか、その人の趣味、趣向だとか、好き嫌いとか、そういうものが合うかどうか見て、こういうとこいけんじゃない?こういう企業文化いけんじゃない?とか、そういうようなことだよね。その人たちがリスキリングすることはないもんね、基本的に。コーディネートする感じなんだね。働き方をデザインするってことだよね、ある意味。
- 原
- そういうことかもね。
- 佐藤
- デザイン経営的な感じで、前回の。
- 原
- そうだね。でも、そういう話になるよね。人事とそういうふうに生かしていくって話だからね。切り口変えてこういうふうにやってみましょうよの話だから。
- 佐藤
- そうそう。それ、なかなか、じゃあ、新しいことやってきて、セミナー受けてきてとか、コンサル入れて、この人ちょっとやるから、ワークショップやるからっつっても、なかなかうまくいかないよね。
- 原
- いかない、うん。
- 佐藤
- いく人といかない人が出てくる。
- 原
- やったところで受け入れられない人のほうがいるもんね。
- 佐藤
- やっぱそれじゃない?だって、結局、人の動機って好きか嫌いかやん。
- 原
- 大事なとこはそこですね。そこだと思う、確かにね。
- 佐藤
- 責任じゃねえわ、やっぱり。好きか嫌いかだわ(笑)。
- 井戸
- シンプル。
- 久田
- 好きを見つけてあげるのか、好きにさせるのかの話な気がしますけどね、今のは。
- 佐藤
- でも、どっちも一緒だと思うよ。好きにさせるのって、好きになる要素を見つけないと、その角度で攻めていかなきゃいけないから。
- 久田
- そんな都合よくみんな好きばっかじゃないし。
- 原
- 大体、人も疑心暗鬼からスタートするからね。それを好きにしていってあげることは、会社としても大事だもんね。
- 佐藤
- そういうことだよね。なるほどね。何でなるほどって自分で納得してるの。
- 一同
- (笑)
- 佐藤
- まあ一回入りましょうか、ソリューション。
- 井戸
- はい、お願いします。
TOPICS
ソリューション
- 佐藤
- じゃあ、本日のソリューションはこちらです。社員の好きを見つけよう。
- 一同
- うん。
- 佐藤
- はい。あんまり、これ正確かね。そういう社長さんもいたりだとか、人事も、人事はそういうこと見るのかな。
- 原
- そこまで見ないと思う。
- 佐藤
- あんまりそこまで見ないよね。
- 久田
- これは正確だよ。丈亮さん、だって、人のことめちゃくちゃ好きだもん。
- 佐藤
- 俺、全然好きじゃないよ。
- 久田
- うそ。
- 一同
- (笑)
- 久田
- すぐ気づくじゃないですか。髪の毛切ったねとかさ。
- 佐藤
- ただ気づくだけだよ。
- 原
- 素の素養の部分を見抜くのがうまいじゃないですか。
- 佐藤
- いや、でも、俺が見抜くのうまくても、みんながどうやったらできるかのところだもんね。
- 原
- もちろんね。
- 佐藤
- じゃあ、次の課題になっちゃうんだね、じゃあ。どうやって好き見つけるの?って話だ。
- 原
- 見つけるのかって話になってくるね。
- 佐藤
- 一回ちょっと明かり戻して(笑)。
- 井戸
- ありがとうございます。盛り上がっちゃって。
- 佐藤
- そうだね。だから、好きってどうやって見つけるかだね、相手の。
- 井戸
- 相手の好きを、
- 佐藤
- でも、これ気づくかどうかなんだって、相手の気遣い、心遣いのほうだと。多分、なべちゃんが相手の好き見つけんのうまいと思う。
- 渡邉
- 相手の好き?
- 佐藤
- うん。相手がどういうことを好きなのかっていうのを見つけるのうまいじゃん。
- 渡邉
- 俺あんま人興味ないんだよ。
- 一同
- (笑)
- 井戸
- 無自覚なんじゃないですか。
- 佐藤
- いや違う。多分、人が好きじゃないやつのほうが、人の好き見つけんのがうまいだって。洞察の話だよ。だから、ぼーっとしとったら多分これはできんかもしれないね。
- 原
- できないね。だから、背景の一部に人間見てちゃだめだって話でしょ?
- 佐藤
- そうそう。だけど、人の好きを見つけようっていうのを、何かフレームワーク化していきゃいいよね。こういうこと教えるときテンション高そうだなとか、こいつ何か鼻歌歌っとるなとかさ。逆に嫌いを見つけるのも重要なんです。
- 井戸
- うん、苦手だもん。
- 佐藤
- こういうことやってるとき、貧乏ゆすりしてるだとか、こういうことをしてるとき、無視されるなとか(笑)。
- 井戸
- あるんだ。
- 佐藤
- そういうのすごい人の態度の変化をすごく気づくから。
- 井戸
- なるほどね、すごいな。
- 佐藤
- でも、好きを見つけてあげて、その人に合ったことにリスキリング、一個前の話だよね、だから。こういうプログラムでリスキリングしていきましょうって作るのはいいんだけど、そこの部分にふるいにかけるところは、人の好きをベースにしたほうがいいんじゃねえのっていう、嫌いなことにリスキリング無理やりさせてもストレスたまってくだけだから、ってことだよね。そうだと思う。
- 原
- そうだと思う。今の話聞いててそう思った。
- 井戸
- 納得。
- 佐藤
- っていうことじゃないでしょうか。
- 井戸
- ありがとうございました。
- 佐藤
- 効率のいいリスキリングをっていうところ。
- 井戸
- では、次回以降の放送はこちらのとおりとなっています。来週も木曜日の夜10時にお会いしましょう。次回もお楽しみに。
- 佐藤
- 最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
番組の感想をシェアしませんか?
みんなに共感を広げよう!
RECOMMEND おすすめ番組
エモーショナルインテリジェンスでチームワークを強化する!感情の理解と管理で組織をドライブするには
2024.07.25 放送分
リベラルアーツが成功するプロフェッショナルを育てる!⼈間の教養を⾼めてビジネスをアップデートするには
2024.02.01 放送分
2023.07.20 放送分
【クリティカルシンキング】クリティカルシンキングを活用して仕事の質を高めるには?
2023.06.08 放送分